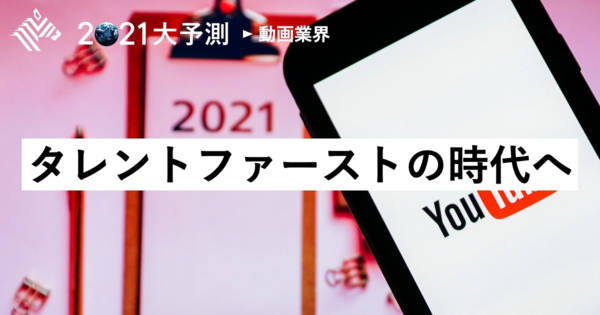【動画業界】レッドオーシャンのYouTube。勝ち抜くカギは?
コメント

注目のコメント
株式会社ケイコンテンツの平山と申します。
私の経験から拙文ながら記事を書かせて頂きました。
今時流に乗るYouTube。
しかし「YouTubeとは?」という概念は、
コンテンツ制作の目線からいくと
突き詰めればありません。
データ分析、アルゴリム解析、
その他YouTubeのお作法などはありますが
全ては コンテンツの結果から弾き出されるものであり、
「卵か先か、鶏が先か」論で言えば、
コンテンツが先とはっきりしているのです。
つまり、YouTubeとはただの「箱」。
無限の大きさを持ちますが、それは箱でしかなく
中身にどんなコンテンツを入れるかなのです。
目に写るもの全てが映像コンテンツになる可能性を持ち、
もっと言えば、CGや漫画など
目に写らないものですら映像コンテンツになる。
昔テレビで流行った企画じゃないですが、
「箱の中身は何だろな?」
人の興味は全てそこにある。
ジャンルはまさに無限。人の興味を満たすならば、
全てに可能性がある。
マスを取れば広告収入で夢を見れるし、
ニッチなジャンルでも関連企業のタイアップがとりやすい。
オンラインサービスに繋ぐこともできるし、
感染症が落ち着けばリアルイベントの集客もできる。
真に優秀なコンテンツならば、
翻訳することによって海外まで無限に広がる。
広告収入も青天井となり、世界規模の成功例が生まれるでしょう。
しかし、上記の夢は「箱の中身」が決めます。
コンテンツありきなのです。
プロの領域に入ったと書きましたが、
だからと言って「戦う権利がない」わけではない。
戦うことは自由であり、
誰も狙わない「スキ」を狙う作戦だってある。
是非挑戦して欲しいと思います!
こんな時代ですが、動画業界の大変革を
楽しんでいきたいと思います!タレントファーストの時代へとあるがまさにその通りで、事務所パワーが強かった時代にはテレビの枠を抑えることができて良かったが、今はYouTubeをはじめ活躍できる場の拡大やそれに伴ってできることが増えているため、現代の事務所は市場のスピードやタレントニーズに合致した付加価値を急速に増やしていかなければならない。
変わらないままであれば辞められてしまうし、付加価値を増やし続けることがタレントに選ばれ続ける事務所として重要だと思います。
また、最近では提供案件や芸能人チャンネルも制作がしっかりと入ることが増えているのでコンテンツがリッチになっていく流れは今後加速していくと思います。