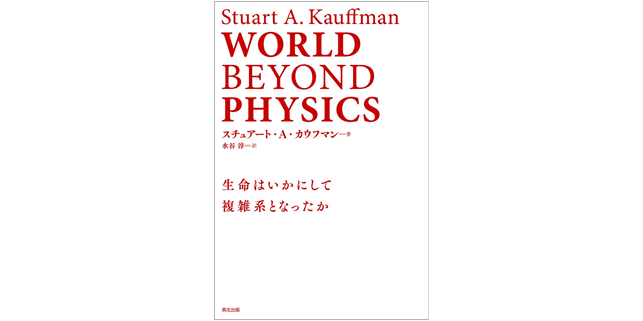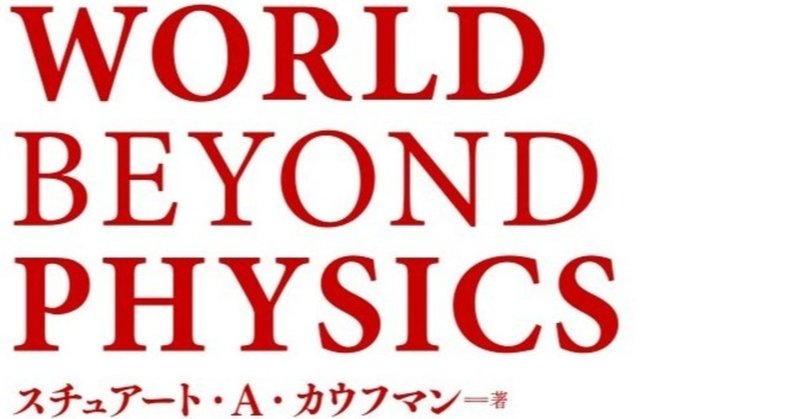
特別寄稿!『WORLD BEYOND PHYSICS』(スチュアート・A・カウフマン 著、水谷淳 訳)【訳者解説】
2020年7月発行、『WORLD BEYOND PHYSICS:生命はいかにして複雑系となったか』の訳者、水谷淳氏による「訳者解説」。本noteへの書き下ろしとなる、特別寄稿です!
『WORLD BEYOND PHYSICS』訳者解説
著:水谷淳
「生命」
それは、誰でも簡単にイメージできる身近な概念だし、具体例を挙げろと言われればいくらでも並べ立てることができる。
ところが、「生命とは何か、厳密に定義せよ」と問われると、はたと困ってしまう。動いているものが生命だろうか? いや、植物の多くはあまり動いているように見えないし、逆に風や川は動いているがどう考えても生命ではない。増殖するものが生命だろうか? 確かにすべての生命は繁殖して子孫を作るが、明らかに生命でないのにどんどん増えていくものはいくらでもある。たとえば、炎は条件さえ整えばひとりでに燃え広がっていくし、ドミノをうまく並べておけば勝手にどんどんと倒れていってくれる。
「生命とは何か」という、身近でありながら深遠なこの問いは、はるか昔からさまざまな人たちが考察を重ねてきた。たとえばアリストテレスは、生命には「プシュケー」というものが備わっていると説いた。「プシュケー」とは要するに「魂」という意味。生命がほかの物体と違うのは、魂という謎めいた存在を内に秘めている点であるということだ。確かに生命には神秘性が感じられるが、それを魂のような非科学的存在に押しつけるのは、それ以上の追求を放棄してしまうことにほかならない。「本当のところは分かりません」と白旗を揚げるようなものだ。
時代が下って1944年、物理学者でノーベル賞受賞者のシュレーディンガーが、『生命とは何か』というそのものズバリのタイトルの本を著した。シュレーディンガーはこの問いに答えるために、純粋に理論的な考察を進めた。非生物である物体は膨大な数の原子がただ集まっているだけで、統計的な法則に従う。しかし生命体の中では、個々の原子が統計的な法則から外れた振る舞いをして、秩序を生み出している。では、そのような振る舞いを見せる物質はどんな性質を有していなければならないか? こうしてシュレーディンガーは、遺伝子がどのような構造を持っていなければならないかを明らかにした。ワトソンとクリックがDNAの二重らせん構造を発見する約10年も前のことである。
シュレーディンガーのこの考察は、理論面から生命の本質に迫るための道筋を示したと言える。さまざまな生物の実例を調べ上げて共通要素を探り出すという帰納的アプローチでは、いつまで経っても答えにはたどり着けない。「生命とは何か」という究極の問いに答えるには、抽象的・形式的な概念に基づいて理論的に生命現象のエッセンスに迫っていく、演繹的アプローチが必要だ。こうしていわゆる「理論生物学」が誕生した。
本書の著者スチュアート・カウフマンは、この理論生物学の第一人者である。1939年に生まれ、1968年にカリフォルニア大学サンフランシスコ校で医学博士号を取得したのち、シカゴ大学で発生遺伝学の研究を始め、ペンシルヴァニア大学で生化学と生物物理学の教授となった。名声を獲得したのは、ニューメキシコ州にある複雑系研究の拠点サンタフェ研究所で、生命の起源・発生・進化の数学モデルを構築したことによる。その後、自らで研究組織を立ち上げるとともに、カナダのカルガリー大学、フィンランドのタンペレ大学、アメリカのヴァーモント大学など各所で教鞭を執っている。
カウフマンは、エントロピーが生命現象の根幹に関わっていると考えている。エントロピーとは簡単に言えば「無秩序さ」のことである。最初は整然と並んでいてエントロピーの小さい原子の集団も、いずれはバラバラになってエントロピーが大きくなってしまう。エントロピーは時間とともに大きくなっていくというのが、この宇宙を支配する根源的原理の一つである。ところが生命は、この原理に背いているように見える。生きている限り秩序立った状態を保っているし、無秩序な物質を取り込んで自分自身の複製を作り上げてしまう。それどころか、単純な生物から次々に複雑な生物へと進化していく。
カウフマンは以前の著書『自己組織化と進化の論理』(米沢富美子監訳、日本経済新聞社、1999年)および『カウフマン、生命と宇宙を語る』(河野至恩訳、日本経済新聞社、2002年)の中で、生命は自己組織化というプロセスによってエントロピーを低く保つことで、生きつづけ、増殖し、進化するのだと論じた。自己組織化とは、単純な要素が多数集まることで、ひとりでに高度な構造や機能が形成されるという現象で、その際に外部のエントロピーの増大と引き換えに自らのエントロピーは小さくなる。しかしカウフマンはこの時点では、生命がこの自己組織化のプロセスを実現させるメカニズムを具体的に考えつくことができないでいた。
それから十数年、カウフマンは考察に考察を重ね、ついに単純な化学物質の集団から生命が自己組織化するメカニズムにたどり着いた。それを論じたのが本書『WORLD BEYOND PHYSICS』である。そのメカニズムの核をなすのが、3つの閉回路という概念だ。ざっくりと言うなら、閉回路とは、何種類もの化学物質がA→B→C→…とバトンを渡していって、最後にAに戻ってくることで形成される、ある種のサイクルのことである。
ちなみに私はここで「閉回路」という訳語を選んだが、これに対応するもとの単語は'closure'である。辞書でこの単語を引くと、数学用語の「閉包」という訳語が出てくる。これは「ある集合を包含する最小の閉集合」という意味で、本書の概念はこれとはまったくの別物なので、このままの訳語を使うのは安易すぎる。サイクルなので「閉じている」のは確かだが、「包む」という要素はどこにもない。バトンが次々に渡されて一周するのだから、「回路」としたほうがいいだろう。そう考えて「閉回路」という訳語に落ち着いたのだが、術語として最適かどうかは識者の判断に委ねたい。
閑話休題。カウフマンが生命の本質として挙げた3つの閉回路とは、仕事閉回路、束縛閉回路、触媒閉回路というものである。本書を先取りしてざっくりと説明するなら、次のようになるだろう。
仕事閉回路の「仕事」とは、要するにA→Bという化学反応のことで、仕事閉回路はA→B→C→…→Aという一連の反応のサイクルそのものを指す。
束縛閉回路の「束縛」とは、Aという物質から何種類もの物質が適当に生成するのでなく、Bという1種類の物質だけが生成するように仕向ける、束縛条件のことである。このような束縛条件が連鎖して1つのサイクルをなすことで、ある特定の仕事閉回路が実現するというわけだ。
しかし反応をスムーズに進行させるには触媒が必要で、A→B→C→…→Aの各反応にそれぞれ別々の触媒が作用しなければならない。そしてそれらの触媒作用は、やはり1つのサイクルを形成することになる。これが触媒閉回路である。
この3つの閉回路を実現させた化学物質の集合体は、自らの秩序構造を維持してエントロピーの増大を防ぐことができる。
しかしこれだけでは、閉回路自体を構成する物質を自力で作ることができない。そのためには、外部から取り込んだ「餌」が一連の反応を経て、必要な物質に変換されるようなしくみ、いわゆる代謝機構が必要となる。そこでカウフマンは、閉回路が適切な代謝反応を触媒し、逆にその代謝機構が閉回路に必要な物質を供給するという、いわば持ちつ持たれつの関係が構築されうることを示した。こうして完成したシステム全体が何らかの膜に取り囲まれたもの、それこそが細胞の起源、原始細胞なのだという。
さらにカウフマンは、このような原始細胞どうしが作用し合うことで、進化が起こって、複雑な生態系が構築されることも示している。Aという原始細胞が、Bという原始細胞の繁栄のための条件を生み出し、BがさらにCの繁栄のための条件を生み出し……、というように、多数の原始細胞がそれぞれの進化を促して、今日の生物圏を形作ったのだという。そして、その各ステップは「事前言い当て不可能」で、その都度、いわば応急修理のようにあり合わせの方法が用いられると、カウフマンは言う。
ここで私は、「事前言い当て不可能」という、あえてぎこちない訳語を選んだ。もとの単語は'unprestatable'で、もちろん著者の造語である。語幹は「述べる」という意味の'state'。これに「あらかじめ」を意味する接頭辞'pre'と、可能を表す接尾辞'able'が付き、さらに否定を表す接頭辞'un'が付いている。すべてつなげると「あらかじめ述べることができない」となる。要するに、「どんな進化が起こってどんな形質が生じるかを、それが起こる前に予測することは不可能だ」ということを表した言葉だが、著者が「私はもっと適切な言葉を知らない」と断っていることを踏まえて、わざとつたない訳語にした次第だ。
カウフマンは自説が地球上の実際の生命や生物圏に当てはまることを示すために、折に触れてDNAやたんぱく質などを用いた具体例を挙げている。しかしじっくり読んでいただければ分かるとおり、この生命の概念はけっして特定の生体物質に限定されるものではない。必要な性質を有する限り、どんな化学物質にも、さらにはどんな物理現象にも当てはまるロジックだ。宇宙のどこかには、まったく違う物質や物理過程で構成された生命が存在するかもしれない。我々の想像のおよばないそのような生命にも当てはまる、カウフマンによるこの生命の定義は、きわめて包括的で普遍的なものだと言えるだろう。
本書は薄いながらもかなり内容が濃く、しかも抽象的で込み入った概念が次々と登場するので、けっして気楽に読めるようなものではない。しかしじっくり腰を据えて読み進めれば、純粋な論理に基づいて生命の定義が展開されていく様に驚くとともに、生命のかけがえのなさ、特別さに改めて気づかされることは間違いない。「生命とは何か」という古代からの問いに対する、カウフマンなりの最終回答が、ここには描き出されているのだ。
水谷淳(みずたに・じゅん)
翻訳家。東京大学理学部卒業。翻訳書に『人工知能 人類最悪にして最後の発明』、『量子力学で生命の謎を解く』、『僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない』などがある。
***
『WORLD BEYOND PHYSICS:生命はいかにして複雑系となったか』
スチュアート・A・カウフマン(著)、水谷淳(訳)
ニュートン以来、この世界のあらゆる事象は物理法則をもとに説明が可能、とされてきました。果たして、「生命の未来」についてもそれは可能でしょうか。
この問いに対するカウフマンの答えは「NO」です。
約37億年の間、可能な限り多様性を高めてきた生命。
いまいる動物について、誰がそうなることを知っていたでしょうか。
いまある植物について、誰がこうなると語れたでしょうか。
進化は事前に言い当てることが不可能な形で進み、この生物圏をますます複雑にしていきます。
本書では、なぜ進化が事前に言い当て不可能なのかを示していきます。
そのなかで、生命システム構築の重要なカギとなる、束縛閉回路(constraint closure)、仕事タスク閉回路(work task closure)、触媒タスク閉回路(catalytic task closure)という3つの閉回路を用いて、増大するエントロピーより速く秩序を増殖させる、いわば物理法則を超えて進む、生命の誕生、進化の謎についても説き明かしていきます。
本書は、著者の集大成といえる作品であり,またそれとともに、もっともやさしく書かれたいわばカウフマンの入門書ともいえる作品です。
カウフマンをご存知の方もご存知でない方も,本書で生命の神秘に迫る旅に出てみませんか。
【目次】
プロローグ
第1章 この世界は機械ではない
第2章 機能の機能
第3章 増殖する組織体
第4章 生命の神秘を暴く
第5章 代謝の作り方
第6章 原始細胞
第7章 遺伝可能な多様性
第8章 我々がプレーするゲーム
エピソード 原始細胞たちの驚くべき実話
第9章 舞台は整った
第10章 外適応とねじ回し
第11章 物理学を超越した世界
エピローグ 経済の進化
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?