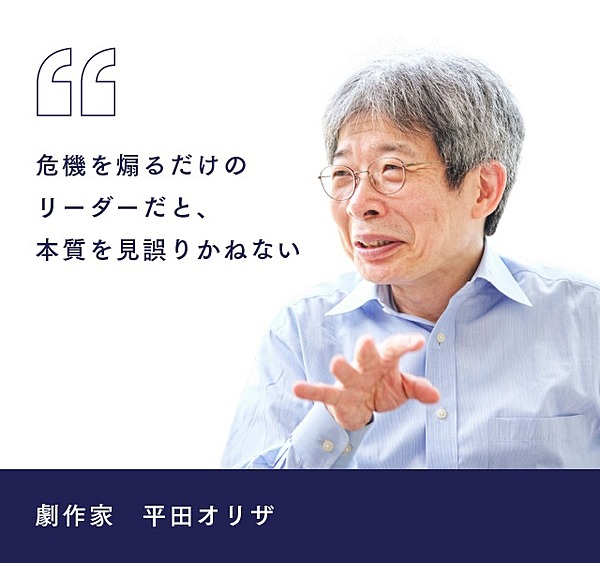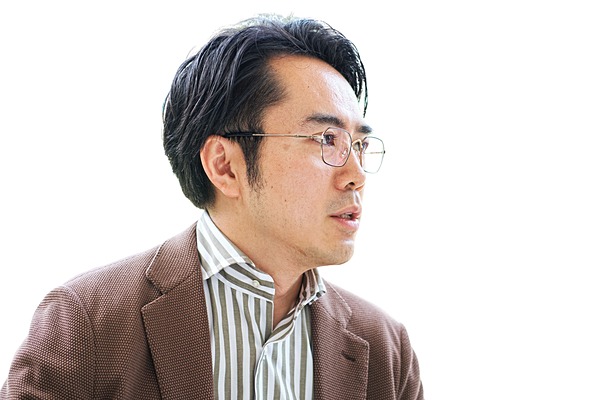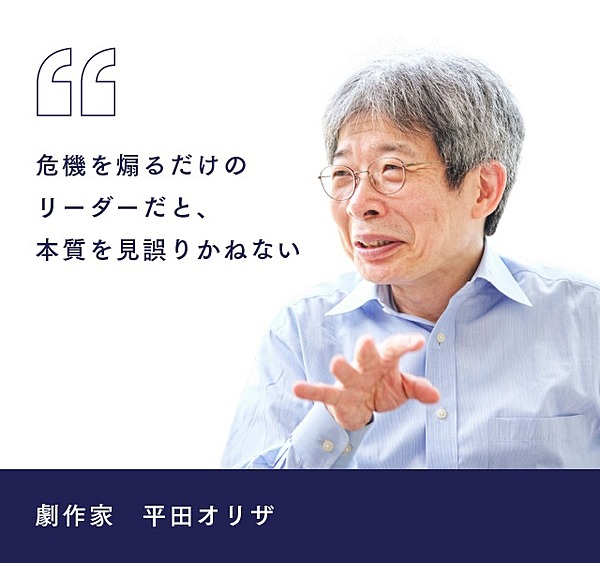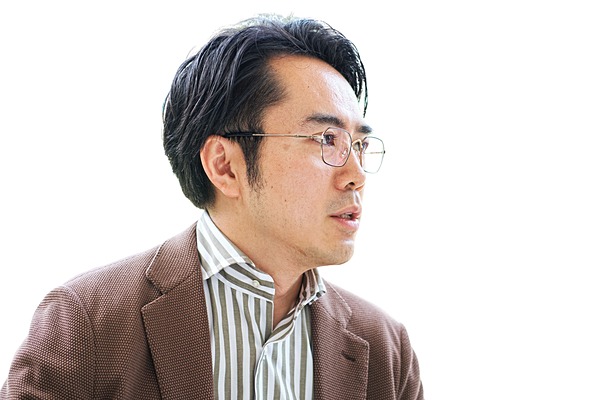“センスのなさ”から始める「発注力」の重要性
2020/9/7
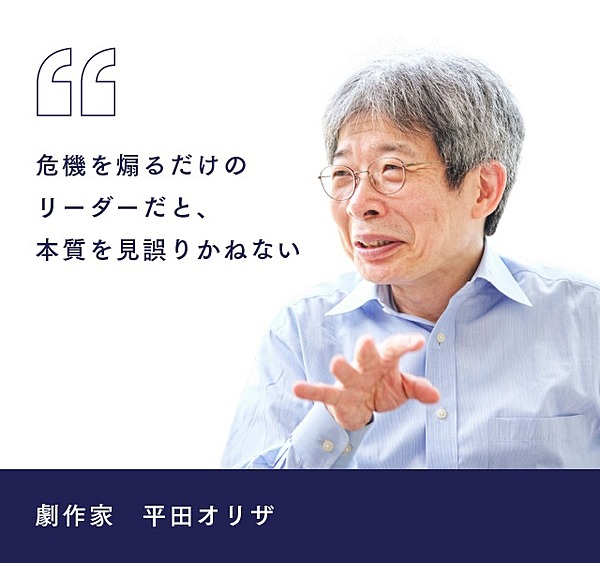
1962年、東京都生まれ。国際基督教大学在学中に劇団「青年団」結成。戯曲と演出を担当。現在、東京藝術大学COI研究推進機構特任教授、大阪大学COデザインセンター特任教授。2002年度から採用された国語教科書に掲載されている平田のワークショップ方法論により、多くの子どもたちが、教室で演劇を創る体験をしている。戯曲の代表作に『東京ノート』(岸田國士戯曲賞受賞)、著書に『演劇入門』『演技と演出』『わかりあえないことから―コミュニケーション能力とは何か』(講談社現代新書)など多数。

埼玉大学経済経営系大学院 准教授。早稲田大学助手、長崎大学経済学部講師・准教授、西南学院大学商学部准教授を経て、2016年より現職。 専門は組織論、経営戦略論。 イノベーティブな組織をいかに創り実践するかについて、社会構成主義に基づくナラティブ・アプローチの観点から研究を行っている。著書に、『他者と働く—「わかりあえなさ」から始める組織論』がある。
新型コロナウイルスのパンデミックは、社会のデジタルシフトをより押し進めたかのように見える。
すこし先の未来を見据えた時、DX、アフターデジタル、withコロナといった社会変化は、私たちにどのような影響を及ぼすだろうか。人と人、人と社会のつながりをどう捉え直していくべきなのだろうか。
そのヒントを探るべく、教育や言語コミュニケーションの専門家である劇作家の平田オリザ氏と、経営学者でありながら人文知にも造詣が深い宇田川元一氏との対談をお届けする。
インターネット、スマホ、SNS、Zoom、5G……テクノロジーの進化によって、社会はどんどん繋がっていきます。人と人、人と社会との距離を超えながら、いかによりよい未来を創っていけるのかを探る大型連載「Change Distance.」。
コミュニケーションの変革をリードするNTTコミュニケーションズの提供でお届けします。
本当に「変化が激しい時代」なのか
──コロナ禍の影響で、社会が大きな変化に見舞われています。「Zoom」の活用が一般化したり、リモートワークの全社適用を決めた企業が増えたりと、デジタル化が一気に進行したように見えますが、お二人はこの先が見えづらい現況をどう捉えていますか?
平田オリザ(以下:平田) 先が見えないのは確かにそうですよね。ただ、いきなり話の腰を折るようで申し訳ないのですが、本質的にはあまり変わっていないように思えます。
例えば平成の30年がちょうど終わりましたが、おそらく中国にとってこの30年はものすごい大きな変化だったと思うんです。それに比べると日本って大して変化していないだろうという、停滞しているだけで。政治的に見ても経済的に見ても。
確かにデジタル化は急速に進みましたよね。新しいツールやメディアが登場すると、人間の体は一瞬追いつかなくなる。だから表面上は変化が激しいように感じるけれども、冷静に見ればそこまで変化はしていないのではないでしょうか。
宇田川 おっしゃるとおりだと思います。現代のビジネス環境を表現する「VUCA ※ 」という言葉がありますよね。私はあの言葉は絶対に使いません。
※Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)
理由は二つあります。一つは、ミクロで見れば技術革新などはあると思いますが、そもそも経営学説の中では、だいたい1940年代頃から「変化が激しい」と言われているんです。おそらく、さらにたどればもっと以前からあると思います。
平田 なるほど(笑)。
宇田川 もう一つは、注意深く見れば、「VUCA」という言葉が使われているのは、結局コンサルタントやメディアのポジショントークに過ぎないからです。
言ってしまえば不安を煽って稼ぐビジネスに似ている。だから落ち着いて本質を見極めようというオリザさんの意見には同感です。
平田 そうですね。教育現場でも「地道な改革が必要」と主張するまっとうな本よりも、危機感を煽るような本が売れます。だから危機を捏造しますよね(笑)。
──耳が痛いお話です……。
平田 あまり世代論に言及したくはないのですが、加えて言えば、僕たちの世代くらい(1962年生まれ)までは「現状は不満でも、未来には希望があった」。ただ、今の若者たちは、ざっくり言うと「現状に不満はなくても、未来に不安がある」という状態です。
つまり「先が読めない」ことよりも「希望が持てない」という不安が大きい。この構造が、今の日本の政治経済のダイナミズムのなさにも影響を及ぼしているように思います。
宇田川 確かにそうかもしれませんね。「現状に不満はない」というのは、さまざまな日本企業で起きている、おかしな「イノベーション推進」の状況を表しているとも感じました。
──おかしな「イノベーション推進」ですか。
宇田川 要するに「どんな必然性をもって企業変革をしたいと思っているのか」ということです。現状に実は不満がない。つまり大半の企業は、過去のビジネスモデルで今は食えてしまっている。
だから「経済的に下り坂だ」ということが何となくわかっていても、実は変革に必然性を感じていなくて、取り組むことが世間的に正しそうだから、やってみている。そういったアリバイ的な「イノベーション推進」や「変革」がよく見受けられます。
こんな話をすると、企業変革の議論では往々にして「危機感を持つことが大事だ」という意見が飛び出すわけですが、それは短期での変革の話です。長いスパンの変化に対して、時間をかけて変えていこうという時に、危機感を持てる持てないは有効でない議論です。
平田 「危機感を持て」と言われても、人間は30年とか50年先のことに対して身体性をもって考えることはできませんからね。
人口減少が進みつつあるとはいっても、1億2000万人の豊かな市場があって、明日どうにかなる、という状態でもない。目に見える危機がないので、余計に危機感を持ちづらいと思います。
危機を身体で把握する
──コロナ禍を契機にDXを推し進めようという風潮があると思いますが、アリバイ的な変革にならないためには何が大事になってくると思われますか。
平田 「3〜5年は維持できても、10年はもたない」と身体感覚でわかる人が組織内にいるかどうかは、今後ポイントになってくると思います。
──「身体感覚でわかる」というのは、もう少し具体的に言うとどういう意味でしょうか。
平田 この文脈に沿って言うと「危機の感じ方」は、言葉を換えれば「リアリティ」の捉え方とも言えるかもしれない。
頭で「10年先はやばいのでは」と思うことはできても、「なんとかしないと大変だ!」「じゃあどうすればいいのか」とまでは切迫感を持って考えられない。
身体感覚ではわかりづらいような長いスパンで進行する危機にこそ、構造的な改革が必要です。
宇田川 なるほど。「急性疾患」と「慢性疾患」にたとえるとわかりやすいかもしれません。
急性疾患の治療は、短期的に起こる症状で原因が明確なので、抗生剤を飲むとか、外科手術をするといったように、医療従事者、つまり外部のプロが主役です。
一方、慢性疾患の治療はそうはいかない。基本的に完治せず、長い付き合いになる。なので、患者がセルフケアをし続けることが主軸になります。この時、主役はプロの医療従事者というより、患者さんとその家族です。
オリザさんが指摘しているのは、今の日本の組織における慢性疾患への対処ですよね。
平田 例えばわかりやすい成功事例として、青森県の八戸市があります。自治体の政策は多くが失敗していますが、危機意識を自治体全体で共有することで、うまくいった事例です。
──なぜ危機意識を共有できたのでしょうか。
平田 まあ単純な話なのですが、八戸市は2002年に開業した東北新幹線の終着駅だったので、経済的にたいへん盛り上がりました。ただ、2010年末に新青森駅への延伸が決まっていたので、好況は約10年の期間限定だと明確にわかっていたんです。
宇田川 なるほど。
平田 ここで市長以下が賢明だったのは、「この10年をバブルで終わらせまい」と持続可能なまちづくりを構想した点にある。文化事業などに注力して街を変えていったんですね。
これはわかりやすいタイムリミットがあったという単純な例ですが、見えづらい危機を慢性疾患であると峻別し、対峙するのは簡単なことではありません。だからこそ首長のリーダーシップが必要になってくる。
特にこれからのリーダーシップは、人々を牽引していくタイプよりも、被害を最小限にとどめながら、周囲と協働して持続可能性を模索していくタイプが求められると思います。哲学者の鷲田清一さんは、これを「しんがりのリーダーシップ」と呼びました。「しんがり」とは撤退戦の際、全軍を逃がすために追っ手を食い止める役割のことです。
つまり、中長期的な危機の本質をしっかり言語化して優先順位をつけ、仲間に共有したり、説得したりできるリーダー像です。声高に引っ張っていくのではなく、時には退却も厭わない。
本質を見誤ってただ危機を煽るだけのリーダーだと、集団全体が冷静さを失ってしまうということになりかねません。
「発注力」とは何か?
──身体的に危機を捉えるには何が必要なのでしょう?
平田 平たく言うと、「自分のものさしで物事をうまく測れること」ではないかと思います。
フランスの社会学者、ピエール・ブルデューが提唱した「文化資本」という言葉がありますが、中でもいわゆる「センス」「感度」のようなものは「身体的文化資本」と呼ばれています。僕は「文化の自己決定能力」と呼んでいます。
わかりやすい例では、2004年に開館した「金沢21世紀美術館」(以下、21美)の例です。当時、多くの自治体が、数十億の西洋絵画を勧められるままに購入するなか、21美では、当時無名だった現代アートの作家に着目して、展示の仕方までをトータルで考えて成功しました。
作品の市場価格に左右されず、自らストーリーまで組み立てた21美の担当者は、自らのものさしで測るセンスがあったということです。ただすこし残酷な話ですが、「身体的文化資本」の厳密な定義に従えば、それは20歳くらいまでに形成されるといわれるもので、後天的に身につきにくいものなんです。
──では、「センス/身体的文化資本」がない人はどうすればいいのでしょうか?
平田 まずそれを自覚することが大事だと思います。自分は何が苦手なのか意識する。これはとても大切で、そこから始まる能力を「発注力」と呼んで僕は重要視しています。
僕が大阪大学の大学院で関わっていた授業で評判が良かったのは、デザイナーに対して学会ポスターを「発注」するワークショップでした。
学生たちはポスターの要件を一生懸命、言葉にしようとする。でも、デザイナーにその場でラフ案を描いてもらっても、なかなか思ったようなものにならない(笑)。
この授業の目的は自分たちの言葉の“伝わらなさ”を体で感じてもらうことにありました。
「発注力」というのは言葉を足すと、苦手な部分や他者に補完してほしい部分を、相手に伝わるように言語化する能力。「センス」は後天的に身につかなくても、「センスの不足」を補うために別の手法を模索することはできるはずなんです。
宇田川 それは、極めて重要な能力ですね。自分の困りごとを認識できると、周りを頼れるようになるということですよね。
平田 おっしゃるとおりです。
宇田川 企業社会に当てはめて言えば、自社が何に困っているのか、よく認識できていないと、短期的な利益を求めて外部のコンサルやツールなどに安易に依存してしまう。
──その場合、何に困っているのでしょうか。成果が出ないことでしょうか。
宇田川 「成果が出なくて困っている」にもいろいろありますよね。
伸び盛りのベンチャーが、売上自体は成長していても、業績目標に対して未達であったならば、株式市場との約束が果たされず、市場価値に傷が付きます。その場合は、資金調達などの面で、思うように信頼が得られないかもしれなくなるというのが困ることですよね。
一方で、業界は成長しているのに、自社の業績が横ばいもしくは微増で、伸び悩んでいるという困りごとであれば、業界の競合他社がその間に市場のシェアを侵食しているかもしれない。その場合は、いずれ他社に市場から駆逐されるかもしれない、ということが困りごとです。
なので、表層の困りごとの背景にある構造が違えば、問題自体の枠組みが変わってきます。そうすると最初に問題だと思っていたものだけを見ていると、うまく発注できないケースがたくさんあります。
自分が必ずしも何もかもできなくても良いので、困りごとを言語化しようとする「発注力」が、まさに「しんがり」的な感覚なのかな、と。
「固有の物語」を掘り起こす
──「発注力」を鍛えていく上でのポイントはどこにあるのでしょうか。
平田 「固有の物語」を基盤に考えるということかと思います。
宇田川 それは、自分たちが何者なのかを知るということでしょうか。
平田 そのとおりです。例えば僕は今、兵庫県の豊岡市に住んでいます。きっかけは、市内の城崎温泉地区にある、使われていないコンベンションセンターをリニューアルしたいと相談を受けたことでした。
城崎温泉は志賀直哉の小説『城の崎にて』で100年もってきた街です。他にも、谷崎潤一郎や島崎藤村ら、文人墨客を無料で逗留させて、最後に書かせた一筆が観光資源にもなってきた。
それは、今でいうアーティスト・イン・レジデンスではないかと気づいたんです。
宇田川 ええ。
平田 そこで、目利きのプロデューサーに現代アートの作家を選抜してもらい、コンベンションセンターをリニューアルしたアートセンターに滞在させる。ここからいずれ21世紀の『城の崎にて』が生まれれば、さらに100年もつまちづくりができるのではないかと考えました。
宇田川 固有の物語を刷新していくということですね。
平田 加えて、簡単な数字の裏付けも示しました。日本の公共ホールはレジデンス施設を保有していません。仮にフランスの20人規模のアートカンパニーが来日する場合の、東京滞在と豊岡滞在のコスト比較も報告書に記載しました。
豊岡なら宿泊費が東京ほどかからないので、1ヶ月あたり数百万円の資金が浮く計算になる。だから利用してくれるだろう、と。
宇田川 固有の物語と、数字的な成果のような別軸の評価をどう結びつけるか。
フィンランドの教育学研究者にユーリア・エンゲストロームという人がいます。彼は「野火的活動(Wildfire Activity)」というコンセプトで、野火のようにしぶとく残る活動について研究をしている。例示したのは、スケートボード、赤十字の災害支援活動、そしてバードウォッチングです。
平田 なるほど。
宇田川 例えばバードウォッチングでは、生物学者と趣味人が共生・搾取関係にあるんです。つまり互いに持ちつ持たれつの関係になっている。これをエンゲストロームは「直線と曲線の融合」というメタファーで表現しています。
これを経営に当てはめると、利益のより大きな分配という成果を求める資本主義の直線的な要素と、それぞれのローカルな現場での気づきから何か新しいものを生み出していく曲線的な要素の融合が、地に足のついた持続可能な変革を促していくことになります。
例えば、企業内の新規事業部は、短期的な収益のインパクトが小さいので、他組織から冷ややかな目線を浴びがちです。その環境下で「野火的活動」の如くどう生き延びるかが、企業内のイノベーション推進の中核と言っても過言ではない。
私の役割は、その企業が持っている「固有の物語」と、数字的な裏付けを踏まえた「成果」の構造的な対立を研究から解き明かし、対話を支援することです。それが「発注力」をベースにした企業の自己決定力につながるのではないか、と思っています。
コミュニケーションの未来とは
──最後に、先々の展望のヒントを伺いたいと思います。「未来に希望も持てない、かといって危機感も持ちづらい」。そんな状況にいる中で、我々はこれから先、どのように物事を変革していけばよいのでしょうか。
平田 「ダイアログ(対話)」という概念が重要になっていくと思います。僕は『わかりあえないことから』という本で、対話の必要性を中核に据えました。違いを尊重しつつ共通点を探るという主旨で、カンバセーション(会話)とは違う概念です。
教育の文脈では「シンパシーからエンパシーへ」とも言われます。前者は弱い者への同情、後者は異なる価値観や文化的背景を理解しようとする態度です。共感とも言えるでしょう。欧州ではエンパシーが教育の基幹になっていますが、逆に日本人は「対話」と「共感」は苦手と言えます。
「ダイアログ」や「エンパシー」は、企業経営や自治体経営においてもポイントになってくる考え方です。もちろん成功例から学ぶこともありますが、自治体だけで1,700もある中で、まったく同じ例などないのですから。
宇田川 つまり派手な成功例に惑わされず、「個別に見ていく」ということですよね。
組織論に当てはめると、新しい状況に右往左往せずに問題を見極めながら、自分たちが何者なのかという個別のナラティブ(物語/常識の枠組み)を見失わないようにする。
最初の話に戻ると、本質は大して変化していない。
どうしてもメガプラットフォーマーなどの派手な成功例をベンチマークにしたりしがちですが、まずは落ち着いて自分の疾患が急性なのか慢性なのか、そして「何に本当に困っているのか」を見定めるのが大事ではないか、と思います。
──それを踏まえて、ICTが不断に進化していく中で、社会におけるコミュニケーションはどう変わっていくべきなのでしょう。
宇田川 コミュニケーションの未来について言えば、「もはやツールだと感じさせないツール」が大事になってくると思います。もっと人間の感覚に沿って、それを拡張するような人間化されたツールというか。
「Zoom飲み」とかリモートワークもそうですが、コミュニケーションツールと言われているものは、ツールである以上目的を伴っているわけです。ただ、“目的のいらない手段”こそが今の時代には必要だと思うんですね。
例えば、人と人がすれ違う時、“互いに関心がない”ことにも意味がある。「儀礼的無関心」と呼ばれるものです。コミュニケーションの幅は、想像以上に深くて広いんです。
こういう状態を、コミュニケーションツールと言われているものはまだ達成していないと思うので、チャレンジのしがいがあると思います。
平田 おっしゃるとおりです。
例えば、今回の新型コロナ禍で起こったのは「孤立の加速」だと思っています。「対話」と「共感」が苦手な日本社会の弱さを突かれて、ストレスフルな社会に拍車がかかっています。
企業や地縁血縁以外の、出入り自由なゆるい集団が、今後オンライン化が進めば進むほど重要になっていくはずです。僕はそれを「関心共同体」と呼んでいます。
制度を設計する立場の人々は、その点を意識することが大事になってくるでしょう。
宇田川 世の中は大きく移り変わっていくように見えます。個別の事象には適切に対処していくことが必要でしょう。
しかし、私たちにとって大切なもの、私たちがなすべきことは、実際のところそんなに変わっていないと思うのです。
必要以上に惑わされることなく、着実な変革の道を歩む。そのために、いかに「自分たちに必要なこと」を発見し、それを形にしていくことができるか。今は、そういうことに取り組む良い機会なのではないかと思います。
(編集:中島洋一 構成:吉田直人 写真提供:小林由喜伸 デザイン:岩城ユリエ)