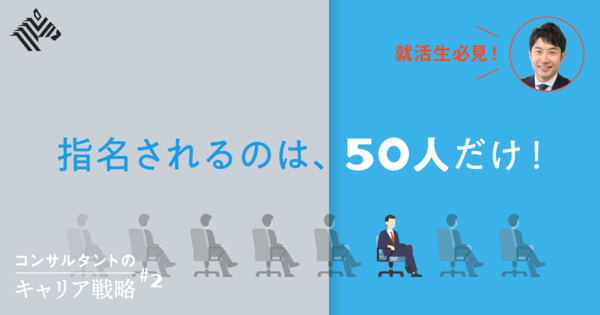【保存版】コンサルのキャリア「5つの選択肢」
コメント

注目のコメント
インタビューをしていただいたIGPIの塩野です。
業界のミジンコのような私が諸先輩方を差しおいて生意気なことを言って申し訳ございません。私自身も将来についていつも悩んでいます。
私は、新卒で志望した日本企業のどこにも入れずに仕方なく外銀でした。歳を取ると、どんな職業・勤務先でももちろん「偉い、偉くない」もなく、本人の幸せと「自己肯定感」こそが大事だと日々感じます。
40代、50代ですと、昔は不遇でも復活した人は幸せそうですし、逆に世間的に輝かしい学歴・職歴でも、自分の現状に満足できず不幸せな人はたくさんいます。人間とは不思議なものです。
単純化すれば「企業の強さ=社員の能力×市場」なので、それを内部または外部(コンサル)から向上させる以外がありません。ここも合理と情理、鬼手仏心。人間のやることなので、データによる戦略やリキャップが意味を持つ場合もあれば、タバコ部屋の情報が重要だったり、ルノワールで土下座することで人が動いたりもします。
今から、知力・体力に自信がある若い方が行くべき分野はインパクトベースではTikTok問題に代表されるような、「国際安全保障×デジタルテクノロジー」でしょう。国際秩序の再構築がされるなか、プレイヤーとして外交やテクノロジーに関わるのでも、EU委員会のマルグレーテ・ベステアーのように規制当局側になっても面白いと思います。この道で働いて20年目になってしまいましたが、非常に良くまとまっていて、過度に美化するわけでもなく、かといって卑下するわけでないスタンスも、内容的にも違和感も不足もない記事だと思いました
卒業後のキャリアについては、ファームによって色がありそうですが、自分の周りではやはりベンチャー(出来たて〜上場くらいまで)が多いように思います。若い人でも活躍できる、給料も良い、コンサル出身をありがたがってくれる、ということで、数年働けば転職先には困らない感じがします。もちろんその後活躍できるかはその人次第です偏差値競争の延長線上で就活してしまい、「難関」の聞こえが高いコンサルを目指す── 。そんな学生を何人見てきたかわかりません。しかし、コンサルに限らず、どんな仕事も本来、自分の得意なこと、やりたいこととの相性、つまり向き不向きで選ぶのが、適職を得る大前提ではないでしょうか。
では、コンサルに向く人とは?その、5つの問いが、グサリと心に刺さる人も多いのでは?
またコンサル後のキャリアの選択肢も、とりわけトレンドであるプライベートエクイティファンドへの転職の内実も詳しく述べています。
コンサルがよく言う「抽象と具象を行き来する思考が大事」ということも、仔細な具体例で示しています。固有名詞がポンポン飛び出す具体的かつ本音のキャリア戦略を、読みやすい図解でお届けします。