
【楠木建×明石ガクト】ストーリーとしてのワンメディア戦略
2020/7/15
新・電子書籍レーベル「NewsPicks Select」。その第一弾を飾るのが、明石ガクト氏の『動画の世紀 The STORY MAKERS』だ。明石氏がバイブルとする『ストーリーとしての競争戦略』の著者である楠木建氏と、クリエイティブをテーマに語った。
持続的競争優位の論理
楠木 僕は競争戦略という分野で仕事をしています。競合他社との差異を創る、これが今も昔も変わらない戦略の本質です。
要するに「違いがあるから選ばれる」ということです。
「違いを創る」といっても「言うは易し、行うは難し」です。競争戦略とは要するに、「他社と違った良いことをやる」ということなのですが、「良い」ことと「違う」ことの間に根本的な矛盾があります。
そんなに良いことだったら皆がやるでしょう。つまり「良いことほど違いにならない」。ここに「競争のジレンマ」があるわけです。
競争戦略の根本問題の1つは、このジレンマをどう乗り越えるのかということにあります。

楠木建(くすのき・けん)/ 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
1964年東京都生まれ。89年一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。一橋ビジネススクール教授。専攻は競争戦略。企業が持続的な競争優位を構築する論理について研究している。著書に『ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件』『戦略読書日記』など。
1964年東京都生まれ。89年一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。一橋ビジネススクール教授。専攻は競争戦略。企業が持続的な競争優位を構築する論理について研究している。著書に『ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件』『戦略読書日記』など。
この問題に対する答えとして、これまで最も多く語られてきたロジックは「模倣障壁」です。成功している企業と同じことをやろうとしても、そこには簡単にまでできない障壁がある。だから違いが維持されるというものです。
たとえば、規模の経済や範囲の経済が効いているとか、ブランドが確立しているか、パテントプロテクションがかかっている、といった模倣障壁です。
模倣障壁に依拠した戦略論の典型的がブルーオーシャン戦略です。
競争市場を再定義し、競争がない「ブルーオーシャン」を見つけることは確かに重要です。しかし、競争優位を構築することと、それを長期的に持続することは似て非なるものです。
いったんブルーオーシャンが発見されてしまえば、それがブルーであればあるほど皆がそこに行きたくなる。
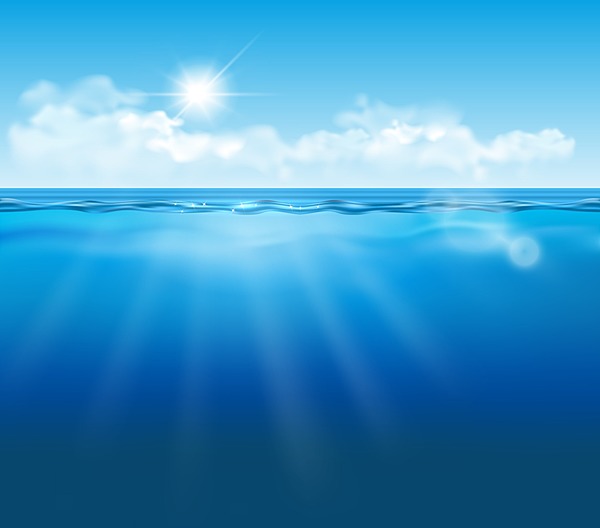
(写真:iStock/Katerina Sisperova)
ここに戦略のジレンマがあります。「ブルーであるほどレッド化の速度が速い」という逆説です。
じゃあどうすればよいのかというと、結局のところ「模倣障壁を築きましょう」という従来のロジックに回帰してしまう。
ここが僕にとっては面白くないのです。
なぜならば、強力な模倣障壁は手に入れにくくなってきているからです。その理由はいくつも列挙できますが、とりあえず2つを挙げておきましょう。
1つは、 クリエイティブといった分野が典型ですが、昔のように規模の経済や範囲の経済が利かない商売が多くなってきていること。
もう1つは、この30年でインターネットが発達し、情報の流通コストが著しく低下したということ。
NewsPicksのようなメディアは、最新の「ベストプラクティス」や成功事例についての情報をひっきりなしに発信しています。
誰しもすぐに低コストでこうした情報にアクセスできる時代です。「他社と違った良いこと」をやっていても、それはすぐに多くの人の知るところになります。
模倣障壁とは異なる持続的な競争優位の論理はあるのか。あるとすれば、それは何か。
この問いに対する僕なりの答えが『ストーリーとしての競争戦略』で書いた「戦略ストーリーのクリティカル・コア」という話です。
さまざまな打ち手が明確な因果論理でつながったストーリーとして戦略をとらえると、部分の合理性と全体の合理性にはギャップがあることに気づきます。
ストーリー全体をよくよく解読すると強力な合理性があるにもかかわらず、それを構成している部分をバラバラに見た場合、中には一見して非合理な要素が入っている。
その業界や商売に詳しい人ほど「そんなバカなことをしてはダメ」と考える。
この「ストーリー全体の文脈に位置づけるときわめて合理的だけれども、それだけを文脈から切り離してみると非合理に見える」という構成要素を戦略ストーリーのクリティカル・コアと呼んでいます。
真似をする側は「そんなことを非合理なことをしてはいけない」と思っているので、真似される側の優れた戦略に近づこうとしない。
つまり、「真似したいのだけれども(模倣障壁があって)できない」のではなく、そもそも「真似しようとは思わない」「むしろ同じことをするのを忌避する」という論理です。
さらに言えば、真似をする側がストーリー全体を理解せず、戦略ストーリーに含まれている「合理的」な要素だけを取り出して真似してしまうため、戦略の一貫性が崩れ、頓珍漢なことをする。
これは真似する側が真似しようとすることによって自滅してしまうという成り行きです。
持続的競争優位性の論理としては、模倣障壁よりもクリティカル・コアによる「模倣の忌避」や「自滅」のほうがよほど強力です。
これこそが究極の競争優位だというのが僕の暫定的な結論です。
ワンメディアの戦略と仙台のコギャル
明石 僕は創業初期に楠木先生の本を読み、今まさに先生がおっしゃっている「クリティカル・コア」――先生の本では「キラーパス」という表現をされていたと思いますが、そこを強く意識しての事業に取り組んでいます。
これまでオープンな場でこういう話をあまりしてこなかったのですが、ワンメディアが比較的うまくいったとされている今だからこそ、楠木先生の本の中にもある動画としての競争戦略も少しからめて話していきたいと思います。
まず、クリティカル・コアの部分からいくと、動画というある種のブルーオーシャンが広がっていく中で、さまざまな会社が動画をテーマに起業しました。

明石ガクト(あかし・がくと)
ワンメディア代表取締役。1982年静岡生まれ、2006年上智大学卒業。2014年6月、ミレニアル世代をターゲットにした新しい動画表現を追求するべくONE MEDIAを創業。著書に『動画2.0』『動画の世紀』。
ワンメディア代表取締役。1982年静岡生まれ、2006年上智大学卒業。2014年6月、ミレニアル世代をターゲットにした新しい動画表現を追求するべくONE MEDIAを創業。著書に『動画2.0』『動画の世紀』。
楠木 「これからは○○が来る!」という、誰もが注目するオポチュニティというものがそれぞれの業界にあるわけですが、クリエイティブ分野で「○○」にあてはまるものは、このところ「動画」ですね。
明石 動画がブルーオーシャンではないかと言われる中で、動画マーケットは小さいながらも毎年ものすごい勢いで伸びていました。
そのため多くの会社が参入したのですが、バタバタと倒れていったのです。
その中で、僕らはまだ生き残っていますが、そこにはいわゆるクリティカル・コアな部分がありました。
1つは社内に制作チームを抱えたことです。
実は映像業界に深く根差していればいるほど、内部に制作スタッフを抱えない傾向があります。
もともと下請会社が多い業界ですから、これだけフリーランスが活躍する中で、撮影や編集といった現場の仕事は外部に振ってしまえばいいわけです
でも僕は禁じ手とされている内製化をあえてやりました。
結局、外注文化では、映像から動画へのパラダイムシフトが起きる時に、動画というブルーオーシャンに適したクリエイティブを作るのは無理なのです。
ですから、われわれは社内にR&D的な制作チームをきちんと作ったのですが、きわめて非効率的で、最初はまったく利益が上がりませんでした。
でも、なかなかうまくいかない時期が約1万時間続いたあと、僕らならではの原則のようなものができあがったのです。
そのうちに「ワンメディアが作る動画は効くらしい」という評判が生まれ、僕らにクリエイティブを依頼するクライアントがどんどん増えていきました。
そうなると、次に模倣のフェーズが起きてきます。
楠木 うまくいっているのは、見ていればわかりますからね。
明石 実際、他の制作会社に「ワンメディアっぽいやつを作ってよ」とオーダーするようなケースがたくさんあったと聞いているのですが、これはやられた!と悔しくなるような模倣がまったく起こらないんですね。
なぜ微妙なコピーしか生まれなかったかということですが、先生の本の中に、仙台のコギャルがファッション全体のバランス感を欠いたまま、東京都内で流行っているパーツをどんどん取り入れていた例があります。

(写真:iStock/metamorworks)
楠木 それはクリティカル・コアというロジックを僕が思いついたきっかけの1つです。
ずいぶん昔の話です。コギャルファッションが東京発で流行っていた当時、東北大学に集中講義に行く用事があり、仙台駅でバスを待っていました。
バス停の行列の前に、東京のコギャルよりもよほど気合が入っているコギャルファッションの女の子3人組がいました。
顔は渋谷センター街のコギャルよりもう一段黒く、目の周りと口紅はより真っ白で、頭は実験に失敗した科学者のように爆発し、ソックスは「殿中松の廊下」レベルの超ルーズなものでした。
ヒマだったし、面白かったので、「君たちはファッションに気合入っているねー!」と声をかけたのです。
すると彼女たちは「そんなことは絶対にない」と言うんです 。
彼女たちはコギャルファッションの専門誌を持っていて、「自分たちは仙台に住んでいるけれど、これを毎月読んで東京のカリスマファッションリーダーの服装を研究している。
この雑誌を調べれば、どんなメイクとヘアスタイルにどういうアイテムを組み合わせればいいのかがわかる。それを忠実に仙台で再現しているに過ぎない。
だから東京のコギャルと何ら変わらないはずだ」と、もっとギャルっぽい話し方で主張するんですね。

東北大学行きのバスに揺られながら、思いついたのが先ほど話した「合理的模倣による自滅」のロジックです。
なぜある種の強い企業はいつまでも強いのか。
誰もがその強さを手に入れたいのに、なぜ追いつけないのか。
それは追いつこうとする側が「仙台のコギャル化」しているからだと。
真似する側は、模倣対象である成功者の目立つ要素、「ベストプラクティス」と言われるような部分だけを模倣しようとする。
しかも、それが「とても良いこと」であり成功者の強みの源泉だと思っているので、思いっきり真似をする。で、やりすぎてしまう。
だから、仙台のコギャルはそこまでやらなくてもいいのに、頭につける花を大きくしてしまう。目の周りとリップも、僕らが「ちょっと白すぎでは?」と思うぐらい白くする。つまり、「構成要素の過剰」が起きる。
その結果、全体の一貫性が壊れた奇妙なファッションになってしまうのです。
ここでのポイントは、渋谷のカリスマコギャルは、仙台のコギャルの模倣を阻止する行動を一切取っていないということです。
彼女たちは渋谷で粛々とコギャルファッションをやっているだけ。にもかかわらず真似ようとする側が勝手に自滅していく。
その結果、渋谷のコギャルの優位性は持続する。こういう競争的相互作用を「仙台のコギャル」にみるわけです。
あえて自社メディアを持たない
明石 まさにこうしたファッションのトータルコーディネートと、ビジュアルのクリエイティブを作ることには非常に近いものがあり、個別のさまざまなパーツのバランスをうまく調整して最適な解を導き出すことが、良いクリエイティブを作る条件の1つです。
動画においては、単純に見た目を構成するパーツや時間軸を構成するパーツ、すなわちタイミングや出方、色使いなどがありますが、それらを総合的に調整していく中で「ビジュアル・ストーリーテリング」というものが生まれるわけです。

明石ガクト(あかし・がくと)
ワンメディア代表取締役。1982年静岡生まれ、2006年上智大学卒業。2014年6月、ミレニアル世代をターゲットにした新しい動画表現を追求するべくONE MEDIAを創業。著書に『動画2.0』『動画の世紀』。
ワンメディア代表取締役。1982年静岡生まれ、2006年上智大学卒業。2014年6月、ミレニアル世代をターゲットにした新しい動画表現を追求するべくONE MEDIAを創業。著書に『動画2.0』『動画の世紀』。
楠木 明石さんが手がけているようなクリエイティブ分野の特徴として、価値を個別の要素に還元しにくいということがありますね。
言い換えると、モノの良さを特定少数のスペックで表現したり比較したりするのが難しい。
明石 その通りです。
要は機械や数字を入れれば製品ができあがるというものではなく、形を真似ればいいというものでもありません。
楠木 ファッションと同じように「最適化」がカギになる。しかもそれは「さじ加減」で決まってくる。
明石 ワンメディアの創業当時、さまざまな情報やデータをグラフィック化するインフォグラフィックスや、今こうやってしゃべっている言葉をタイポグラフィにすることを駆使して、FacebookやTwitterなどで見やすい動画を制作することが、僕らのプロダクトでした。
その頃、「情報を凝縮するなら、時間の中になるべく情報を詰め込むようにすべきだ」と僕は言っていましたが、多くの情報を詰め込もうとするあまり、(グラフィックが)速くて読めないなどのバランス感を欠くプロダクトになってもおかしくありません。
ところが僕らの場合、とくに何も対策を施さなくても、そうしたトラブルは皆無だったのです。
楠木 つまり内部で戦略のストーリーをお互いに理解し共有し合っている人たちが自前でプロダクトを作っているので、「さじ加減」を重ねて最適化することができたということですね。外注ではそういうことができない。
明石 そうですね。
僕はさらに、コンセプトにストーリーと時間軸を持たせ、われわれも徐々に変化していくような戦い方をしなくてはいけないと思いました。
われわれのビジネスは、インフォグラフィックスの制作から始まっているのですが、ある意味で制限された環境だったからこそ、それをやらざるを得なかったという事情もあるのです。
要はワンメディアという社名を誰も知らないわけです。
僕らにはブランドがなくて、芸能人などに出てもらって動画を作りたいのに、誰も我々のオファーを受けてくれなかったんですね。
そこで出演者に依存しないやり方で動画を作るとなるとインフォグラフィックスだ!と。
自社でR&Dを重ねる中で、僕らなりのスタイルや制作力の検証がある程度できてきたわけです。
その次の段階で、僕らは当時注目を集めていた分散型メディアという戦略にチャレンジしました。
自社のプラットフォームを持たずにTwitterやInstagram、Facebookなどを通じて動画をさまざまな所に流すわけですが、これが実は、僕らの2つ目のクリティカル・コア になっているのです。
一般に、メディア事業をやろうとする企業は自社メディアを作ります。
実際、アプリケーションやサイトなどの情報を拡散できる資源を作り、それを売るのがいわゆるメディアビジネスでした。
しかし、僕らはあえて、そういうものをオープンなSNSにしか作らないという方法を取ったのです。
これには不合理な部分もあると同時に、クライアント企業がSNSでコミュニケーションを行う時に「ワンメディアはとても詳しい。しかもSNSについては、彼らが最もいろいろな場所を知っている」という評判にもつながります。
また、先行している競合企業は既に自社メディアの開発に多くの投資をしてしまっており、それ戦略のコアになっているので、僕らと同じやり方に振り切ることもできません。
分散型メディアを通じて動画による情報発信を繰り返していくと、いよいよ芸能人やインフルエンサー、楠木先生のような文化人にも「ワンメディアってあるよね」と言われるようになってきます。
つまりインフルエンサー、 SNS、 動画の3つの流行ワードを掛け合わせることでブルーオーシャンが見えてくるという意味で、まさに戦略のストーリーにつながっているわけです。
マイケル・デルはなぜ本を書いたのか
楠木 優れた戦略のストーリーを持っている企業によく見られる傾向として、「鷹揚さ」があるんですね。
今から20年以上前の話ですが、Dellの「ダイレクト戦略」「ダイレクトモデル」がPC業界で脚光を浴びていました。
皆がDellの戦略に注目したわけですが、僕はそのころDellの手伝いをすることがちょくちょくあって、CEOのマイケル・デルさんから面白い話を聞いたことがあります。

(写真:AP/アフロ)
デルさんはDellの成功した戦略を書いた『Direct from Dell』という本を出しています。これが世界でベストセラーになりました。
僕はデルさんに「いくらダイレクトが信条だからといって、あの本はデルの戦略の詳細をダイレクトに公開し過ぎではないか」と聞いたんです。
すると彼は「いやいや、われわれは成功したバスケットボールの選手なんだ。野球選手がバスケットボール選手の話を聞いてまったく同じことをやろうとしたらどうなると思う?」と言ったんです。
つまり、目立つ「ベストプラクティス」や個別の要素は真似できても、戦略のストーリー全体はそう簡単には真似できないという自信がある。
だから鷹揚な姿勢でいられるということです。
自社の戦略ややり方に関して徹底的に秘密主義の会社がありますが、それは裏を返すと自分たちの戦略ストーリーの強みにそれほどの自信がないということなのかもしれません。
(写真:遠藤素子、デザイン:九喜洋介)
*後編に続く。



