その直木賞作家にとって、児童虐待のテーマについて取り組むことが、まさにキャリアの転機となった。
1999年、まだ世間一般では児童虐待が今ほどは注目を集めていない中で、『永遠の仔』を世に送り出した。
6年という時間をかけて書き上げたこの小説は、100万部を超えるベストセラーに。虐待を経験した3人の男女の物語は反響を呼び、ドラマにもなった。
出版後、小説家のもとには、5000通を超える虐待経験者からの声が寄せられた。

作家・天童荒太。2009年に亡くなった人々を追悼して歩く青年を描いた『悼む人』で直木賞を受賞してからも、精力的に執筆活動に取り組む。
2020年5月に刊行した短編集『迷子のままで』には2つの物語が収められている。そのうちの1つのテーマは虐待加害者の物語だ。
新型コロナウイルスの感染拡大で、虐待やDVなど家庭内の問題が再び表面化した。そんな時代に、長年、児童虐待の問題や家族の問題について向き合ってきた天童は何を思うのか。(敬称略)
児童虐待は「特別な人による特別な事件」ではない

「児童虐待と聞くと、どこか特別な事件のように感じる方も多いかもしれません。でも、これは誰にとっても関わりのあるものだと僕は捉えているんです」
長年取り組んできたテーマについて、天童はこう語る。
「All or Nothingで、虐待をしてしまう家族がいるか、いないかということではない。誰にとっても子どもに手を上げてしまった、叱り過ぎてしまったという出来事はあるはずです。レベルを超えてしまうことで、事件化する。しかし、苛立ちのあまり、物を投げつけたくなってしまうような感情は誰もが持っているものだと思います」
児童虐待は自分とは違う遠い誰かの問題、と捉えてしまうことに警鐘を鳴らす。「特別な人が起こしている特別な事件ではない」。それが伝えたいことだ。
なぜ、母親ばかりが責められる?
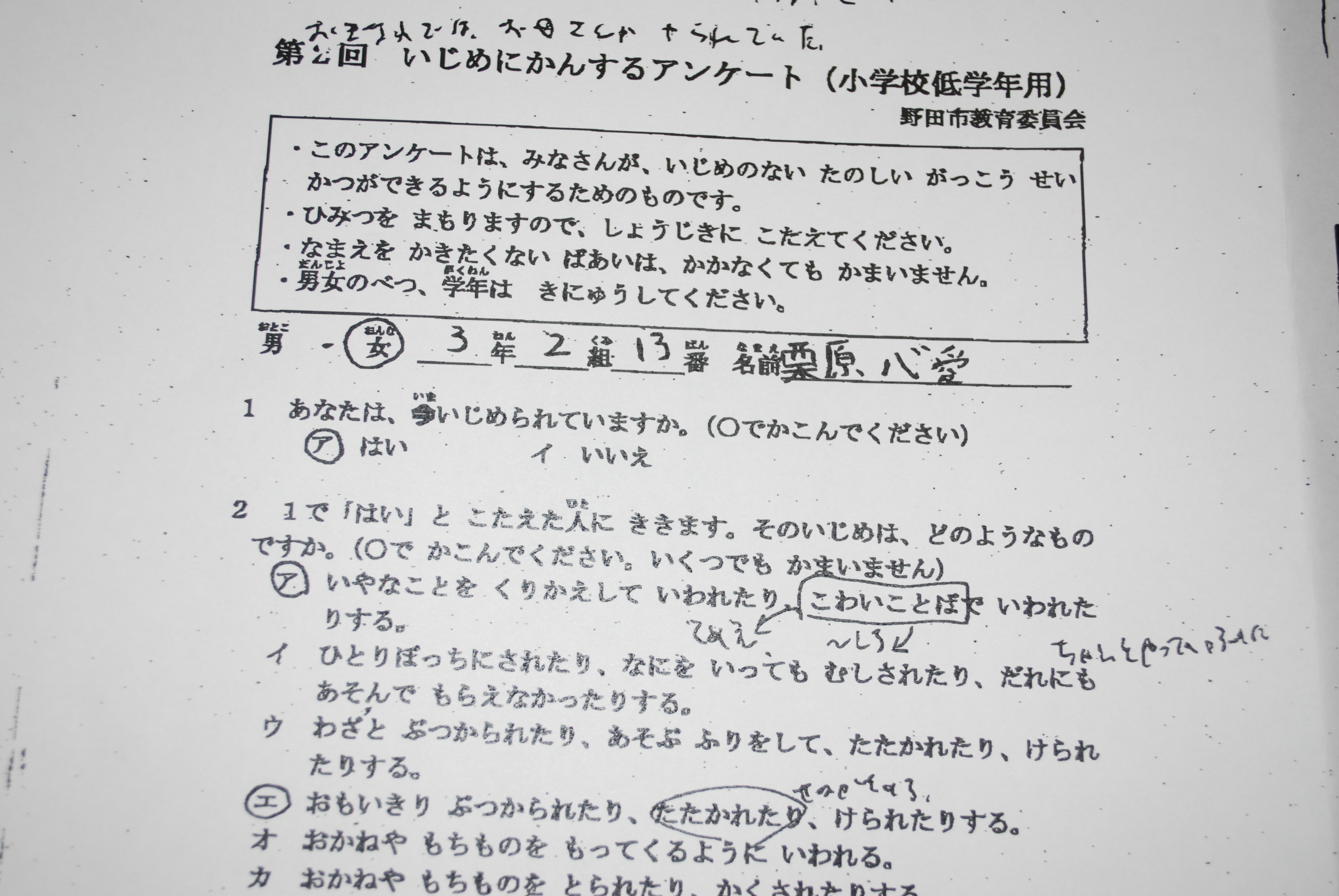
近年、毎年のように小さな子どもが虐待の末に命を落とす事件が起きる。その度、過熱するのが加害者へのバッシングだ。
虐待をセンセーショナルに取り上げ、週刊誌などが加害者を「鬼母」と表現することも。SNSなどでは加害者を責める声が膨れ上がる。
しかし、天童はこの光景に違和感を覚えるという。
「虐待のセンセーショナルな部分に注目が集まる中で、常に母親が責められる。でも、多くの場合、既にそこにいない母と子を捨ててしまった実の父親の存在が語られることは少ないと感じています」
児童虐待は1人親の家庭で起きやすい傾向にある。全国児童相談所長会によるる「全国児童相談所 における虐待の実態調査」(2008年)では、虐待の32.0%が1人親家庭で起きていることがわかっている。
「子どもができたけれど、育てることが面倒で父親が逃げ出してしまうケースもあります。さらに、養育費も払わないことも。そうした中で、残された若い母親は苦労をして、夜泣きにも耐えて、オムツも替えて、生活がうまくいかない中でなんとかしようとする」
「そして、ある日、我慢の閾値を超えてしまって事件化する。その時、逃げた実の父親が免罪されてしまうことの裏には男性に甘い日本の差別構造があるのではないでしょうか」

そこに既にいない父親が免罪されてしまうことは「日本における社会的罪なのではないか」、天童は指摘する。だからこそ、今作「迷子のままで」では、前妻と別れた父親の物語を描いた。
ある日、友人からの知らせで前妻が自分との間に生まれた子どもを殺してしまったと知ることから、物語は進む。
時間を巻き戻すことはできない。離婚してから、前妻と実子が歩んできた道のりを辿る中で、芽生えるのは後悔の念だ。
「おむかえにきて」、実子はメッセージを残していた。
報道では見えない切実さこそ、小説に

「成績や美醜といった価値観で測られてしまうことがまだまだ多い世界において、常に自己卑下せざるを得ない状況で生きている人が少なからずいる。しかし、マスコミにはそうした人々の切実さが見えていないのでは」
胸の内にあるのは、現在の報道のあり方への疑問だ。
「自己卑下をしてしまう人たちがセックスを"逃げ場"としてしまうことは少なくない。唯一の逃げ場である場合もある。時にはセックスをする中で、『かわいいね』と褒められたりもする」
「それゆえに、そうした行為にすがって生きざるを得ない人たちがいるということは事実です。でも、そこに思い至らず、なぜこんなことが起きるのか?と、すぐに誰かを責める」
そんな報道では光の当たらない部分にこそ、天童は光を当てる。それが小説の役割だと考える。
「マスコミやジャーナリズムは見えているものしか伝えられない。でも、小説は見えない物を見えるようにして届けることが可能です。可視化こそ、小説の1つの武器なんです」
「決してこれは特別な人による特別な事件ではない、自分たちと地続きの誰かの身に降りかかる悲しみなのだと伝えたいと願いながら書きました」
なぜ、構造的な課題に目を向けない?

このままでは、これからも児童虐待をめぐる状況は「悪化し続ける」。天童は断言する。
これは自分たちと地続きの問題だと実感することがなければ、児童相談所の問題や警察だけの問題と見なされてしまう。そうした中で、積み重ねられていく対策は「土嚢(どのう)のようなもの」だ。
だが、それでは「決壊し続けるダムを修復することはできない」と苦言を呈す。
「たとえ離婚して、1人で子育てをしていても、パートで働くことができれば問題なく『幸せです』と言うことができるような社会になっているのか。虐待の問題を通じて問われているのは、社会のあり方です」
「もしも、離婚したとしても、十分な養育費が払われていれば、こうした問題はゼロにはならなくとも減るはずです。虐待は社会の構造によって引き起こされています」
踏み込んで書かなければ、わからない。掴んだ確信

児童虐待がまだそこまで広く知られる課題ではない時代から、一貫してテーマに据えて書き続けてきた。しかし、社会問題の多くは、当事者でなければ全てはわからないという難しさと隣り合わせだ。
わかろうとする努力を続けても、辿り着けないものがある。そんな中で、見えていない物を見えるように書くことに恐れを抱くことはないのだろうか。
「当事者にしかわからない部分は常に存在する」と前置きをした上で、それでも「自分をどれだけ当事者の側に置くことができるのか」が表現する上では重要だと天童はつぶやく。
「書かなければ見えない部分に真実や社会の隠されている問題があると、僕は思う。それを明らかにすることで、人間が幸せになるための障害となっているものが見えてくる。そこに踏み込まない限りは、また同じ悲しみを繰り返していくことになるのだと思います」
「踏み込んで、初めてわかる」。30年以上、作家人生を続ける中で掴んだ確信だ。
『永遠の仔』を書き上げた当時から、その確信を得られていたわけではない。むしろ、当時は何を書くにも手探りだった。
天童を救ったのは当事者にしかわからない領域にまで踏み込んだ小説に寄せられた、虐待当事者たちからの「ありがとう」という言葉だった。
社会的な評価も手にして初めて、「自分はこの世界において、こうした声の代弁者としての作家になろう」と踏ん切りがついた。
あえて"王道"は避けてきた

なぜ人は、人を虐げないと生きていけないのか。
(『だから、人間は滅びない』, 幻冬舎)
デビュー以来、向き合い続けてきたテーマだ。だからこそ、多くの人があえて直視したいとは思わない人間の一面を描く。
「人間は常に日の当たる道だけを歩いて生きていけるはずがない。時には、事故や災害、犯罪を経験して転んだり、しゃがみこんでしまうものです。そんな中で、もしも明るく楽しく、人生の"王道"を歩いている人に向けた表現しか存在しなかったら、転んだり、しゃがみこんでも生きていく人のことは誰がわかってあげることができるのでしょうか?」
「たとえ過酷な状況にあっても、自分たちのことはわかってくれている。そう思ってもらえる作家になりたい。常に大ヒットするのは、明るい世界を描いたものかもしれません。でも、そうしたものを描く作家は既にいますから、もういいんです。それは、他の誰かにお任せします」
「僕は転んで、しゃがみこんで、それでも生きていく人たちのために表現できる作家になれれば本望です」
社会のメインストリームでは語られない声にこそ、作家は耳を澄ませる。
