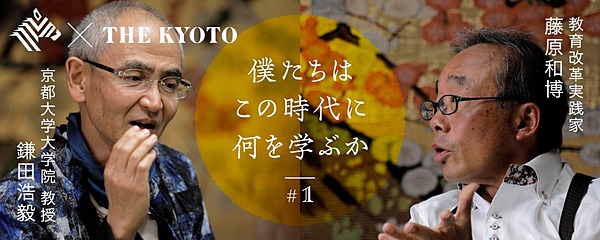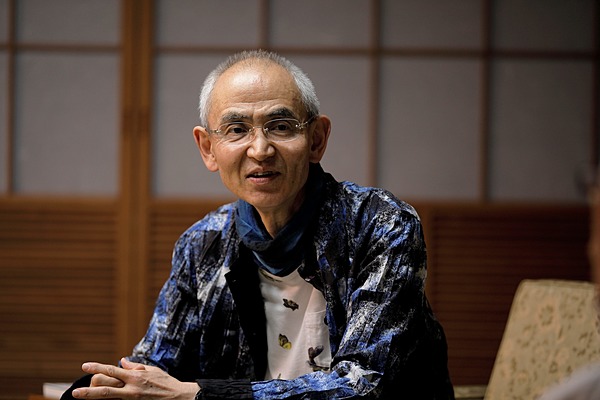【藤原和博×鎌田浩毅】 真に必要とされる「学び」の正体
2020/6/20
NewsPicksアカデミアは、京都発の文化・アートの新サービス「THE KYOTO」と連携し、「THE KYOTO ACADEMIA」という新プロジェクトを始動。記事、イベントなどを通し、「with/ポストコロナ時代」を⾒据えた「豊かさの再定義」を進めていく予定だ。
今回は特別対談として、教育改革実践家の藤原和博氏が京都を訪問。京都大大学院人間・環境学研究科教授の鎌田浩毅氏と、「いまこそ求められる学び」について語り合った。(聞き手:THE KYOTO編集長・各務亮)
教育とは「伝染・感染」
──現在のように不確実な時代こそ「教養」を学ぶことが必要と言われます。お二人が考える「教養を身に付ける際のポイント」について教えてください。
鎌田 身に付けるための基本はやはり読書だと思います。私は京大で地球科学をずっと教えていますが、火山について教えるとき、新井白石の『折たく柴の記』に記述されている約300年前の富士山噴火について話すと、生徒は火山学の講義内容の理解が一気に進みます。これは文学や歴史などの幅広い教養が不可欠であることを物語っているのではないでしょうか。
藤原 同感です。読書というと、私は乱読を勧めています。乱読するとさまざまなものが頭の中でつながり、自ら答えを出す「情報編集力」の基礎となります。私はこの「情報編集力」の大事さをずっと発信し続けています。
また、遊びの要素も大切です。特に子ども時代の過ごし方は大きく影響します。
私の場合、小さいころは野を駆け回り、たっぷりと時間があった大学在学時は、若者らしく流行を追い回したり、アルバイトをしたり、海外を巡ったことがベースになっています。

藤原和博(ふじはら・かずひろ)
1955年生まれ。78年東京大学経済学部卒業後、リクルート入社。東京営業統括部長、新規事業担当部長などを歴任。93年からロンドン大学ビジネススクール客員研究員。96年より年俸契約の客員社員「フェロー」制度を人事部とともに創出、自らその第1号に。教育、ビジネス、生き方など、幅広い分野で著書がある。ちくま文庫から『本を読む人だけが手にするもの』『必ず食える1%の人になる方法』など人生の教科書コレクション創刊。人気番組のもとになった『世界でいちばん受けたい授業』(小学館)も。
鎌田 私は藤原先生と同世代かと思いますが、子どものころはベーゴマとかメンコが全盛でした。大学生時代は4つのサークルの掛け持ちで忙しく、夜行バスでスキーには行きましたが、つまらない授業にはほとんど出席せず、飲み屋に通っていました(笑)。
だから就職は公務員で拾ってもらったようなもので、要は落ちこぼれでした。実は火山学も泣く泣く始めたようなものです。
藤原 そういう遊びこそが「生き生きとした学び」に通じますよね。教育は、教える側、つまりプレゼンター自らがエネルギーを見せないといけません。教育というのは「伝染・感染」だと私は思っています。だから私は手書きボードは使いますが、箇条書きを並べただけのパワーポイントは一切使いません。
「子どもが読書をするにはどうしたらいいか」とよく親から相談されますが、大事なのは親が夢中で本を読んでいる姿を見せること。
例えば、仮に中身はマージャンの本で、外側のカバーだけ真面目なものに替えてもいいから、親が夢中で読んでいれば、「おのずと読書の大切さは伝わりますよ」と話しています。
鎌田 おっしゃる通りですね。私も授業は黒板のみを使います。京大の授業では、面白いことを話しだすと出席する学生が増えます。大人が楽しそうに学ぶそのオーラが「伝染」するんでしょうね。
東大と京大の教育のスタンスの違いも面白いですよ。
東大では「ほとんどの学生をきちんと教育して世に出さないといけない」といった使命感がありますが、京大は、「専門分野は1人が育って、あとの学生は、楽しみながら教養を身に付けて卒業してくれればいい」と、がんじがらめではなく自由な雰囲気があります。
実際京都に来ると、きまじめに研究していない雰囲気があります。面白そうなことを追い掛けていると誰かしら集まってくるし、先生が大した研究をしていなくても弟子がすごいことをやっていたりする。
結果、トータルでノーベル受賞者が出ているんでよすね。
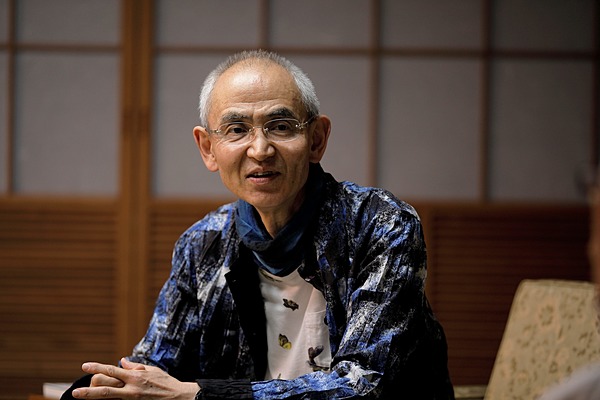
鎌田浩毅(かまた・ひろき)
1955年、東京都生まれ。79年東京大学理学部卒。通産省(現経済産業省)入省。同地質調査所の研究官として火山と出合い、とりことなる。米国カスケード火山観測所客員研究員など経て97年から現職。理学博士。専門は地球科学・火山学・科学コミュニケーション。テレビや講演会で科学を明快に楽しく解説する“科学の伝道師“。 「世界一受けたい授業」「情熱大陸」「ようこそ先輩 課外授業」「グレートネイチャー」などに出演。『新版 一生モノの勉強法』『理学博士の本棚』『一生モノの超・自己啓発』『理科系の読書術』『座右の古典』『地球の歴史』など著書多数。
大学こそ「9月入学」
──藤原先生はどういうふうに遊びとオフを分けていますか。
藤原 私は「オンとオフ」という分け方は全くせず、混然一体としています。講演や研修会講師が主な仕事ですが、平日がオンで土日がオフかと聞かれると非常に困ります。参加者からエネルギーをもらうことが楽しくて仕方ありませんから。
鎌田 よく分かります。
藤原 私たちの大学時代は時間が結構ありましたが、いまは文系でも課題が増え過ぎて全然遊びがないですよね。現在9月入学を巡る議論がありますが、高校以下は大反対で、何のメリットもないでしょう。
大学が9月入学に移行したとすると、春に高校を卒業して秋まで半年間あります。バイトざんまいでもいいし、海外の最貧国に行って自分に何ができるかを試したり、国境なき医師団でボランティアに参加したり、人生のベクトルを見つける時間に充ててもいいかもしれません。受験勉強態勢のままシームレスに大学に入るよりいいでしょう。
鎌田 そこは切ってやらないと駄目でしょうね。
──そんなお二人は、京都をどのように見ていらっしゃいますか。
藤原 私は京都の象徴として3点挙げます。「伝統を受け継ぎながら普通の街と共存する祇園」「ノーベル賞級研究者を輩出し続ける京大」「花札販売から世界的優良企業に育った任天堂」です。
いずれも京都の本質を体現する存在で、圧倒的な遊びの蓄積があります。
鎌田 東京を「勝つ都市」とすると、京都は世界有数の観光都市かつ「深める都市」とでも言いましょうか。別の視点で見ると、東京はオンで京都はオフ。そういうバランスを保ちながら日本文化は成り立っていると言えます。
いま『デジタルで読む脳×紙の本で読む脳』(メアリアン・ウルフ)がベストセラーになっていますが、効率よく取れるネット情報へのアクセスは外せないにしても、紙から得る情報、実際の手触り感がある本は圧倒的に違うと思います。やっぱり私は本に戻ります。
人間は、紙の上に鉛筆で書いて消したり、試行錯誤したりすることによってクリエイティブなものを生み出します。それはきっと右脳を刺激するからでしょう。
私は加藤周一さんの『羊の歌』をいまでも大事に持っていて、いろいろな書き込みを高校生のころから加えています。40年経過して読んでみて、改めて感動しました。僕のライブラリーの一つであり、そういうところから自分なりの深みが出せるのではないかと思います。
この記事を読んでいる方に僕が伝えたいことは、ネット世界からもう一回原点回帰し、再度、紙の本に付き合ってみてほしいということ。そこにも京都の深みがあるのではないかと思います。

(写真:istock.com/Jakub Michankow)
注目している京都人
──これぞ京都文化という方を挙げてみてください。
藤原 3人挙げます。まず童夢の林みのるさん。スーパーカーのデザインで世界的に有名な方です。同社の本社には、なぜかゴルフのショートコースがあり、清流に釣り糸を垂らすこともできる。そういうたたずまいに「すごくしゃれているな」と衝撃を受けました。遊びのエッセンス満載で、僕としては憧れの人です。
次に面白いと思ったのは、キーヤン(木村英輝)という作家です。烏丸御池の地下のニシキゴイが天に舞い上がっていくような絵です。
実は僕の母方は狩野派。絵描きの家系なので、絵画は見慣れているんですが、彼の作品には驚きました。金や朱の使い方が大胆で、青や藍も秀逸、とりわけ大きな絵がいい。僕は原画も持っていますが、想像を超える着想力です。
最後は、自然の造形美を伝える「ウサギノネドコ」で、吉村紘一氏が京都と東京に店を構えています。4センチ角ぐらいの透明なアクリル箱にタンポポの綿を閉じ込め、その綿がそのまま中で浮いている置物は若い人に大変な評判です。最近印象深いなと感じたのは、咲いたサクラの花を、そのままアクリルの中に閉じ込めたプロダクトですね。
──京都には人を育てる土壌があるのでしょうか。
鎌田 仏教で言うような「空・無」が学びには必要です。京都には思考を妨げる余計なものがないから、ぶつからずに突き抜けられるのではないでしょうか。藤原先生のおっしゃる3人は、ミラノでもニューヨークでもできないことが京都ではできたのかもしれません。
哲学の泰斗・西田幾多郎の京都大学在職時も、ある意味、何をやってもオーケーな雰囲気がありました。数学者の森毅と動物行動学者の日高敏隆も京大の名物教授です。
彼らは2人とも東大出身ですが、京都に来てから伸び伸びと学問と教養を発信し始めた。羽を大きく伸ばせたのでしょうね。実は僕もまったく同じタイプです。
京セラの稲盛和夫さんやオムロンの立石一真さんをはじめ、たくさんの起業家が京都に来て事業を起こし、世界的企業に成長しています。人が育ちやすい京都だからこそ、ビジネスでも学問でも本当の自分の力を発揮できたと思います。
東京という中央から離れられることが僕にとってのユーティリティですし、まさにそこに京都の優位性があります。これがずっと離れた南洋の孤島では駄目でしょう。新幹線で2時間強の地に1200年の文化と伝統がある。京都はそういう非常に絶妙な位置にあります。
藤原 京都は、祇園や南禅寺庭園など街全体を「舞台」として「演出」する力にもたけていますよね。そこにも奥深さを感じます。

(写真:istock.com/Peera_Sathawirawong)
※明日掲載の後編に続く
(構成:佐藤寛之、写真:伊藤信)