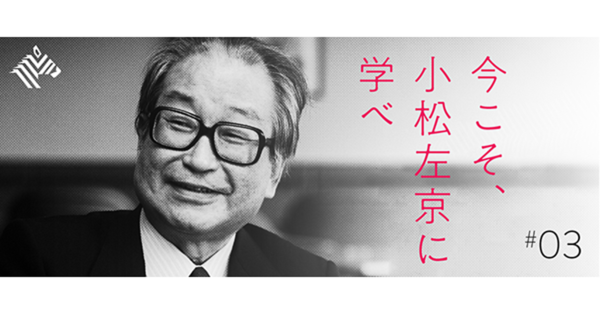【近内悠太】非常時こそ「逸脱的思考」を鍛えよ
コメント

注目のコメント
小松左京や星新一も好きですが、個人的には日本のSF作家の中で最も好きなのが筒井康隆です。
つまらない「良識」なんてものはかなぐり捨てた物語を軽妙洒脱に展開する作品群にうっかり出会ってしまったがばかりに、人格形成に相応の悪影響を受けてしまいました。
『時をかける少女』しか知らない人が読んだらひっくり返るような作品が多々あります。
現代のネット炎上も古くから予見していた作家であり、言葉狩り騒動からの断筆宣言に至る経緯など、その言動もまた作品化した人物だと言えるでしょう。
中学生の頃に彼の講演を聞きに行ったことがありますが、そんな筒井康隆をもってしても、阪神大震災の際、下水道の停止によって生じた大混乱は予見できなかったと話していた事が大変印象に残っています。まさに、事実は小説より奇なり、なんでしょうね。
いずれにせよ、「自分が当たり前と思っていることは本当に当たり前なのか?」「正しいと思っていることは本当に正しいのか?」を根本から見直すうえで、SFは非常に有効なのだと思います。
一方で、一定以上の既成概念に染まった後だと、まじめに向き合えば向き合うほど、真芯に迫るSFの読者体験は不快なものになるんじゃないかという気もします。
インスタントに鍛えられる「思考」なんてものは、思考でもなんでもないんじゃないかとも感じてしまいますが、こうしたひねくれ感が、青年期にSFと出会うということの意味なんだと思うことにします。近内さんのインタビュー記事ですね。彼と先日リリースされた対談でもお話したことなのですが、この「逸脱的思考」というのは、我々が暗黙のうちに一体何をしているのかを明らかにする上でとても大切な考え方だと思うのです。
僕は、精神障害ケアのコミュニティの「べてるの家」の当事者研究の中で、「反転」という考え方にとても衝撃を受けたのですが、問題があった時に、それ自体を解決するのではなくて、再現性をもたせる、つまり、もう一度どうやったらその問題を繰り返すことができるか、ということをやったりしています。ここから見えてくることは、日常、私達が何をやっているのか、実はすごくいろいろな複雑な意味のネットワークの網目の中に生きているということです。
近内さんが議論する贈与と交換の関係はそこに関係していて、交換に見えるものがいかに贈与という複雑な意味のネットワークの中で繰り広げられているか、ということかと思うのです。
その複雑さを知る時、ライフハック的思考や、単純化された常識が機能しないことが、わかる。そうしたことがわかった時、私達の行いは大きく変わるだろうと思います。いま、一人のSF作家がふたたび注目を集めています。
『復活の日』『日本沈没』といったベストセラーを送り出した、小松左京です。
日常のすぐそばに潜むカタストロフの可能性を見抜いていた、小松の「逸脱的思考」とはどのようなものか。
なぜ小松は発信手段として「SF」というエンタテインメント形式を選んだのか。
小松左京作品に詳しい哲学者・近内悠太さんのデビュー著書『世界は贈与でできている』からお届けします。
「世界の論理の歯車がたった一つ狂うことで、この世界全体が悪夢へと簡単に変わってしまこと」をめぐる、とても刺激的な考察です。