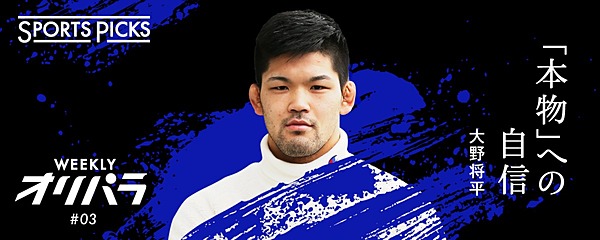【東京五輪】金子達仁、森保ジャパンが金メダル候補である理由
2020/1/23
東京オリンピックまで半年。その盛り上がりはまだ「関係者」にとどまる。解決しなければいけない問題も山積みだ。アスリートにとっては一生に一度と言えるほど「人生を賭けた戦い」。果たして彼・彼女らに注目は集まるのか──。ノンフィクション作家・金子達仁氏による寄稿。
94年のアメリカと96年のアメリカ
先日、老舗のスポーツ雑誌の編集部の人間からこんな質問を受けた。
「今回のオリンピックは盛り上がるのでしょうか?」
聞けば、近年オリンピックモノの刊行物の売れ行きは芳しくなく、雑誌社としたら、大会が盛り上がるかどうか、は死活問題だという。
彼らが心配するのは当然だろうが、すぐに私はこう言った。
「心配するな、1000パーセント盛り上がる」と。さらに付け加えれば、「スタートからフルスロットルで、盛り上がるはずだ」と。
理由は明確。とにかく格が違う。ほかのイベントと比べても規模が別格だ。
オリンピックは“アマチュアの祭典”というイメージがあったが、それは過去の話。そのスケールは圧倒的で、ラグビーのワールドカップやサッカーのワールドカップと比較にならない。
「去年、ラグビーワールドカップが盛り上がったよね!」っていうのがおかしく思えるくらい、とてつもない盛り上がりを見せるだろう。
かつてオリンピックの偉大さを知らされたことがあった。
いまから26年前。1994年のサッカーワールドカップを取材するため、アメリカへと向かった。現地に着いたら、アメリカ人からさんざんぱらこう聞かれた。
「なにしに来たんだ?」
私が「サッカーのワールドカップを観に来た」と言うと「それはなんだ?」という答えが圧倒的だった。空港での入国審査しかり。サッカーの会場から一歩離れてしまうと、現地の反応はそんなものだった。
つまり、サッカーワールドカップという大会が、アメリカのなかではまったく認知されていなかった。
ところが、その2年後にアメリカに行ったときは、まったく反応が違っていた。「なにしに来たんだ?」とは、誰からも聞かれなかった。アトランタ・オリンピックのことだ。

1996年に行われたアトランタ五輪の開会式。
たしかに、昨年のラグビーワールドカップも盛り上がった。しかし序盤戦は、それこそ地方のテレビ・ディレクターの言葉を借りれば、「バレーボールのワールドカップと変わらない」という程度の盛り上がりで、スタートから日本全土でラグビー熱は感じられなかった。
でもオリンピックは違う。
ラグビーやサッカーのワールドカップが盛り上がるのは、基本的には日本戦だけ。あとの試合はみんなお客さんだ。
ワールドカップで言えば、日本の試合はラグビーだったら1週間に1試合のペースで、サッカーだったら3日に1試合のペースだが、オリンピックは連日、日本人がメダルに挑戦する。
去年のラグビーワールドカップで言えば、毎試合アイルランド戦やスコットランド戦が見られるイメージを想像してみてほしい。毎日、毎試合、クライマックスが続くわけだから、盛り上がらないわけがない。
競技の未来を変える2つの種目
その東京オリンピックで、個人的に注目している競技を挙げるとしたら、まずはバスケットボールだ。
八村塁と渡辺雄太。ふたりの日本人のスター候補がいるバスケットボールという競技は、大変なことになる可能性があるだろう。今回のオリンピックは、日本のバスケットボール界にとって明治維新的な位置づけになるかもしれない。いずれ、歴史を振り返ったとき、ここからすべてが始まったと言われる日が来るだろう。

NBAで活躍する八村塁は新たな日本人のスター候補であり、「日本バスケ界の可能性」でもある。
正直勝つのは難しい、というのがバスケットボール関係者の見立てだろうけれど、そうは言っても、強豪に食らいつく姿が見られたら、競技人口の多いバスケットボールの人気が一気に火がつく。
すでに火が噴いている状態とも言えるけれど、「世界に通じる日本」という絵が、これまで描けていなかった。それがいまひとつメディアの熱を取り込めなかった一因だと思っていて、そのあたりが全面的に変わってくるかもしれない。
そう考えると、バスケットボール界にとっては、去年のラグビー界以上に千載一遇の大チャンス。人気スポーツがまだ日本に生まれるきっかけになってくれたらいいなと思っている。
バスケットボールに続いてその人気が爆発しそうな競技が、スポーツクライミングだ。
男子では楢崎智亜、女子では野口啓代(ともにTEAM au)がすでに世界トップクラスに位置しているが、日本のお家芸になる可能性を秘めている。

スポーツクライミングの野口啓代はメダル候補としても注目を集める。
理由は三つ。
まず見ていて抜群に面白いこと。
それから欧米人に比べると、日本人は骨格が細い。重いものを持ち上げていくのと軽いものを持ち上げていくのでは、軽いほうが当然有利。必ずしも筋肉で勝負する競技ではない。日本人の身軽さというのが、欧米人がどんなに頑張っても手に入れられない資質だ。この大会をきっかけに日本の独壇場になると思う。
もうひとつの理由は、日本が山の国であること。その気になったらいくらでもトレーニングができる。さらに言うと、この競技がスポーツとして根付いていくことで、地方にとっても集客力を見込める可能性がある。
このスポーツは地方と都会のハンデがない。世界を見渡しても、野球にしてもサッカーにしてもどうしても都会にいないと、いい選手が育ってこない時代に来ている。でも、スポーツクライミングはどんな田舎であってもスター選手が生み出せる。これからの日本の将来を考えていくうえでも、大事にしていきたいスポーツだと思う。
サッカー日本代表は金メダル候補
バスケットボール、スポーツクラミング以外の注目競技を挙げれば、やっぱりサッカーの男子は外せない。
というのも、日本が金メダルを獲れるとしたら地元大会しかないからだ。
過去を見ても、スペインが1992年のバルセロナ大会で初めて金メダルを獲得した。あのブラジルが金メダルを手に入れることができたのも、前回のリオ大会だった。サッカーの場合、ホームアドバンテージのメリットは、どのスポーツに比べても圧倒的だ。
ワールドカップで優勝する可能性は、現時点で1パーセントあるかないかだが、今回のオリンピックで日本が金メダルを獲る可能性は、おそらく30パーセントくらいある。
2012年のロンドン大会のとき、関塚隆監督率いる日本はベスト4入りを果たした。ホームでもなんでもなく、突出した選手がいたわけでもなかったが、それでもメダルが手にかかるところまで勝ち上がることができた。
優勝のポイントは、主力選手を呼べるかどうか。
8年前のチームと比べて、今回は海外でプレーしている選手を中心に構成されるだろう(編集部注:ロンドン五輪代表チームの海外クラブ所属選手は6人。吉田麻也=VVVフェンロ、酒井高徳=シュツットガルト、酒井宏樹=ハノーファー、清武弘嗣=ニュルンベルク、宇佐美貴史=ホッフェンハイム、大津祐樹=ボルシアMG/所属クラブは当時のもの)。
なかでも、冨安健洋(現・ボローニャ)は欠かせない。もちろん、久保建英(現・マジョルカ)には頑張ってもらわないといけないのは当然として、冨安はA代表のなかでももはや抜けた存在。彼が呼べるかどうかは、まさに大問題だろう。

五輪代表が金メダルを獲得するのに欠かせない存在、冨安健洋。
ライバルは南米勢、アジア勢か、アフリカ勢か。ヨーロッパのチームは、U-23のチームで活動していない。チームとして勝つための訓練なんて一切していない。対して、アフリカ勢などは、オリンピックで結果を出してヨーロッパに売り込みをかけたい。モチベーションが全然違うだろうし、発展途上国ほど、オリンピックを国威発揚の場として見ている。ずっと前からそうだが、オリンピックに関して言えば、いわゆる第三世界の勝負になる。
28年前、日本はブラジルを破った。あのときは本当の衝撃だった。アトランタでブラジルに勝つことなんて、0.1パーセントも想像していなかった。
でも、今回は日本が勝ったとしても驚きではない。30パーセントくらい優勝の可能性があるのだから。ここで勝たなくていつ勝つのか──。
何度も言うけれど、日本が金メダルを取れる、千載一遇のチャンスだ。
もっとも、昔と違って、選手たちは小学生の頃からワールドカップに出場している日本を見ている。さらに言えば、20歳前半の選手たちは、9年前になでしこジャパンが女子ワールカップで世界一になるところを見ている。
世界一になる日本、という“心の壁”がない。東洋の魔女と呼ばれた女子バレーが1964年の東京オリンピックで勝ったあと、男子バレーが1972年のミュンヘン・オリンピックで金メダルを獲ったように、世界一になる日本を見て育ってきた。金メダルを獲るのは、夢物語ではなく、現実目標として捉えている。
言い換えれば、今回のオリンピックは、世界一に対するコンプレックスのない世代が臨む大会になる、ということだ。
それこそ、テニスの大坂なおみが世界ランキング1位になって、100メートルを9秒台で走る日本人選手がジャンジャン出てきている。昔は日本人というのが、世界大会で勝てないことのエクスキューズだった。そういう時代は完全に終わっている。むしろ、頭が追いつかないのは、我々“おっさんメディア”かもしれない(苦笑)。
そんなおっさんメディアが勝手に作ってしまった「ガラスの壁」が今回、木っ端微塵にすべての競技で砕かれる。それが私の一番の夢でもある。
金子達仁(かねこ・たつひと)。1966年1月26日、神奈川県生まれ。テニス専門誌、サッカー専門誌編集部記者を経て1995年に独立。翌年には「断層」「叫び」で、ミズノスポーツライター賞を受賞。著作に『28年目のハーフタイム』『決戦前夜』『熱病フットボール』『ターニングポイント』『泣き虫』『ラスト・ワン』など。近著に『プライド』がある。
WEEKLYオリパラ
- 【一目でわかる】東京五輪代表はいつ、どのように決まる?
- スプリンター×テクノロジーは「人類最速」を生み出すか
- 【卓球】東京五輪へ最終決戦、水谷隼、平野美宇の逆転は?
- 【柔道・大野将平】圧倒的王者は「粗野なれど卑にあらず」
- 【パラスポーツ】「息づかいで見える」金メダリストの視界
- 【中村輪夢】BMX界の寵児、東京五輪で誰より高く
- 山田拓朗はなぜ5度目のパラリンピックを目指したか
- 東江雄斗が語る「世界最下位」「東京五輪」「まだまだだね」
- 【中村敬斗】「ブレイクのときを待ち続ける」海外での挑戦
- 【トップの流儀】加藤健人「始めなければ始まらない」
- 【文田健一郎】「マットまで一歩、一歩」ゆっくり歩く理由
- 【小野真由美】「何かを得たければ、何かを諦めなければいけない」
- 【大迫敬介】高1から書き続けた「東京五輪」とさらなる飛躍
(構成:小須田泰二、編集:黒田俊、デザイン:松嶋こよみ、写真:GettyImage)