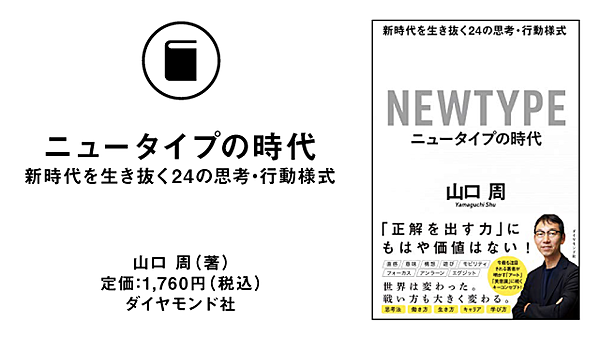社会構造の変化やテクノロジーの進化にともない、個人や企業は、新しい考え方や成功モデルへの書き換えが求められている。サイエンスによる答えがコモディティ化した現代では、「正解を出す力」に価値はなく、資本主義社会で評価されてきた能力や資質は、急速に凡庸なものへと変わりつつあるのだ。
では、私たちはどのようにして「オールドタイプ(旧型の価値観)」から「ニュータイプ(新型の価値観)」へシフトしていけばいいのか。『ニュータイプの時代 新時代を生き抜く24の思考・行動様式』(山口周〔著〕、ダイヤモンド社)より、4回連載でお届けする。(第1回)
「努力すれば夢は叶う」という価値観の危険性
日の当たらない場所であっても、地道に誠実に努力すれば、いつかきっと報われる、という考え方をする人が少なくありません。つまり「世界は公正であるべきだし、実際にそうだ」と考える人です。
このような世界観を、社会心理学では「公正世界仮説」と呼びます。公正世界仮説を初めて提唱したのは、正義感の研究で先駆的な業績を挙げたメルビン・ラーナーでした。
ラーナーによれば、公正世界仮説の持ち主は、「世の中というのは、頑張っている人は報われるし、そうでない人は罰せられる」と考えます。
もちろん、このような世界観を持つことで努力が喚起されるというのであれば、それはそれで喜ばしい面があることは否定しませんが、頑なに持つことは、むしろ弊害の方が大きいと言えます。
注意しなければならないのは、公正世界仮説に囚われた人が垂れ流している「努力すれば必ず夢は叶う、もし夢が叶わないのだとすれば、それは努力が足りないからだ」というような極端な主張、まるで「努力原理主義」とでも言うしかないような主張です。
確かに、モノを生み出すことがそのまま価値の創出に直結するような時代であれば、努力を積み重ねることでパフォーマンスを高めることができたかもしれません。しかし、これまで本書において再三にわたって指摘してきた通り、現在の世界では「モノ」が過剰化し、そもそもの「価値」の定義からして難しくなっています。
このような時代にあって「努力すれば夢は叶う」という価値観に固陋に執着するオールドタイプの思考様式は極めてリスクの高いものになりつつあります。
「1万時間の法則」のお粗末さ
「努力は報われる」という主張を無邪気に振り回している人たちが主張の根拠としてよく持ち出してくるのが、いわゆる「1万時間の法則」です。「1万時間の法則」とは、アメリカの著述家であるマルコム・グラッドウェルが、著書『天才! 成功する人々の法則』の中で提唱した法則で、骨子をまとめれば次のようになります。
・大きな成功を収めた音楽家やスポーツ選手はみんな1万時間という気の遠くなるような時間をトレーニングに費やしている
・1万時間よりも短い時間で世界レベルに達した人はいないし、1万時間をトレーニングに費やして世界レベルになれなかった人もいない
つまり「1万時間の練習を積み重ねれば、あなたは一流になれますよ」ということを言っているわけですが、では何を根拠にそのような大胆な主張をしているかというと、グラッドウェルは次の3つをその根拠にしています。
・一流のバイオリニストは皆、子供時代に1万時間を練習に費やしている
・ビル・ゲイツは学生時代に1万時間をプログラミングに費やしている
・ビートルズはデビュー前に1万時間をステージでの演奏に費やしている
形式論理学を多少ともかじったことのある人であれば、ここまで読んだ時点で、上記の事実からグラッドウェルの導いた「1万時間の練習を積み重ねれば一流になれる」という命題が導けないことにすぐに気づいたでしょう。
これはグラッドウェルに限ったことではなく、「才能より努力だ」と主張する多くの本に共通しているミスです。
たとえばデイビッド・シェンクによる『天才を考察する』では、「生まれついての天才」の代表格であるウォルフガング・モーツァルトが、実際は幼少期から集中的なトレーニングを積み重ねていた、という事実を論拠として挙げて、やはり「才能より努力だ」と結んでいるのですが、これはよくある論理展開の初歩的なミスで、実はまったく命題の証明になっていません。
まず、真の命題は次のようになります。
「命題1 天才モーツァルトも努力していた」
この命題に対して、逆の命題、つまり、「命題2 努力すればモーツァルトのような天才になれる」を真としてしまうのは、子供がよくやる「逆の命題」のミスです。
正しくは、「命題1 天才モーツァルトは努力していた」という真の命題によって導かれるのは、対偶となる命題、つまり、「命題3 努力なしにはモーツァルトのような天才にはなれない」であって、「努力すればモーツァルトのような天才になれる」という命題ではありません。
では努力は「まったく意味がない」かというと、もちろんそういうわけではありません。
たとえば、プリンストン大学のマクナマラ准教授他のグループは「自覚的訓練」に関する件の研究についてメタ分析を行い、「練習が技量に与える影響の大きさはスキルの分野によって異なり、スキル習得のために必要な時間は決まっていない」という、極めて真っ当な結論を出しています。
興味深いのは同論文がまとめた、各分野についての「練習量の多少によってパフォーマンスの差を説明できる度合い」です。
・テレビゲーム 26%
・楽器 21%
・スポーツ 18%
・教育 4%
・知的専門職 1%以下
グラッドウェルはバイオリニストに関する研究から「1万時間の法則」を導き出したわけですが、この結果をみれば、確かに楽器演奏は相対的に、練習量がパフォーマンスに与える影響の大きい分野であることがわかります。
しかし、私たちの多くが関わることになる知的専門職はどうかというと、努力の量とパフォーマンスにはほとんど関係がないということが示唆されています。
この数字を見ればグラッドウェルの主張する「1万時間の法則」が、いかに人をミスリードするタチの悪い主張かということがよくわかります。
「努力は報われる」という主張には一種の世界観が反映されていて確かに美しく響きます。しかしそれは願望でしかなく、現実の世界はそうではないということを直視しなければ、「自分の人生」を有意義に豊かに生きることは難しいでしょう。
「努力のレイヤー」を変えない限り、人一倍努力しても無意味
「努力」に意味がないのではなく、ポイントなのは「努力のレイヤーを上げる」ということです。
努力には階層性があります。たとえばある職場で人一倍努力しているのになかなか成果が出ないというとき、もしかしたらそれは努力不足なのではなく、そもそも「場所が悪い」、つまりその仕事が求める資質と本人の資質がフィットしていない可能性があります。
このとき、そのままひたすらに頑張るという「レイヤー1の努力」を続けることもできますし、「向いていない」という事実にしっかりと向き合い、自分にはどのような仕事が向いているかと考え、さまざまな情報を集めて次の仕事を見つけるという「レイヤー2の努力」を始めることもできます。
職場の人から見れば「レイヤー2の努力」をしている人は「逃げた」ように見えるかもしれませんが、そんなことはありません。むしろ、あてがわれた場所を無批判に受け入れ、ひたすらにわかりやすい努力を続けるレイヤー1の行動様式こそ「安易な努力に逃げた」ということもできるでしょう。
レイヤーの異なる2つの努力のうち、今後、より求められることになるのはレイヤー2の努力でしょう。現在、私たちのキャリアは中長期的な伸長傾向にある一方で、世界の変化は目まぐるしく、自分と仕事との関係性はかつてより短期間で変わっていくことになります。
このとき、レイヤー1の努力だけに依存して状況を打開しようとするオールドタイプの行動様式を続けていれば、どうやっても成果の出ない場所で不毛な努力をし続けるということになりかねません。
このような世界にあっては、柔軟に機動しながら、常に自分の価値が相対的に高まるポジションにい続けるというニュータイプの行動様式が求められます。
ポジショニングを変えてノーベル賞を取った山中伸弥
ポジショニングを変えることで、自分の価値が最も高まる場所にポジショニングするというニュータイプのワーキングスタイルを実践し、大きな成果に結びつけたのがノーベル賞を受賞した山中伸弥氏のキャリアです。
山中氏は、スポーツ整形外科医を夢見て1987年から整形外科研修医として勤務するものの、手術のあまりの下手さに「向いていない」と感じて、2年後には基礎医学を学ぶため薬理学研究科に入学しています。
しかし、伝統的な薬理学にも強いフラストレーションを抱いて、ここでも挫折してしまうのですが、研究の最中にノックアウト・マウス(遺伝子の機能を推定するために、特定の遺伝子を不活性化させたマウス)に出会って衝撃を受け、ここに新しいブレークスルーへの道があることを直感します。
その後、博士号を取得し、アメリカのグラッドストーン研究所でゼロから分子生物学を勉強し、どんな細胞にも変化するES細胞に強い興味を持ちます。帰国後は、大阪市立大学医学部助手になってES細胞の研究をゼロから始めます。
研究の内容は「受精卵から取り出して培養した生きた胚からではなく、皮膚などの体細胞からES細胞と同じような細胞を作る」という、まだ誰もやったことのないチャレンジでした。
できるかどうかはわからない。しかし、もしできれば、受精卵を使うという倫理的問題と免疫拒絶問題の両方をクリアできる。
できなければ、科学者をあっさりあきらめて町医者をやる、というのが助教授に就任したときの覚悟だったそうです。この研究がやがてiPS細胞の発見へとつながり、山中氏にノーベル賞をもたらしたのです。
山中氏のキャリアは、私たちにさまざまな示唆を与えてくれます。
山中氏が最初に目指したキャリアはスポーツ整形外科医でした。ですが、これは自分に向いていないと考えて、2年後にはキャリアを転向しています。結構短いな、というのが多くの人の印象ではないでしょうか。
しかし医師としてどの領域で生きていくか、まさにどこにポジショニングするかを選べる期間はそう長くはありません。そのように考えてみれば「2年で見切る」というのも一つの勇気だと考えるべきなのかもしれません。
そしてその後、薬理学の世界に身を転じた山中氏は、ここでも挫折してしまいますが、このとき、後の研究につながる大きなヒントを得ています。
挫折して逃げる。ただし逃げるときにタダでは逃げない。そこから盗めるものはできるだけ盗んで、次のフィールドで活かす。そのようにしてフィールドを越境しているからこそ、知識や経験の多様性が増加し、それがやがてユニークな知的成果の創出につながったわけです。
山中氏のキャリアは、一般に日本では忌避されがちなニュータイプの行動様式、つまり「一所懸命に頑張らず、次々にポジショニングを試すことで、最も自分が輝ける場所を探す」という行動様式がもたらす大きな成果を示しています。
(デザイン:月森恭助 バナー写真:masterzphotois / iStock)
※本記事は書籍『ニュータイプの時代』より抜粋して転載しています