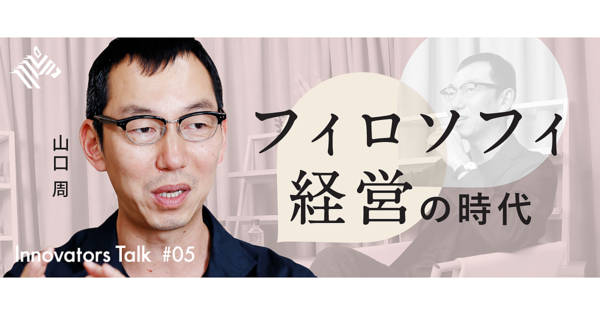会社は“バンド化”する。激変する令和時代のトレンドを読む
コメント

注目のコメント
フィロソフィ経営の時代、楽しく読ませていただきました。会社が「バンド化」するのであれば、そこにいる人材の流動性や音楽性の進化は必須。意味を生み出す感性をどう育てていくか。
あとは「利便性の方向に富の源泉はないので、この先は文化的な豊かさに向かっていく」というのが文明史的に面白い。利便性=富の源泉、芸術=無用の美学みたいなところがというのが近代のイデオロギーとしてはあるので、未来に向けてそれが本当に変わっていくのか。
以前、「つまらないものはつくらない」という考え方で不動産のセレクトショップとしてのR-不動産を展開しているスピークの林さんと話したときにも感じたのですが、個人的には、どの市場でも、少なくとも世の中の10%くらいはそういうニーズがあると思っています。
バンドマンが先に変わるのか、リスナーが先に変わるのか。両方なのか。どこまで変わっていくのか。なんか朝から色々と妄想してしまいました。山口周さんとオルビス小林さんの対談、最終回は今後の会社とビジネスの変化についての考察です。
山口さんは、会社の未来は「バンドになる」と予測します。たくさんの人が所属する大企業や大手、あるいは長期に継続する会社は、もう時代遅れになるということです。
それは成長したけど、画一的で閉塞感があった昭和時代とは対極的な、みんながそれぞれ個性をもって楽しむという、明るい未来です。
最後にAI、ゲノムで変わる化粧品業界のお話も興味深いです。全5回、読んでいただき、ありがとうございました。バンド化する社会において、メンバーとして声がかかるよう、怠りなく精進したいもの。
歌が歌えるのか、ギターが弾けるのか、マネジメントができるのか、はっきりしていた方がいい。
「今は富の源泉が利便性にシフトしてしまっていて、文化的な豊かさを生み出す方向に富が向かっていません」
「どうでもいい機能を付けるために、みんな一生懸命、仕事をしているようなものです」