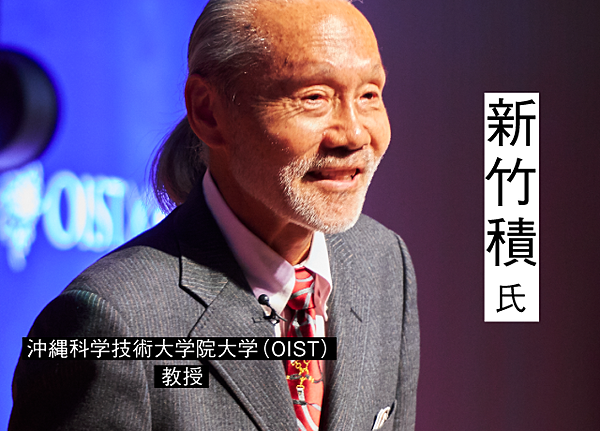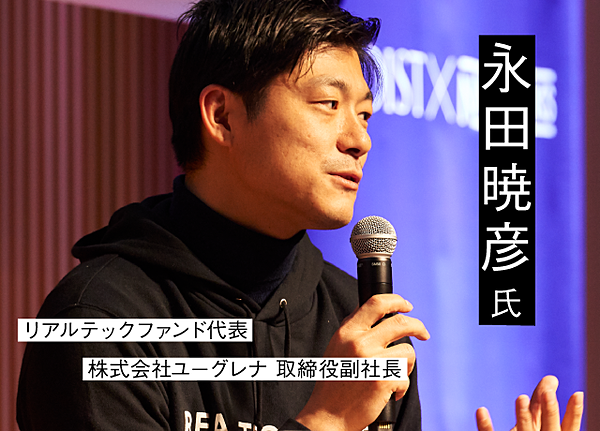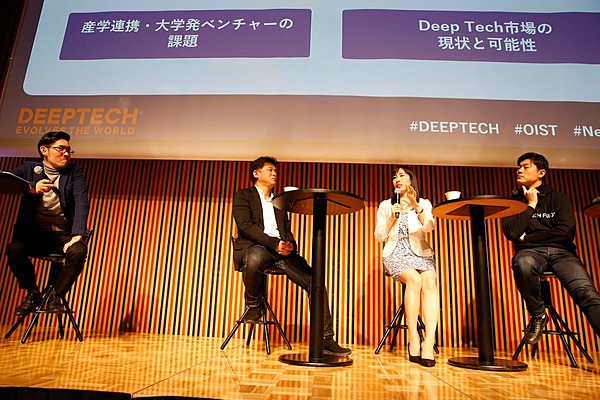【Deep Tech】科学技術とビジネスの最新融合。その生態系とは
2019/3/26
先端的な科学技術の優れた研究成果を、イノベーションを起こすための競争力とする「Deep Tech」。その潮流がグローバルに広がりつつあるなか、日本でも「アカデミック✕ビジネス」の新しい融合の動きが始まっている。
大学を拠点とした新たなイノベーション・エコシステムの創出を目指す沖縄科学技術大学院大学(OIST)と、NewsPicks Brand Designの共催によるイベント「OISTフォーラム2019 “Deep Tech”が進化させる社会」のレポートをお届けする。
【120秒で分かるOISTフォーラム】
革新的なビジネスをいかに生み出すか。イノベーションによる社会の発展を志す科学者・起業家・投資家たちから、いま世界的に注目が集まっているのが「Deep Tech」の領域だ。
“アジアの中心地・沖縄に最高水準の英知を結集し、科学技術の研究と教育によって世界を変えるイノベーションを創出する”という構想から10年余の期間を経て設立された「沖縄科学技術大学院大学(OIST)」は、最先端の研究施設とインキュベーション施設を有する次世代型アカデミアだ。
3月5日、東京・神田明神ホールで開催された『OISTフォーラム2019』には、Deep Techに造詣が深いイノベーターが集結し、「アカデミック✕ビジネス」の融合によるイノベーション・エコシステムの創出について議論を交わした。
会場には、Deep Techというキーワードに関心を持つ起業家やベンチャーキャピタリスト、そしてさまざまな大学に籍を置く研究者や学生たちが数多く来場し、これからの大学発ベンチャーの可能性について語り合った。
OISTが取り組むイノベーション・エコシステム
『OISTフォーラム2019』の冒頭は、沖縄振興・科学技術政策の担当である内閣府副大臣・左藤章氏によるスピーチから始まった。
続くオープニングセッションでは、アサヒグループホールディングス株式会社の代表取締役会長であり、日本経団連審議会副議長を務める泉谷直木氏が登壇。
「日本経団連が提言する『Society 5.0』は、先端的なテクノロジーと、多様な人材によるクリエイティビティの融合によるイノベーションの創出、それによる第4次産業革命の実現を目標に掲げています。
そのためには、優れた科学者・研究者が集まるアカデミックの研究室で育まれているシーズに光を当て、産学連携を活発化させる必要があります」と語った。そして産学連携の強化には、
①企業のアセット解放によるオープンイノベーションの定着化
②シナジーある企業同士のM&A
③大学発のディープサイエンス系スタートアップの支援及び知財支援
これら3つの要素が重要だと説いた。
そこで期待されているのが、先端的なテクノロジーの研究開発と、それを生かしたビジネスを創出するインキュベーション施設を兼ね備えた「次世代のアカデミア」だ。
次に登壇したOIST首席副学長のロバート・バックマン氏は、2011年に創立されたOISTについて、次のように説明した。
「OISTが取り組むイノベーション・エコシステムの創出は、まさにアカデミック✕ビジネスのシードを生み出すためのものです」
OISTは日本の大学でありながら、40を超える国と地域から集った優秀な学生たち、そして多様な分野における知と独創性を持つ一流の教授陣を擁し(学生の80%以上、教員の60%以上が外国籍)、英語を公用語として使用する。まさにグローバルな“人材のるつぼ”だ。
国際的にも卓越した研究環境が整っているほか、「研究のみならず、ビジネス領域でもメンターとなる人材が世界中から集まっている」とバックマン氏は強調する。
「ユニークな点は学科や学部による境界線がないことです。垣根を取り払うことで、異分野の研究者同士の交流が生まれ、画期的な研究やビジネスが生まれやすい環境を提供しています。
OISTにはチャンス、リソース、知見、スタートアップインキュベーターのすべてがそろっており、先端的な研究成果の商業化の実現に最も近いアカデミアと言えるでしょう」
なぜ「Deep Tech」に注目すべきか
基調講演では、Deep Techの可能性を示す研究事例のひとつとして、沖縄科学技術大学院大学(OIST)教授である新竹積氏が登壇した。新竹教授は現在、海岸で立つ波のエネルギーを利用する「波力発電」の挑戦的な研究を行っている。
「海の波は、天候に関係なく24時間発電することができる、次世代の“永久不滅のエネルギー”として注目されています。現在、独自に設計した小型波力発電機をモルディブの海に設置し、実用化に向けた研究を重ねています」
自らの研究成果についてプレゼンしながら、新竹教授は「先端的なテクノロジーを生み出し、社会に実装するために、科学者にはスピードに乗って走るリズム感と、技術開発に対するあくなき情熱が必要だ」と語り、聴衆の研究者たちへエールを送った。
続いて登壇したのは日本ディープテック協会理事の中島徹氏だ。
同氏はベンチャーキャピタリストとしてのキャリアを積み、現在は孫泰蔵氏が立ち上げたMistletoeで、世界14カ国で投資活動を行い、152のスタートアップとベンチャーキャピタルに投資している。
「私はDeep Techによるイノベーションについて、『独創的かつ複製困難であり、特許化された最先端の科学技術によって構築された、破壊的なソリューション』であると定義します。
しかし、それを実現するためには、科学的リサーチ、時間、資金の3点において、莫大なリソースが必要となります。このすべてを粘り強く応援してくれる環境が必要です」
中島氏は、かつて世界的なイノベーションを起こしたホンダやソニーの事例、日本企業がCDやDVDといったプラットフォーム(規格)の主導権を握っていた事例をひもときながら、「昔の日本企業はDeep Techを実践していた」と説明する。
「不可欠なのは“提案型エンジニア”の存在です。新たな市場カテゴリーを創出したウォークマンやiPhoneは、顧客の声から生まれたものではなく、新しいライフスタイルを送るための提案として生まれたプロダクトの好例です。
自ら提案することで、顧客のニーズの主導権を握っていくことができ、世界に通用するサービスやプロダクトが創出できるのです」
新たな“カテゴリー・クリエーター”となりうるスタートアップを輩出するには、正攻法だけでは難しく、産学連携によって「周りから固めていくのが良い」と中島氏は続ける。
「大学とスタートアップ、そして大企業の3者が連携してDeep Techを盛り上げていくことが必要です。そうして2周目、3周目の起業家やエンジェル投資家を輩出していく流れをDeep Tech領域で作っていくべきです」
また、その動きは日本国内だけにとどまらず、OISTのように大学が“ハブ”となってグローバルとのコネクションを作り、海外の投資家からの資金調達ルートを整備することも必要になってくるとも指摘した。
その後、新竹教授と共に聴衆からの質問に応えるなかで、中島氏は「Deep Techによるイノベーションが加速することで、再び日本のテクノロジーが世界の注目を集める時代が訪れる可能性があるでしょう」と締めくくった。
アカデミックとビジネスとの垣根をなくすには
日本からDeep Techの革新的ビジネスを生み出すために、何が必要か。フォーラム後半に行われたパネルディスカッションでは、大学発ベンチャーに関わる有識者として高橋祥子氏(ジーンクエスト代表取締役)、永田暁彦氏(リアルテックファンド代表/ユーグレナ取締役副社長)、そして仁木勝雅氏(ディープコア代表取締役)の3氏が登壇。モデレーターは佐々木紀彦(ニューズピックスCCO)が務めた。
──まず永田さんに伺いますが、ユーグレナは今日本で一番有名なDeep Techのベンチャーですよね。成功している理由を教えていただけますか。
永田 ユーグレナは東大発ベンチャーで資金繰りが厳しい状況も経験しながら、東証1部上場に至るまでに成長しました。
ユーグレナが成功できた理由として、「アカデミアっぽくなかったから」だと考えています。最初のチームビルディングの段階でマーケティング、テクノロジー、ファイナンス、ビジョンといった役割を明確に決めてスタートしました。
──普通の大学発ベンチャーは、そうではない?
永田 そもそも見ているものが違うという問題があります。科学的な研究成果は、企業の立場から見れば、社会課題を解決する=ビジネスとして利益につながるかどうかで価値が判断されます。
一方で研究者は、研究そのものに対し情熱を注ぐので、ビジネスの市場に合わせて研究を進めているわけではありません。市場ができようとできまいと、ただひたすら研究を続けるのです。
それゆえ、研究者たちの間には、「お金を儲けることは悪である」「儲けようとすると周囲から嫌われる」という風潮がいまだに残っている。
高橋 経営者と研究者の考え方の違いは、コミュニケーション課題ですね。研究者のなかでも人それぞれで、儲けたい人もいれば、儲かることによって、もっと研究ができるというモチベーションもあると思います。
例えば生命科学の成果を使ってビジネスを伸ばしたいのか、ビジネスイノベーションを起こして、生命科学の研究をより推進していきたいのか。本来は両立できるものですが、ある種の二元論になってしまっている。
仁木 日本発で世界にも通用する企業について、どういう人が創業したかという点で見ていくと、本田技研工業の本田宗一郎さんやソニーの井深大さんなど、技術者が起業しています。
海外のマイクロソフトやアップルも同じで、技術者が起業することがDeep Techのチームビルディングでは大事だと思っています。
日本の抱える課題は、企業でも大学でも同じ分野の人材で固まり過ぎてしまっていること。また、日本の社会システムとして、教育の中に「ダブルメジャー」の制度がないことも課題だと思います。
海外では、エンジニアでも経営やビジネスを学ぶダブルメジャーが一般化しています。この制度があればお互いの垣根を越えた交流が生まれ、ビジネスマッチングが加速するはずです。
高橋 同感です。以前、サマーダボス会議に出席したんですが、そこで出会った海外の投資家の方々はPh.D(博士)を持っている人が多かったですね。彼らはテクノロジーを理解しているので、研究者とも容易にコミュニケーションできます。私もダブルメジャーが日本に一番足りない部分ではないかと思っています。
──経営者、研究者、投資家。それぞれがお互いの領域に歩み寄ることができないとチームにならない。
永田 チームという観点でいうと、良いチームを作るには同じ船に乗せられるかどうか。行き先の示し方がとても大切だと思っています。しかし、実際にアカデミアの方とは多分にお付き合いがあるのですが、他人がわからないことを「他責」にしてしまう傾向があります。
高橋 私も以前は、研究成果を理解してもらえないことを「相手のせい」にしていました。そもそも研究者同士では、論文を読んで理解できない場合は「わからない方が悪い」というルールです。でも一般の議論では、「わからないプレゼンをした方が悪い」。この違いを理解するのに苦労しました。
異分野の人とコミュニケーションがうまく取れずさまざまな失敗を経験して、研究者から経営者の考えがわかるようになるまでは1、2年かかりました。
でも、目の前の人を巻き込めないなら、世界は変えられません。経営者として自分の会社を成長させるには、異分野とのつながりと相互理解、リスペクトがとても大切だと実感しています。
仁木 おっしゃるとおりですね。ディープコアでは「KERNEL HONGO」というインキュベーション施設を東大の近くで運営しています。メンバーは医療や都市工学、法律などの専門分野に詳しい人、エンジニアや起業経験者など、バックボーンの異なった人材で構成されています。
また東大にある10学部すべての学部のメンバーがいます。必然的な偶発で異分野とのコミュニケーションが生まれ、相互理解を生み出しやすい環境になっていると思います。
後続が続く「轍」をどれだけ作れるか
──続いて、Deep Techへの投資についてお聞きします。昨今の投資・資金調達環境について、どう感じていますか?
永田 私が現場で感じているのは、“金の卵”を支えるVCや投資家の数が圧倒的に足りていないことです。
今増えてきているのは、起業してPoC(概念実証)まで終わり、実際にビジネスのフェーズに入る段階で、ようやく投資家から資金調達ができるケースです。
しかし、その前の前の段階、研究開発が滞って先が見えない「死の谷」を伴走者として支え、共に乗り越えられるような投資家やハンズオン型VCの存在がもっと必要です。
ITやWeb系のスタートアップだと、広告戦略投資をするタイミングで大型の資金調達を実施するのが一般的ですが、Deep Tech・リアルテック領域では、ある程度ビジネスが見えてくると、マニュファクチャリング体制構築の資金が必要になってくるフェーズに差し掛かります。
例えば、宇宙開発系のスタートアップだと、プロトタイプを宇宙空間に送り込むのにワンショット50億くらいかかるわけです。
ただ、Deep Tech・リアルテック領域のこのフェーズで実際に投資対効果があるかは不透明なので、短期的なリターンにフォーカスしている日本の投資家は資金を投入しないというのが現状ですね。
──ただ、永田さんがリアルテックファンドを立ち上げたように、そこに資金を投入する投資家たちも一部で出てきているわけですよね。
高橋 そうですね。私が6年前に起業した時よりも、感覚値ですが資金調達環境は間違いなく良くなっていると感じます。
起業を検討している研究者も増えていますし、つながりのある大学の先生から「自分の研究で起業したい」といった相談を受ける機会も最近は多くなってきました。
こういった、将来Deep Techを盛り上げる起業家予備軍の人へのバックアップ体制を整えていかなければならないと感じています。
永田 「誰かができるなら、自分もできるかもしれない」。先人と同じ轍を進めば成功できる、と思える市場になっていかなければなりません。轍をどれだけ作れるかによって、これからDeep Tech領域が盛り上がるかどうかが決まると思います。
しかし、ことアカデミアに関しては地域格差がありすぎると感じます。唯一、東大は轍を作った人が大学に戻ってきて、次世代の成功を担うアントレプレナーに還元するエコシステムができています。
今後は第二、第三の東大のようなアカデミアを作っていくことが、日本のDeep Techのブレークスルーの肝になってくるでしょう。
高橋 「研究開発に投資する」こと自体が、社会に対して良いインパクトを与えるという価値観が広まってほしいですね。世界にまだない産業を作るきっかけに対して投資する、「未来のシーズを育てる」ことに価値を感じる投資家が増えると、良い循環が回っていくのではないでしょうか。
大学教授が起業できない問題
──日本のDeep Techが直面している問題のひとつに、大学教授が起業できない。「兼職禁止規定」に違反してしまうというルールがあります。
高橋 これは日本の大学の課題ですね。一般的に、教授が自分で起業すると大学に戻ってこれません。兼職禁止規定の範囲内で起業するには、自分はアドバイザーになって、代わりにやってくれる経営者を探すといった、回りくどいやり方をしなくてはなりません。
実は以前、文科大臣に物申したことがあるんですが……「今は大学がそれぞれ決めていることなので、大学に直接言ってくれ」と。
ただ、徳島大学では「起業した人を教授にする」という取り組みがされていたりもします。いずれにしろ、日本のアカデミックも兼職禁止規定の緩和をしていくべきだと思います。
永田 話を広げると、産学連携を実際にやったことがある人、成功させた経験がある人が圧倒的に少ないことが、日本の課題です。本来であれば、実績のある人を各大学に配置すべきだと思っています。
その点でOISTは、学部の垣根がないのが素晴らしいし、オープンイノベーションが生まれやすい環境ですよね。
今の時代、技術領域の壁はもはや関係ありません。実際にユーグレナでも生命科学以外の領域に投資しています。さまざまな角度から技術を組み合わせることにより、新しい価値が生まれると思っています。
Deep Techのエコシステムを作るには
──まさにOISTが提唱しているように、今後、日本でもDeep Techによるイノベーション創出のエコシステム構築が求められていくはずです。そのために何が必要ですか?
仁木 まずいえるのは、大学におけるダイバーシティの推進と文化の融合が必要でしょう。若くて優秀な海外の研究者が日本の大学に入りやすい環境を用意すること。日本の大学自体をもっとグローバルで魅力的なものにしていく必要があります。
日本のアカデミックを、内向きに閉じた価値観から解放し、次世代のアカデミアを目指していかなくてはいけません。その意味では、OISTはまさに先駆者だと思います。
高橋 大学の研究者で、実際に起業した人や将来的に起業したい人は増えてきていると感じます。一緒に共同で案件をこなしたり、横で連携したりと、研究者同士のコミュニティも生まれてきています。
コミュニティの中で成功が生まれると、「自分でもやってみよう」と思えるようになってくる。大学発のベンチャービジネスの成功モデルを1つずつ作ることが大切だと思います。
永田 やはり本質的な「アカデミア改革」をしていくべきだと思います。例えば、「MITはカッコいいのに、東工大はカッコ悪い」と見られているのにも疑問を感じますよね。まず作業着と白衣をモテるようにカッコよくすればだいぶ変わると思うんですよ(笑)。
実はこれも冗談ではなくて、リアルテックファンドがスタートアップに出資して、まず最初にすることが決まっているんです。それは「経営者」と「ホームページ」と「プロダクト」の3つをカッコよくすること。
実際、この3つが変わると、投資家が事業の将来性を理解し始めたり、人の採用が始まったりと急にビジネスが動き出すんです。突きつめると「人間の機微や欲求」をきちんと理解することが重要だということ。
「カッコいい」「面白そう」といった感性が大事で、課題の本質はこういうところから見えてくるのではと思っています。
パネルディスカッションの終了後はネットワーキングタイムとなり、来場者同士がそれぞれの立場から交流を深めたほか、OISTの研究室によるピッチなども行われるなど、日本のDeep Techを牽引する人々がつながるきっかけとしても盛況を博した。
今後、Deep Techへの興味関心が高まっていくにつれて、次世代を担う人材を輩出するアカデミアの重要性はますます強くなっていく。
アカデミック✕ビジネスが相互にシンクし、真に社会を革新するDeep Techのエコシステムが覚醒することに期待していきたい。
(編集:呉琢磨 取材:古田島大介 撮影:Atsuko Tanaka デザイン:國弘朋佳)