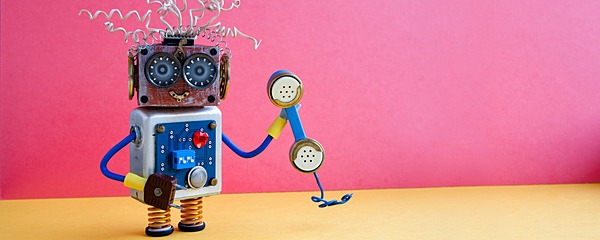
AIツール導入で泣き出した中年社員
昨年、ヒアセイ・システムズの創業者クララ・シーは、保険関係の取引先への定期訪問に立ち会っていた。ヒアセイは15万人以上のファイナンシャルアドバイザーや保険アドバイザーに対し、顧客との関係や作業工程の改善のための人工知能(AI)を使ったツールを提供している。
この時の訪問先は従業員4人の小さな会社で、うち2人は保険金の滞納と契約更新に関する連絡や手続きだけを担当していた。つまり折り返しの連絡などまず期待できない電話をひたすらかけ続けるといった、非生産的で手間と時間ばかりかかるやり方で業務を進めていたわけだ。
そこでヒアセイ側は、人力に頼った顧客への連絡作業をデジタル化するためのAIを使った新しいツールを提案した。1人1人に電話をかけるのではなく、何十人もの顧客に支払期限を過ぎた旨をメールで一斉通知するというツールだ。
使い方を説明していると、中年の男性アドバイザーがいきなり泣き始めた。
AIツールのせいで自分の仕事がなくなってしまうと思われたのではないか──。シーたちは初め、そう懸念した。というのも、それが機械学習を使ったツールの導入を前にした労働者のよくある反応だったからだ。
ところがこの時の涙の理由は違った。「これはすごい」と男性は言ったという。「20年もの間、私は時間を無駄にして何をやってきたんだろうか」
雇用が奪われる一方、新たな創出も
機械学習(それがロボットによる作業の自動化であれ、高度なデータ分析であれ、AIであれ)は今後、間違いなく職場のありようを変えていく。それによりいくつの職が失われ、いくつの新たな職が生み出されるかについてはさまざまな推測がなされている。
世界経済フォーラムの報告書「未来の仕事2018年版」によれば、2025年までに総労働時間の5割以上に相当する仕事を機械がこなすようになるという。
自動化を背景に2022年までにフルタイム従業員の一部が削減されると予測する企業は全体の50%近くに上り、従業員が生産性向上の新たな役割を担えるように教育しようと考えていた企業は38%だった。
また、コンサルティング会社PwCの最近の研究では、英国では今後20年間に700万の既存の雇用が機械に奪われる一方で、新たに720万の雇用が創出されるという。
人間と機械が生産的に共存する必要のある職場への移行は、ビジネスを生み出すことも壊すこともあるだろう。
経営者は将来に向けた計画を立てる際、機械学習が生産性やスキル、従業員の士気や社風まであらゆる面におよぼすインパクトを考慮しなければならなくなるだろう。また、人間と同じくらいの数の知的なマシンが稼働しているかもしれない会社を、どのように率いていくべきか学ばなければならない。
「AIは(今)われわれ人間がやっている既存の作業をよりよく、より効率的に、より安くやってくれるだけではない。以前なら考えもしなかったようなことをする助けになる可能性も秘めている」と、コンサルタント会社エンビジョナーズのデイブ・コプリン最高経営責任者(CEO)は言う。
「だが、人間の側が何とか使いこなすすべを理解しなければ、AIがもたらす可能性を実際より低く捉えてしまう恐れもある」
最良の道は「人間参加型」関係構築
AIの導入が進めば進むほど、ロボット的思考をしない人材を求める企業が増えてくることはわかっている。
「テクノロジーと競合するのではなく、相補うようなスキルを伸ばすように努めなくてはならない」とコプリンは言う。
「エクセルより早く計算できるようになろうとか、グーグルよりたくさんの事物を覚えようなどとする人はいないはずだ。その代わりに私たちが考えなければならないのは、今後数十年はコンピューターが真似できないような、極めて人間らしいスキルとは何だろうということだ」
AIが人間よりはるかにうまくやれるタスクはたくさんあるが、その仕事を解釈し、その結果を戦略的で共感的で創造的な方法で応用するのは人間の仕事だ。
ヒアセイのシーに言わせれば、機械は人間にとって利用可能なリソースの1つに過ぎない点、そして人間は機械の関係を真に有益なものにするためのスキルを備えている点を理解することがカギになる。「大事なのは偏見にとらわれず、適切なタスクを機械に任せられることだ」とシーは話す。
そのための最良の道は、AI業界で「人間参加型(Human-in-the-loop)」と呼ばれる関係を構築することだ。つまりアルゴリズムには自分の仕事をやらせ、人間はそれを監督し、さらに改良していくという関係だ。
「機械学習だけで100%の正答を出すのは難しい」とシーは言う。だが、人間参加型のプロセスを実施することで「(最初から)完璧である必要はなくなる。人間がプロセスに介入すれば、アルゴリズムは学習する」
人間側の「恐れ」をどう払拭するか
例として挙げたのが、ヒアセイが先ごろ発表したアドバイザーや保険代理店向けの新サービスだ。アルゴリズムが顧客への返信を自動生成するというサービスだが、導入当初はとんでもない文案が出てくることがあった。
たとえば、顧客にハッピーバースデーを言うようにアドバイザーに提案し、顧客がそれに対して返事をすると「お気遣いありがとうございます。それはいいですね!」と返すといった具合だ。
顧客はアドバイザーが上の空になっているか、ちょっとおかしくなってしまったのかと思ったという(ちなみにグーグルも電子メールの返信を自動作成するサービスを始めたが、この数カ月というもの、もっとひどい文面を作る失敗を繰り返している)。
ヒアセイのサービスの場合、スタッフの介入と機械学習の双方によりアルゴリズムが改善されたことで、メッセージのあらがなくなって、もっと適切な返信を生成できるようになったという。
さて、こうした人間と機械の共生を実現する唯一の方法は、新たな関係に恐れを抱いたまま足を踏み入れないことだ。
恐怖は「意志決定の際の感情としては最悪のもの」だと、ナラティブ・サイエンスの共同創業者であるクリスティアン・ハモンドは言う。同社は、データや統計から自然言語を使った報告書をAIで生成するサービスを展開している。
相互作用が恐れによって促進される場合、テクノロジーばかりに目が行って、事業にとってのテクノロジーの活用の必要性がおろそかになりがちだ。
ハモンドは、データアーキテクトと事業戦略の担当者からなるチームを作ることを勧める。「AIの専門家に、もっと幅広いイニシアティブに参加してもらうのだ。目指す企業の姿、そしてAIがビジネスを形作るすべについて論じるようなイニシアティブに」
機械への信頼を築くための工夫
もし人間が機械を敵ではなくパートナーとして見なすようになっていくとすれば、そこには機械の仕事ぶりへの信頼がなければならない。
前出のコプリンは従業員の信頼を得るため、AIを段階的に導入していく方法を勧める。「アルゴリズムを職務の一部分に限って取り入れて、アルゴリズムの働きぶりを見るとともに、期待通りの結果が出るという信頼を築くための時間を人間に与えるのだ」
コプリンは、アルゴリズムベースのテーブル予約システムを導入した大手レストランチェーンを例に挙げた。
各店舗のマネジャーは当初、クラウド上のアルゴリズムが自分たちより上手にテーブルの予約を管理できるなど信じられずにいた。彼らの懸念を和らげるため、会社はアルゴリズムで管理するテーブルを当初はほんの1部に抑え、もしマネジャーがその結果に満足すれば、テーブルの数を増やすことにしたのだ。
予約可能なテーブルのわずか10%からスタートしたところ、マネジャーたちはすぐにアルゴリズムがいい仕事をするばかりか、そのおかげで他のもっと大事な仕事に時間を回せることに気がついた。
「新たなベビーシッターを雇う時と同じだ」
スティーブン・アフォードは、金融機関のマネーロンダリング監視システム向けにAIを使った照合サービスを提供しているトゥルリユーの共同創業者兼CEOだ。
マネーロンダリング防止のための監視は銀行セキュリティの重要な分野であり、従来は人の手で行われてきた。
ところがコンピューターの性能向上と生み出されるデジタルデータの量が膨大になったことで、もはや人手では対応しきれなくなったばかりか、犯罪組織にも力負けするようになってしまった。
今ではトゥルリユーなどが開発したアルゴリズムが、人間にはとてもさばききれない大量の決済を調べている。詐欺が疑われる案件を見つけたり、怪しい個人をブロックしたりする方法をアルゴリズムに仕込んだのは人間だ。
詐欺的な取引を特定するといった難しい問題を扱うに際して、トゥルリユーのスタッフが作ったアルゴリズムは、意志決定や怪しい人物を警告する際にいかなるバイアスも示さないようなものでなければならなかった。
「AIを信頼できるようになるということは、新たなベビーシッターを雇う時と同じだ」とアフォードは言う。
「まず最初は、ベビーモニターのカメラを通して何をしているか様子を見る。だがしばらくすると仕事ぶりに対する信頼が高まり、気楽に構えることができるようになっていく」
「創造性の触媒」になる可能性
企業内のAIが成長していけば、最終的には重役たちが直視したくないような実存的な問いが立ち上がってくる。将来、実際に機械と一緒に働くのは社員の中のどのくらいの人数なのか──。
現実問題として、変化は避けられない。だから企業は、自動化したほうがよさそうな機能的で反復的な作業を担当している人々のために、確実にソフトランディングできるように努める必要がある。
彼らに再研修を受けさせたりスキルアップさせて、その組織としての知識や経験を最大限活かすことを目指す企業もあるかも知れない。一方で、自動化によってどうしても職を追われる人も出てくる。たとえばフォックスコンでは2016年、6万人の労働者がロボットに取って代わられた。
だが長い目で見た場合、業務の自動化がもたらす大量失業への恐怖は大げさだったということになる可能性はあるのだろうか。
そもそも、次世代の労働者(「アレクサ世代」と言ってもいいだろう)は、機械と一緒に暮らし、機械から学ぶことに慣れているはずだ。そうした労働者の働くやる気をかき立てるのは、従来型のインセンティブではなく経験や自由や創造性にあることはすでに示されつつある。
「うちの祖父母のうち2人は工場で働いていたが、祖父は絵を描くのが大好きだった」とトゥルリユーのアフォードは言う。「仕事は人の創造性を潰すのではなく、うまく活用すべきではないのだろうか」
つまるところ、機械はみんなが待っていた創造性の触媒となるかもしれないのだ。
原文はこちら(英語)。
(執筆:Matthew Yeomans/Founder, Sustainly、翻訳:村井裕美、写真:Besjunior/iStock)
©2018 Mansueto Ventures LLC; Distributed by Tribune Content Agency, LLC
This article was translated and edited by NewsPicks in conjunction with IBM.

