
AI時代におけるデータサイエンスの根付かせ方、生かし方
NEC | NewsPicks Brand Design
2018/9/25
今春、データサイエンス界がざわついた。2013年の初代「データサイエンティスト・オブ・ザ・イヤー」に選出された河本薫氏が、在籍していた大阪ガスを退社するというのだ。データ活用の先進企業といわれる大阪ガスを辞し、新天地として選んだのは滋賀大学。2017年4月に日本初の「データサイエンス学部」を新設した同大学の教授として、データサイエンティストの育成に心血をそそぐ道を選んだ。
企業での実務経験者が教育に携わる意義は、大きい。というのも、データサイエンス、AIは机上で終わらせる学問ではなく、ビジネスで使ってこそ意味がある。その思いを強く持っているのは、NECで最も多くAI活用のプロジェクトに携わり、「人工知能システムのプロジェクトがわかる本」を上梓している本橋洋介氏だ。NECは、いかにAIをビジネスで使えるかを念頭にAIの開発を続け、提供している。
データサイエンスのスペシャリスト同士が、企業においてデータ活用文化を浸透させる方法論、慢性的に不足している専門人材の育成について意見を交わした。
企業での実務経験者が教育に携わる意義は、大きい。というのも、データサイエンス、AIは机上で終わらせる学問ではなく、ビジネスで使ってこそ意味がある。その思いを強く持っているのは、NECで最も多くAI活用のプロジェクトに携わり、「人工知能システムのプロジェクトがわかる本」を上梓している本橋洋介氏だ。NECは、いかにAIをビジネスで使えるかを念頭にAIの開発を続け、提供している。
データサイエンスのスペシャリスト同士が、企業においてデータ活用文化を浸透させる方法論、慢性的に不足している専門人材の育成について意見を交わした。
企業との距離が近い学問
──この度の転身、かなり反響がありました。どういう経緯で決断されたのですか。
河本 2011年から大阪ガスのデータ分析専門チームを引っ張る立場になって、7年間。自分で言うのもなんですが、それなりに結果が出せたと考えています。
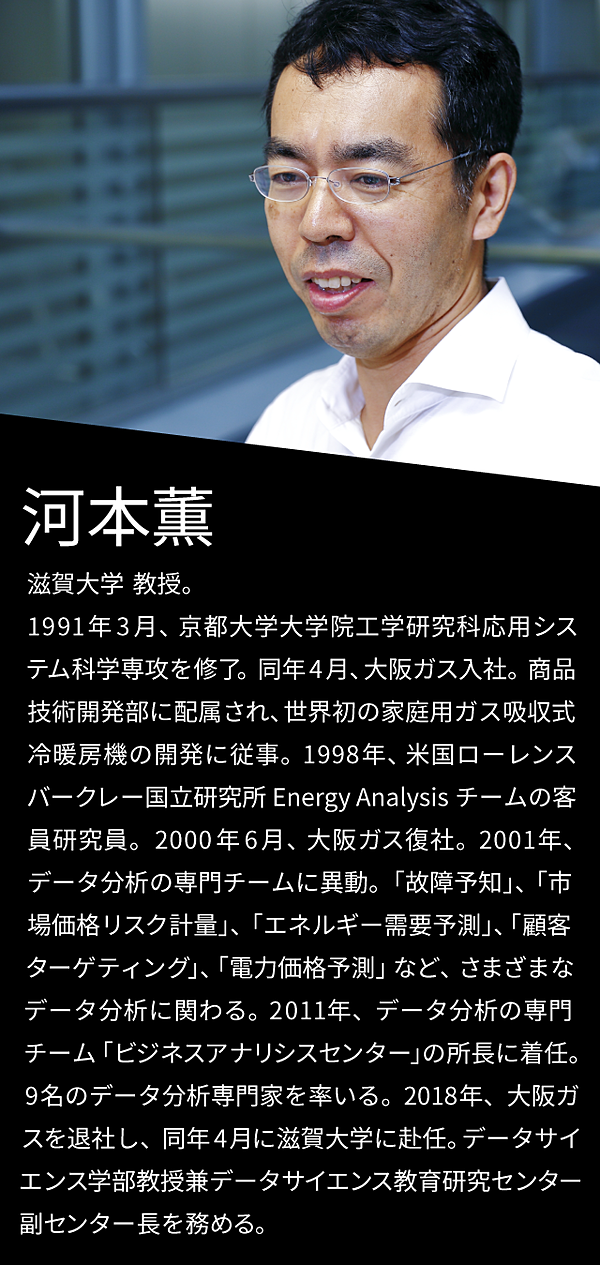
社内でのデータ活用を定着させ、チームが認められ、後継者も育ってきた。自他ともに、そろそろバトンを渡す時期だという意識を持っていたところ、ちょうど滋賀大学からのお誘いがありました。実は、若かりし頃から教育への関心があって。いいタイミングが重なったし、とても自然な人生の流れだと感じて決意しました。
──滋賀大学に移籍してから、ちょうど半年になります。まったく別の世界ではないかと思いますが、想像していた通りですか。
河本 別世界に隠居しました、というイメージと全然違っていて、今までの20数年間の事業会社でのビジネス生活で養ったコミュニケーション力やビジネス感覚が、継続的に役に立っています。
移ってみて期待以上だったのは、教鞭を執るだけではなく、いろんな企業との共同研究ができることです。企業に協力してもらって、学生もジョインするような「ビジネス×教育」の場を作れています。直接ビジネスをしているわけではないですが、ビジネスとの関わりあいを続けているんですよ。
本橋 大学だからこそ、より企業とのつながりができるような気がしています。私たちも河本先生にアドバイスを求める機会があるのですが、今までは「なぜ大阪ガスなんだ」という説明をお客様や社内に用意する必要があった。でも、大学の先生なら自然だから、企業としては関わりやすいんです。
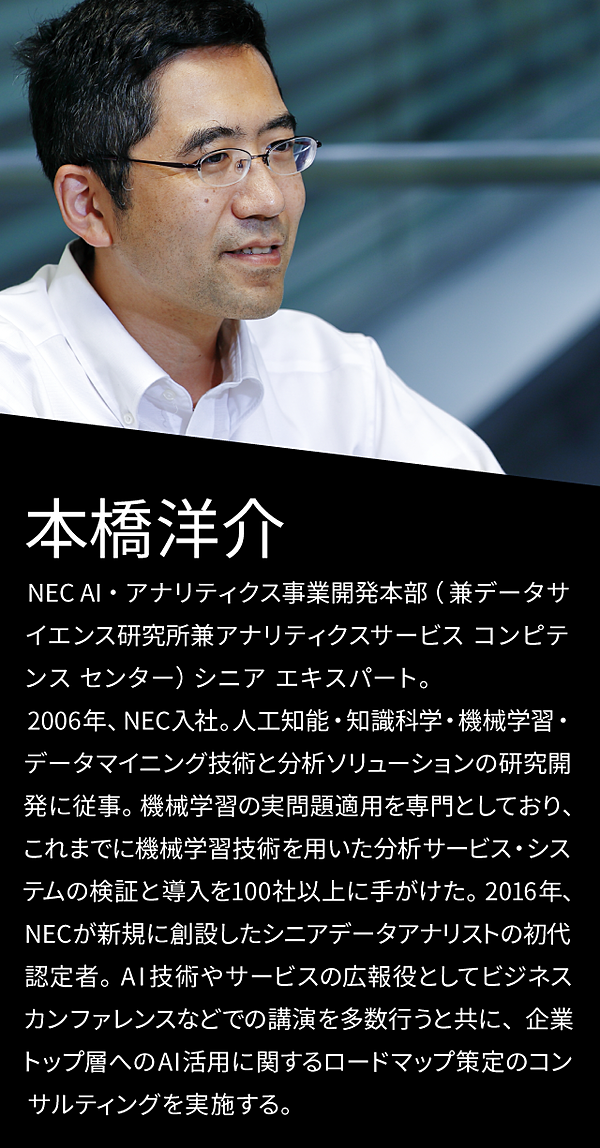
河本 それは確かにあります。企業から見たらニュートラルな立場なので。前職よりも多くの企業から声がかかるし、いろんな話を深くしてくれますよ。前職時代は、自分の知見をよりオープンに伝えたくても、立場上難しい状況もありました。
それから、大学の先生には企業経験がない人も多いから、企業の人たちとの接点が細いんですよね。そこに私が教育側で入って太くできるのは、学生にとっても、大学にとっても、企業にとってもいいことじゃないですか。
大学1年生からインターンを引き受けてくれる企業もあって。いろんな切り口で企業と大学がうまく繋がることで、お互いハッピーになる機会って結構あるんです。
企業でデータサイエンスを定着させるには
──河本さんは、大阪ガスでデータサイエンスをどのように浸透させていったのですか。企業で定着させるコツ、教えてください。
河本 企業といっても星の数ほどありますので一概には言えませんが、大阪ガスは100年以上続くコテコテの日本企業。そして、他の企業と同じように、やっぱり現場が強い。
「ヘルメットのおっちゃん」が強いんですよ。その中でデータサイエンスという新しい概念を活用していくのは、水と油のようなところもあるわけです。すると、ものすごくフラストレーションが溜まる日々が続くんです。なんで受け入れてもらえないのかと。
──それでもうまくいった。どうしてでしょうか。
河本 大阪ガスで浸透したのは、企業風土に2つの特徴があったからではと思います。1つは、超ボトムアップ。担当レベルの裁量がかなり大きい。だから、ビジネスアナリシスセンターは、どんな行動をするのか誰かに言われて行動するんじゃなくて、自分で考えて自分で行動できた。計画ガチガチじゃなくて、それなりの裁量を持って進むことができました。
もう1つの特徴が大阪らしくて、「儲かってなんぼ」というのが強いんです。データ分析をして、説明する。でも、それでは評価されなくて「ほな、お前、これでいくら儲かるん?」って言われたら答えに窮して、「お前、アホか」って感じになる。
そういうカルチャーの中で、無意識のうちにカネになるまで、最後までやり遂げる意識が芽生えてきたんでしょうね。
結局、言葉ではなく成果を出さないと分かってくれないんです。現場へ4回も5回も行って、データ分析を現場に導入して、それで品質がすごく上がった、大幅にコストダウンできたとなると、誰が見ても「すごいやん!」となる。
そういう案件が増えてきたら理屈を言わなくても、今まで反対していた人間が急に「もっとやれよ」という風になってくる。そんな感じのステップですね。
あと、最初の頃は全然信用されていなくても、業務が効率化できたり、新たなアイデアが生まれるきっかけをデータ活用を通じて得たり、業務が変わるところまでやるから「河本さんのところは信用できる」となる。それをすごく大切にしてきましたね。信頼されることのありがたさを感じて、このレピュテーションを失いたくないという意識も強かったです。

──本橋さんのところへは、AIを使いたい、データを生かしたいという企業からの問い合わせが多いと思いますが、今の企業における進捗状況について教えてください。
本橋 日本全体では、データ分析専用組織がある企業は数パーセントではないでしょうか。ただ今はAIが流行っていて、流行っているから経営者は絶対に認識しているはず。そして若手なんかに「お前がミスターAIになれ」みたいな声を掛け始めています。
河本 ミスターAIですか(笑)。
本橋 若い人で意欲や関心がある方にとっては喜ばしいことで、勉強したり、取り組み始めたりしている。IT部門の中に、AIについて詳しい人が現れているところです。
ただ、AIもデータサイエンスも時間がかかるもので、魔法ではない。データがすぐ結果につながってお金になることはまずありません。その辺を誤解して、成果と取り組みの関係にギャップがある会社もあります。例えば2年かけてデータを整備するぐらいの、もう少しゆっくり取り組めばよいのにと思うことも結構あります。
──企業はAIやデータサイエンスですぐに結果を求めがちですか。
本橋 そうですね。それは丁寧に説明をして、一緒にやらせていただいています。「ビッグデータ」という言葉ができて7年ぐらいでしょうか。以来、去年あたりの「デジタルトランスフォーメーション」まで、言葉は違えど似たようなコンセプトが続いています。ずっと辛抱強く取り組んでいる会社が出てきているのも確かです。

企業がデータサイエンスに取り組む本質
──大阪ガスのビジネスアナリシスチームは、2011年からでしたか。
河本 そうですね。ただその前から、20年ほど前から取り組んでいたんです。
本橋 その経験は先生の本にも書かれていますよね。それを読んで、すごく「企業人らしいサイエンティスト」で素敵だなと思ったものです。
率直に言って、マネージメント寄りの人が好きな内容。データサイエンスの本や講演って、テクノロジー寄りのものが多いんですよね。Pythonでディープラーニング、みたいな。そうではなくて組織論や仕事の進め方の話は、発刊当時は今以上に稀有でした。仕事でデータを使うとは、そういうことではない、本質ではないという解説です。
河本 今、メディアの影響もあって、経営者の方々の頭の中にAIやIoTって言葉が強烈にこびりついている。経営者は「AIをやろう」と言うようになって、いつの間にかそれ自体が目的になってしまっていることがありますよね。それから、ないものねだりが多いんですよ。
本橋 ないものねだり、ですか。
河本 データがあるから何かできるのでは、あるいは他の会社もやってるから何かやれとか。そういうのは、ないものねだりなんですよ。不毛な気がして。データも分析力も必要ですけど、それも手段です。
では、何をすべきかと言えば、そのデータ分析力で成果を出す機会を作ること。さらにその源泉は何なのか考えたら、真剣な意思決定なんですよ。真剣に業務改革しよう、真剣に問題解決しよう、真剣にいい選択をしよう、とかね。
真剣に意思決定をよりよくすることを考えていく風土があれば、そこにはおのずと「勘と経験」だけではなくて、データを生かそうってなるんです。
その真剣さが少し弱い企業もあって、そういうところは、なかなかデータ活用が浸透しない。極端なことをいうと、経営危機に直面している会社ほど、当然真剣なわけですから入っていくんです。
経営の危機感が弱くて、現状のいろんな意思決定に対する真剣な思いが緩いと、そこにデータ分析を持っていっても最後は「まあ、それはわかるけど後回し」って感じになるんです。
本橋 そうですよね。今までも勘で何となく意思決定できていたものを、「数値がこうだから」と意思決定するようになるのが変革で、そうなるかどうか。結果の半分ぐらいは、分析を見なくても定性的にわかっていますよね。
例えば、高年齢は病気になりやすい、というのは当たり前ですよね。では、その高齢者とは何歳以上なのかを数字で出す。数字で出すことに意味を感じるかどうかだと思いますが、そこは受け手の気持ち次第ですね。
河本 そうですね。
本橋 そのほうが公平だったり楽だったりする感覚を身に着けると、よいスパイラルに回ると思います。人間が考え込む量も減って、楽なんですけどね。
全員が「研究者」になるわけではない
──先生は、大学教育でデータサイエンティストを育てるのに、何が大切だと思って教えていますか。
河本 データサイエンスの基礎となる「足腰」を鍛えること。まずは線形代数や解析学などの数学や、プログラミング言語をしっかりと勉強させています。これが、社会人になってからでは忙しいから勉強できなくて、とりあえず使うための道具だけ勉強することになるんですが、大学生だからこそ、足腰を鍛えておく。
教えるにあたって、大切にしているのは、勉強して何のためになるのかという、「出口」も見せてあげること。
そのために取り組んでいるのが、いろんな企業でデータ分析をしている人に来てもらって、学生に話をしてもらっています。すると、学生からの質問も、たくさん出るんですよ。
仕事の進め方とか、会社の中でのデータの受け止められ方とか。このデータサイエンス学部を卒業した後、どんな仕事が待っているか強い興味を持っていて、そのために逆算したら、こういう勉強が必要だという意識を付けてもらうために行っています。
近々始めるのが、データ分析の全体感を体験してもらうことです。専門的な知識をいっぱい勉強していないと、ゴールに行き着かないって思いすぎるわけですよ。あまりそこに壁を感じすぎると、全体のストーリーが見えなくなるんで。
簡単でいいから自分で問題意識を持ってデータを見て、どこに問題があるか発見して、解決する。全体のプロセスを経験させるような、比較的簡単なお題を大学1年生の時点で提供してみようと思っているんです。
本橋 線形代数や統計は、一度応用を経験してからのほうが、間違いなく学ぶモチベーションになるでしょうね。例えば、なぜ行列を使うのかは、本当に大人にならないとわからないので。
河本 そうそう。なんで行列を学ばなあかんねんって。
本橋 ほとんど全てのデータ分析は、Excelでできる。でも、Excelだと一定のレベル以上になると線形代数などの知識がないとできないんですよね。今は便利なツールがあって、ボタンをポンで結果が手に入る。だけど、仕事にしていくとブラックボックスじゃ駄目で、中の挙動を理解したり、その結果を説明できたりしないといけないんです。
だから先に1回、ブラックボックスでもいいから、使えるんだ、役に立つんだなって知ってから、それからの勉強がいいと思います。
──ベンダー側とユーザ側でどのようにデータサイエンスの人材育成をしていけばいいのですか。
本橋 NECの中の人材育成だと、まず1つにAIの企画ができる人材の育成です。「企画」とはお客様の会社の中でAIの提供分野は何かを検討することで、なんでAIが必要なのかから一緒に考えます。そのために、NECとしては引き出しが多いデータサイエンティストを育てています。
次に、AIの実行やシステム実装ができる人材の育成の話をします。
ITベンダーは短距離走の選手の瞬発力のように決められた期間で結果を出すことが求められます。そのためにさまざまな業種・業務の事例や手法を勉強するような教育プログラムや自主的な共有の仕組みを提供しています。
また、自主的に学びたい人のために、NECグループの人間なら誰でも触れるAI(機械学習)ソフトウェアと練習用データがある環境を用意して、自ら自由に学習できる仕掛けを作っています。
NECはシステムエンジニアが多く、そういった人は手に職をつけたくなるものです。2500人くらいがその環境を使って勉強しています。そして、いまNEC内のデータサイエンティストの育成ノウハウをお客様に外販できるように進めています。
河本 会社によって、全然違う。大阪ガスでは、全社員向けにデータ分析の必要性をわかってもらうための研修はありました。平均値と中央値の違いとか、そんなレベルの話です。
でも、専門チームのメンバーにどうやって難しい分析方法を教えるかというと、ほぼ独学ですね。それなりに優秀な人が入ってきて、それに甘えられた良さはありました。
ただ、それで一度失敗しました。修士卒の優秀な学生が分析チームに配属されたのですが、大学院生の気分がそのまま継続されちゃったんです。大学院時代も、会社に入ってからもやることはデータ分析で、何も変わらない。
でも、今までは授業料を払っていて、これからは給料をもらっているという違いが意識できないようになってしまって。これは最初の段階で陥ると、根が深いんですよ。だから、そこだけはものすごくケアして、現場に使って実際に業務改革が起こるまでが仕事だと、肝に銘ずるような仕事を最初に与えるようにしていました。
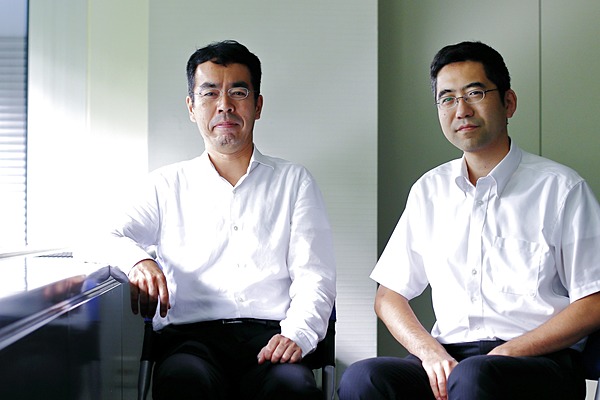
──新設から間もない滋賀大学では、まだ卒業生がいません。どういった活躍が期待されますか。
河本 最近、データサイエンス学部を卒業する学生の出口を作ったんですよ。大きく3つあって、「研究者」、それからNECで多く活躍するような「職業データサイエンティスト」。
そして「データサイエンスに明るいビジネスパーソン」。
3つ目のカテゴリーの人たちのキャリアは、あくまでもビジネスをする人です。
──マーケティングかもしれないし、セールスかもしれないけど、データサイエンスの素養がある人ですね。
河本 そう。そして、企業からの需要は、3つ目も大きいんです。一方、学生の中には、データサイエンス学部に入ってみたけどデータ分析はそこまで得意じゃないとか、データ分析は得意だけどでも人生をずっとデータ分析だけに捧げるのではなくビジネスにも携わってみたいとか、そういった学生もいる。でも、現在は、学生の能力や価値観の多様性、それから企業の求める人材の多様性が整理されていない。
世の中のイメージもそうじゃないですか。「職業データサイエンティスト」っていうキャリアだけになっていて。そうではなく、「データサイエンスに明るいビジネスパーソン」もポジティブな出口として学生に見せるし、企業のほうにも認識してもらいたい。
そういう学生と企業の線を結んで、お互いハッピーなマッチングができるようにしたい。でないと、入学したら全員が職業データサイエンティストになるための学部だとなると、学生も企業も不幸になるかなって気がして。
本橋 素晴らしいビジョンで取り組まれていますね。データサイエンスは、あらゆる場面で求められる素養で、しかもビジネスで生かすことを前提に教育されているところが、まさに河本先生らしいし、今後のあるべき姿だと思うんです。
NECでも、AIはビジネスで使えてこそだという大前提を大切にしていますし、AIが結果に至った理由を説明できるようにしたり、データサイエンティストでないと導き出せなかったことを自動化したり、そういうビジネスのど真ん中で使えるAIを作っています。
とはいえ、やはり使う人の育成というのは欠かせません。その意味で、今日はお客様に、AIの使い手としての心構えをお伝えできるヒントを得られました。
河本 本当に社会で活躍できる人材を輩出するには、やはりビジネスの現場の声を学生の前で語ってもらう必要があります。ビジネスの最前線でお客様に向き合っている本橋さんは貴重な教材です(笑)。
(取材・編集:木村剛士、構成:加藤学宏、撮影:竹井晴清)

本対談で登場した滋賀大学の河本氏とNECの本橋氏は、NEC主催イベント「C&Cユーザーフォーラム&iEXPO2018」に登壇し、トークセッション「AIが変革する未来~先進事例と組織づくり~」を行います。AIの最新動向や、AI時代の組織の在り方、人材育成の考え方を紹介します。日時は11/9(金)16:15~17:45です。無料で参加できます(事前登録制)ので、ぜひご参加ください。詳細はこちらです。
NEC | NewsPicks Brand Design


