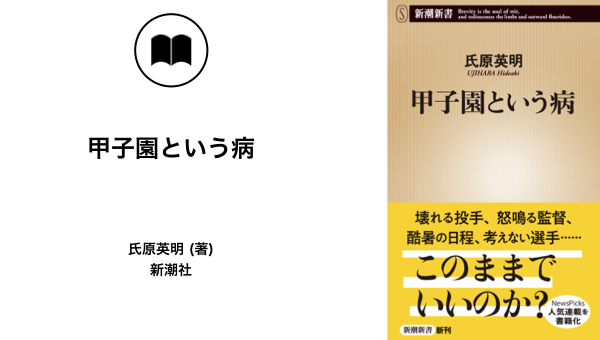「甲子園病」の処方箋。酷使されるエースたちを守るために
2018/9/4
9月3日から第12回BFA U18アジア選手権が開催されている。
今大会のU18日本代表は夏の甲子園で活躍した選手を中心にメンバーが構成されているが、彼らの活躍ぶりとともに注目されているのが、初めて導入される球数制限制度だ(詳細は
侍ジャパンの公式HP参照)。
100回目を迎えたこの夏の甲子園では、同メンバーでもある金足農業の吉田輝星が6試合で881球を投じるなど、一部で甲子園の球数が問題視された。橋下徹元大阪市長をはじめ、作家の乙武洋匡さんらが「球数制限をすべきだ」との論調を展開し、甲子園における大会制度の在り方が問われた。
本連載でもたびたび、投手の登板過多について取り上げてきたが、果たして、今後の高校野球は球児の健康問題という100回の歴史で噴出した課題に対して、どう立ち向かうべきなのだろうか。この夏の甲子園での出来事を振り返りながら、検証したいと思う。
「エース依存」に陥る理由
そもそも、なぜ、球数制限は必要なのか。
スポーツ科学的な観点に立てば、おそらく、制度化は必然の流れだろう。米国では、若年層の投手が相次いで故障することから、米国野球協会とMLB(メジャーリーグベースボール)は投球制限に関するガイドライン「PITCH SMART」を策定した。そのガイドラインについては、以前の連載でも取り上げているので、そちらを参照してほしい。
米国にならっての制度化には賛成なのだが、甲子園における登板過多などの健康問題において、忘れ去られているもう一つの問題について提起したい。
それは、高校野球の中にある「勝利至上主義」や「甲子園至上主義」が引き起こす健康問題についてだ。
試合が始まれば勝利を目指すのは当たり前のことだが、勝利至上主義とは、勝利でしか得られるものはない、敗北に価値はないと考える主義・主張のことだ。甲子園至上主義とは、甲子園に出場しなければ、甲子園で勝たなければ意味がないと考えることだ。
「投手の登板過多問題は、投球数をルールで縛れば解決することができる」ことは確かにわかるが、勝利至上主義や甲子園至上主義が高校球児の健康問題に足かせとなっているように感じる。
先述したように、この夏の甲子園で金足農の吉田は6試合で881球を投じた。秋田県大会から甲子園決勝戦の5回まですべてのイニングを1人で投げ続け、たった1カ月余りの間に1500球を投げた。プロ野球の先発ローテーション投手の年間投球数は3000球を超えると多いとされているから、この数字の異常性がわかるだろう。
吉田のように地区大会からほぼ1人の投手が投げてきたケースは他にもある。2回戦の星稜―済美戦は延長13回タイブレークまでもつれ、済美はエースの山口直哉が184球の完投をしたのである。今大会における1試合での最多の球数であり、明らかに投げすぎだ。
9回9失点の山口を延長に入っても続投させた、済美・中矢太監督の「エース依存」には疑問を抱かざるを得ない。
中矢監督は試合後、山口を続投させた理由をこう語っている。
「山口の交代を考えてはいたんですけど、こういう試合展開のなかで、ここで代えてしまうと監督は勝負を諦めたのかという空気が生まれてしまう。山口がずっと投げてきたチームですから、続投させました」
もっともらしい言葉のように聞こえるが、選手の健康面を後回しにした指揮官の起用法は到底納得できるものではない。
どのような試合展開になろうとも、起用にはリスクが伴う。だが、ここで肝になるのはそのリスクを誰が背負うかだ。甲子園という大舞台で地区大会では登板していない投手を起用するのは敗北のリスクが高まるが、中矢監督はそのリスクを避けて健康面のリスクをエースに背負わせたのである。
そもそも、エース依存の起用を地区大会からしてきたから招いたことなのだ。
実戦経験不足の2番手投手
「本当は県大会の序盤で投げるはずだったんですけど、大差で勝てる相手にコールドで勝てず、結局、山口が投げる展開になってしまいました」
そう語っていたのは、準々決勝の報徳学園戦でこの夏初登板を果たした済美の背番号「5」池内優一主将だ。旧チームから投手もしていた彼は、2番手投手として山口を支えるはずだったが、愛媛大会では接戦が多く、自分の出番がなかったと説明した。
済美にしても、おそらく、吉田の金足農にしても、北代の高知商にしても、エースの多投を招いたのは同じ理由だろう。接戦を展開してきた中で、2番手以降の投手起用ができなかった。
池内は準々決勝で先発した際144キロのストレートを投げ込み、フォークとのコンビネーションでうまくゲームをつくった。決勝戦で吉田の後を受け継いで登板した金足農の打川和輝も140キロ近いボールを投じ、大阪桐蔭打線を終盤3イニング1失点に抑えている。
投手がいないのではなく、指揮官自身がリスクを恐れて、2番手投手の登板機会をつくってこなかったことに他ならない。
中矢監督の言葉が象徴的だ。
「愛媛県大会で(控え投手の)池内を出してこなかったのは、負けられない戦いの中で山口の安定感を優先していました」
この現実こそが、球数制限を導入しなければいけない理由だ。
敗北するかもしれないというリスクを指導者自身が背負うことができず、選手の健康面を後回しにして、中矢監督風にいえば「勝つ姿勢を見せる」ことに固執する。「エースへの信頼」を語っているようで、勝つことでしか得られるものが何もないという発想に陥っている。
指導者の意識がこの程度だから、ルールで縛らなければいけないのだ。
勝てば勝つほど登板過多に
もっとも、今大会で登板過多を避けようとしなかった象徴的指導者として中矢監督らを挙げたが、あくまで勝ち上がったから明るみに出ただけであって、彼らが特別だとは思わない。
以下は今大会の通算投球数と1試合の最多投球数の上位5人だ。
<大会通算投球数>
1位 881球 吉田(金足農)準優勝(6試合)
2位 607球 山口(済美) ベスト4(5試合)
3位 512球 柿木(大阪桐蔭)優勝(6試合)
4位 489球 鶴田(下関国際)ベスト8(4試合)
5位 449球 河村(日大三)ベスト4(5試合)
<1試合最多投球数>
1位 184球 山口(済美)2回戦対星稜 ※延長13回
2位 179球 西(創志学園)2回戦対下関国際
3位 176球 木村(奈良大付)3回戦対日大三
4位 164球 吉田(金足農)3回戦対横浜
5位 157球 吉田(金足農)1回戦対鹿児島実
大会通算投球数は勝ち上がったチームのエースないし、中心的人物であることがわかるだろう。1回戦から登場したチームばかりで、勝ち上がって投球数がかさんだ。
一方、大会中にガッツポーズを控えるように審判から注意を受けたことで騒ぎになった創志学園のエース・西純矢は2回戦の下関国際戦で、9イニングでは大会最多の179球を投じている。勝ち上がっていれば、通算投球数がどうなっていたか。2試合で308球を投げている奈良大付の木村にも同じことがいえる。
つまり、高校野球界のいまの風潮からすれば、どこが勝ち上がっても登板過多問題は噴出していたということである。
「勝利至上主義」「甲子園至上主義」が根底にあり、指導者がそのマインドに汚染されているのだ。
最大の問題は年間スケジュール
では、なぜ、いまの高校野球界にはそうしたマインドが植え付けられているのか。
その理由のひとつに高校野球の年間スケジュールの問題があると思う。
夏の甲子園大会中に、翌春のセンバツ出場権を懸けた戦いが始まっている地区があり、さらには、その秋季大会は多くの地区で負けることが許されないトーナメント制で行われている。
指導者や高校球児たちが休まる時期がどこにあるのか。
勝敗にしても、選手の起用にしても、勝負に追いかけられるようにスケジューリングされている現状が「勝利至上主義」を助長しているのではないか。
例えば秋から春にかけてのリーグ戦という形で、ゆったりとした日程で各都道府県大会が開催されれば、「負けてもいい」試合がおのずと存在し、投手の起用についてたくさんの方法を見つけ出すことができるだろう。2番手以降の投手が経験を重ねる中で自信をつかむ機会もあるはずだ。
その中で本番の夏を迎えたときに、複数の投手起用が現実的になってくるのではないか。球数制限がルール化されようとも、「不公平」を口にする指導者はいなくなるだろう。
100回目の今大会を取材して改めて感じたのは、いまの高校野球は投手への負担が多大であるということだ。
連日35度を超える猛暑は投手に最高のパフォーマンスを発揮させる環境ではない。ケガをしない投球フォームを見つけ出したとしても、この暑さでは全球でそのフォームを保つのは難しいだろう。
誰が高校生投手を守るのか
また、今大会ではいくつか問題が起きた。
2016年夏の覇者・作新学院の小針崇宏監督は「昨年あたりから、ボールが飛ぶようになっている」と打球の変化を指摘している。数年前、プロ野球でも明るみに出たボールによるものなのか、金属バットの性能の変化なのか、甲子園の風なのか、様々な臆測が飛ぶが、8年連続して甲子園出場を果たしている指揮官の言葉を軽視できない。
一方、バッテリーのサインを走者が伝達する行為も、昨今の大会では考えていくべき事象となっている。
2013年の夏、優勝を果たした前橋育英は守備時にセカンド走者を背負った場合、セカンドランナーの前に遊撃手を立たせ、捕手のサインが見えないよう対策を講じて優勝につなげた。今大会でも、「相手はサインを盗んでくるチームだと聞いたので、バレないためにサインをたくさん出した」と証言する学校があった。
「酷暑」「打球」「サイン伝達」……投手はたくさんの戦いにさらされているのだ。
球数制限の導入には賛成だ。だが、それだけでは投手の健康問題の解決にならない。
100回大会で噴出した課題に対して、どう球児たちの健康面を守っていくのか。高校野球の年間スケジュールから「甲子園」を再考していくべきではないだろうか。
(写真:岡沢克郎/アフロ)