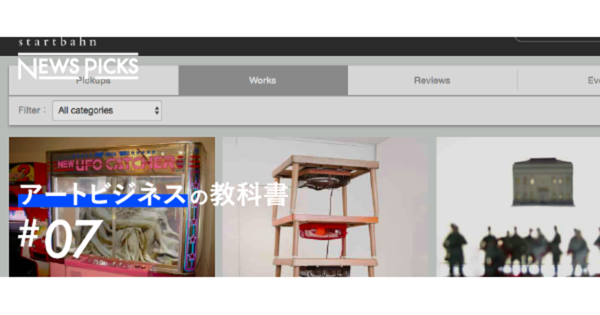【独自】ブロックチェーンが果たす「アートの民主化」
コメント

注目のコメント
「◯◯の民主化」が流行ってますね。民主的な状態もしくは民主主義の定義は学術的にも市井の認識的も多岐に渡るので、このフレーズに出会うと余計な事を考えてしまうのですが、それはどうでもいいとして、このサービスはやはり興味深い。
関連記事: https://newspicks.com/news/3150241/
"短期的な人気投票ではなく、「長い目で見て支持された作品」の価値が高まると考えています。"
これが実現すると、アートの価値を毀損せずにアート業界への参加者が増える、正にブロックチェーンを活用した素晴らしい事例になる気がします。期待してます!錚々たるプレイヤーたちのそれぞれの観点から見たアートマーケット特集の最後、未来を考察する回に取り上げていただきました。民主化というと多数決をイメージする人が多いと思いますが、僕のなかではそうではなく、誰しもが知ることができ、楽しめ、世界中のどこ出身でもシームレスにトップまで辿り着ける世界を意味します。
今では市場が成立している野球業界も、プロ野球が出来る前までは食べられる選手も少なく、野球人口も少なかったと聞きます。野球はルールが複雑だし直感的な要素がサッカーなどと比べ少ないけど、好きな選手がいたり若い頃からの経験を通じて楽しみ方を理解している人が多いことで市場が活性化しています。プロ野球のようにトップが充分に反映し、充分に情報を発信する世界になれば、自ずとピラミッドの下部も広がり市場は反映していくと信じています。
アートがそのようになるまでに課題は少なくとも2つあります。1つはトップ層の情報集約と連結、それに伴う市場のプロトコル生成、もう1つはボトム層の隆盛がトップにシームレスに繋がるルートと継続するインセンティブの確保です。ブロックチェーンを活用すると各段階を担う団体を「つなげる」ことが出来るというのもブロックチェーンの大きな可能性であると感じます。
ブロックチェーンでないとダメな理由がわからないというコメントが多いようですが、いずれホワイトペーパーなりで全貌を公開する予定となっています。脱中心的な設計、インセンティブ設計などもさることながら、何よりも還元金のようなルールの実行をスムーズにする設計、市場全体で最適解を模索することが出来る設計でブロックチェーンならではの仕組みを活用します。当然、ブロックチェーン上の情報と作品情報の紐付けに関する課題にもかなりの時間を割いて現時点での最適解となり得る仕組みを用意しております。乞うご期待。最終日は、アートの課題をブロックチェーンによって解決しようとしている企業を取材させていただきました。
取材の中で印象的だったのは、長期的な視点での評価の仕方がアートには向いているということです。多数決には向かない価値というのは他にもあろうかと思います。
おそらく、古くなることで価値が増したり、修復の良し悪しで価値が上下する「文化財」や、ワインもこの中に入ってくるのではないかなと思います。価値を可視化しにくいモノに対する、価値評価の思想設計としてとても勉強になりました。
(追記)
贋作を排除できるのが、このネットワークの利点の一つですが、一方で贋作は贋作として評価できる余地が出てきたらも面白いなと思いました。
記事には入っていませんが、施井さんも同様の趣旨のことをおっしゃっていました。
詐欺ができるようになることを勧めるということなのではなく、
本物でないものが、その後別の価値を持つものになる可能性があるのではないかなと思うからです。
先日ちょうど大塚国際美術館に行って、世界の名画の複製を見たときに、複製だけれども、3000円払う価値があるなと。
そういう評価ができないものだと、評価として不完全なものになってしまうなと、、思った次第です。完全なものなどないのだろうと思いますが。