
【田原総一朗】天皇制の未来と、ポスト平成のリーダー
2018/1/10
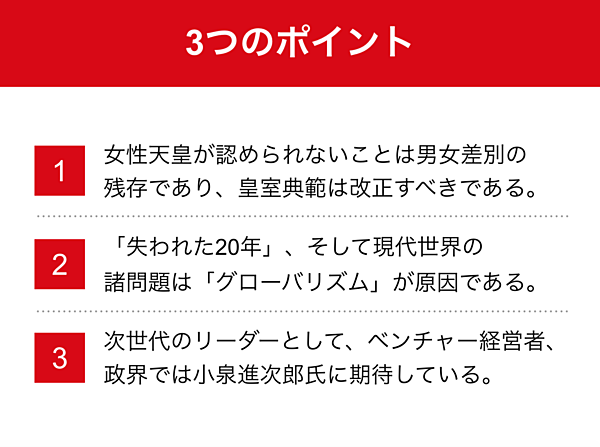
天皇制度の歴史
2017年は天皇陛下の退位の日が決まり、秋篠宮家の眞子さまの婚約が内定するなど、皇室をめぐる大きなニュースが相次いだ年でしたが、私はいまこそ「日本人にとって天皇とは何か」ということを考えるべきだと思います。
一般的に「天下を取る」とはその国の最高位になることですが、日本では時の為政者たち、源頼朝にしても足利尊氏にしても、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康も、いずれも自分の上に天皇という存在を置きました。誰も天皇を亡きものにしようとは考えなかったわけです。
だからこそ、日本は政権がコロコロ代わってもどうにか安定していられたという面があります。
ただ、いずれの時代にも、天皇に権力らしい権力はなく、財政も将軍や大名に頼っていました。つまり、天皇は象徴だったわけです。
面白いのは明治維新の際のエピソードです。当時は伊藤博文をはじめ、明治政府の幹部たちはアメリカ、イギリス、フランスに歴訪をしていました。欧米では産業革命が進んでおり、この文明を何とか日本に取り入れようとしたのです。
その際、伊藤博文は当時の世界的に有名な学者である公法学者グナイストから「天皇を、キリスト教のキリストのような絶対的な存在にすればいい」とアドバイスを受けます。
そうして、天皇の先祖を祀っている伊勢神宮を国民の中心的存在にすることとなり、あらゆる法律も、天皇の意向を受けて、大臣たちが作るようにしました。それが明治憲法です。
ただ、天皇は実際には何もせず、あらゆる責任から免れます。あらゆる責任から免れるということは、権力もないということです。これもキリスト教と同じです。
それが昭和になり、政府も天皇の名前を使って戦争をするようになりました。
敗戦後、天皇は「人間宣言」をして国民の象徴となるわけですが、象徴となるのは戦後が初めてではなく、実は、明治以前も象徴でした。

