
【水野良樹✕原泰久】最初は「無邪気」から始まった
2017/8/8
現在、“放牧中”の「いきものがかり」のリーダー水野良樹氏が、先輩クリエーターたちに話を聴きに行くシリーズ。第1弾の糸井重里氏に続いて、第2弾では、大ヒットマンガ「キングダム」の作者である原泰久氏との対談を、3日間にわたってお届けする。
10年という時間を振り返って
水野良樹 お久しぶりです。この対談は、僕が、ものを作っている方や人生の先輩方にお話を聞かせていただく企画です。
前回
僕と原さんの関係をご存じない方もたくさんいると思うので、まずはその辺りを少し。
週刊ヤングジャンプで今も連載が続いている『キングダム』という漫画がありまして。連載開始が2006年で、偶然ですが、僕ら「いきものがかり」のデビューと同じ年なんですね。
そんなきっかけもあるんですが、僕がとにかく『キングダム』のファンで、ツイッターなどで原さんに「ファンです」と送ったりしているうちにつながりができました。
『キングダム』は、今ちょうど「(主人公たちが)自国を統一する」という、大きな物語の前半部分に区切りがついて、次へ進んでいるところだと思うんですが、連載開始当初に思っていたことと、作品が世の中に広く受け入れられてからとで、原さんの中で変わってきたことはありますか?

原泰久 僕は『キン肉マン』世代で、あの当時のジャンプ作品が次々に大ヒットしていくのを見ていたので、「それくらいの社会現象を起こすぞ!」くらいの心意気を持って連載を始めました。
最初はただ無邪気に描いていたので、無邪気ならではのパワーがありました。「これは絶対カッコいい!」とか「自分の考えは間違ってない」という思いを強く持っていたので、自分の気持ちを優先する部分は大きかったですね。
当初は、読者が求めるものを意識するよりも、ストーリー1話ごとにカッコよく終わらせることが、結果的に読者の共感を得られると思っていました。でも、売り上げにはつながらなかった。作品を世の中に出す以上、売れることの大切さは理解していたので、編集側からのアドバイスを聞きながら作り方を変えたり直したり試行錯誤しました。そうしていくうちに、いつのまにか読者につながっていった感じですね。

水野 でも、ご自身の中で「絶対面白いはずだ」と確信を持っているところからスタートしているのに、それはきつくなかったですか?「自分の気持ちに従うのが正しい」と思う作り手の方も多いと思うのですが。
原 ある時点で、僕は圧倒的に絵がアマチュアだったと気づいたんです。話が面白ければ読者も喜ぶはずだと思い込んで、絵に比重がいってなかった。そのとき井上雄彦先生に絵についてのアドバイスをいただきました。「絵と話、セットで成長しないといけないんだ」と気づいてから変わりましたね。
この10年を振り返って気づくのは「ああ、自分は1歩1歩上がっていかないとできないタイプなんだな」ということです。
「どうやったらヒットしますか?」
水野 初めて原さんにお会いしたのは、確か前半の重要なキャラクターである王騎が作中で死んだ後くらいでしたね。
その頃キングダムはもう人気漫画になり始めていて、僕は「原先生に会える!」と喜び勇んで会いにうかがったんですよ。そうしたら突然「どうやったらヒットしますか?」と聞かれて、とにかく驚いたのを覚えています。
あれだけヒットが叶っていたときなのに「まだまだ」とおっしゃっていて!
原 いや、そりゃ聞きたいですよ!いきものがかりさんがもうベストアルバムを出したりしていて、すでにトップを走られていましたから。
水野 あの頃、原さんの中では「もっと受け入れられるはず」という思いがあったんでしょうか?
原 それは今でもありますね。今連載している物語はまだ半ばで、120分映画で言えば半分ちょっとくらいのところですから。後半の盛り上がりはこれからですし、もっと多くの人に楽しんでもらえる、もらいたいと思っています。
水野 まだ盛り上がりますか!

最初の頃から比べるとかなり読者の方が増えていると思いますが、作品を「商品」として見る目ってお持ちですか?
原 そこはまったくないかもしれないです。
ただ、読者が増えると女性のファンも増えてきて、人気のキャラクターが「キャー!」なんて言われると、つい艶っぽく描きたくなることはあります(笑)。
でも、奥底の部分は一切揺らがずにきていると思います。僕はまだ無邪気かもしれませんね(笑)。
無邪気さだけでは見失う
水野 原さんの無邪気さは伝わってきます。
仮に作品をビジネスだと捉えて、それだけに突き進んでいくと、読者を見失うのではないでしょうか。
もしも原さんが無邪気さを失ったり、作品としての何かを失ったりすると、逆に読者が離れるんじゃないかなと。僕も作品づくりでそれを感じることがあります。
原 水野さんも作詞されるときって、かなり深く考えてらっしゃいますよね。
水野 広がるように広がるように、いろんな解釈ができるように…というのはすごく考えて作ってます。たとえば「ありがとう」という言葉はとても短いんですが、短いからこそ受け取る人の心に寄り添って意味を広げることができるので、そういう点を意識しています。
原 それは最初からですか?
水野 僕も最初はただ無邪気に曲を作っていましたね。曲を書き始めた高校生ぐらいのときはCDが全盛期の時代でヒットソングがいっぱいあって、「あのヒットソングみたいなものを書きたい」、そういう純粋な憧れで書いていましたから。
原 では途中から、プロとして「広げる」ために何がきっかけで言葉を減らしていったんでしょうか。
水野 僕の中で大きかったのは、歌う人が女性だったことです。
10代の頃は自分が抱えている闇の部分を書きたい気持ちや、思春期にありがちな「世の中を変えてやるんだ!」という血気盛んな部分があったんですけど、たまたま組んだら、まあ牧歌的なグループで(笑)。
いざこの世界で本気でご飯を食べようって思い始めた頃に、ふと気づいたんですよ。「女の子のボーカルで、自分は何を書けばいいんだろう?」って。
たった1人の秘密につながるロマン
水野 一番男性としてモテたい気持ちの強い20歳ぐらいの時期に「コイスルオトメ」という男性の心情とは真逆の女性の恋愛の曲を書いたんです。
10代の女の子の気持ちなんて自分から離れすぎててまるでわからなかったし、オトメの気持ちなんて書くのがものすごく恥ずかしかったんですが、事務所のスタッフに「女の子のボーカルだから女性の曲を書きなさい」と言われて。半ばやさぐれて書いたんですね。
そうしたら、女の子のファンが「なんで私の気持ちわかるんですか」と。そこに驚きと喜びを感じました。
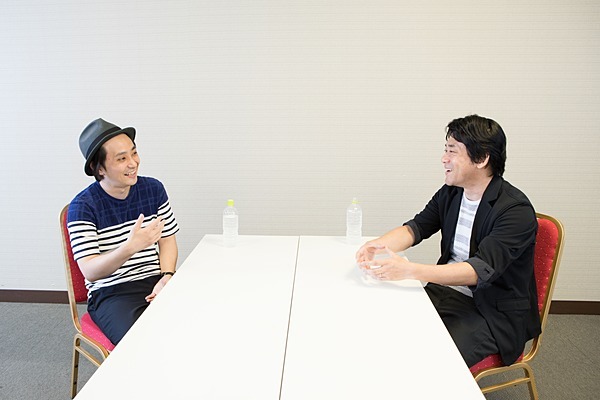
水野 見知らぬ女の子の、お父さんにもお母さんにも、友だちにも言ってないような秘密に自分の曲がつながるなんて、なんてロマンがあることなんだ!と思って。
吉岡という女性ボーカルが歌ってくれたおかげで、曲にはそういうつながり方があるんだと気づくことができました。
そこから意識的に自分から離れて、「広がる」ものへいきたいと思うようになりましたね。
原 じゃあ10代の「世の中を変えてやるぜ」という水野さんは、もういないんですか?
「半開き」ぐらいがちょうど良い
水野 いないことはないですね。完全に我をなくして商業人として無心に書くということはないです。
何も熱を入れずに小手先で書くと全然ダメで、やっぱり何か主体がないと伝わらないという感覚がありますから。
原 商品として作品を捉えすぎると、視点が変わってしまいますからね。
僕の場合だと、「読者が増えたからこうしなきゃ」という考えで売れるほうに一気に方向転換すると、多分その1~2週は面白いかもしれないですけど、10話、20話と重ねていくうちに逆に読者が離れていってしまうと思います。
読者の視点を全く考慮しないと独りよがりになるのでそれも良いことではないんですが、読者の期待に応えながらも、揺るがない本質を持ち続けるのが大切だと考えてます。
水野 「半開き」ぐらいがちょうど良いのかなと思いますね。それも、微妙に35度くらいの。
原 はい。主体性と客観性のバランスですね。
水野 閉じすぎて自分だけの世界で終わらないために、忘れてはいけないのが、作品を通じた受け手とのコミュニケーションなんですね。
(構成:仰倉あかり、写真:横山隆俊(EGG STUDIO)、デザイン:中川亜弥)



