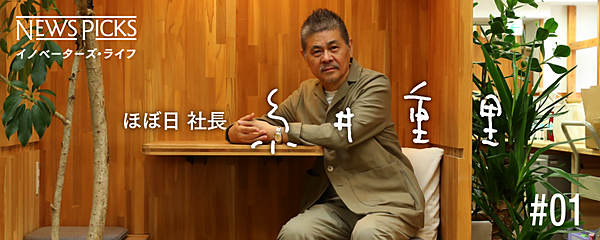
母親の温もりを知らない
2017/8/19
ぼくが生まれたころ
生まれたときのことから話すんですか? もしもぼくがほんとうに子ども時代のことを語っていったら、それはもう戦争の匂いがぷんぷんする話になると思いますよ(笑)。
実際ぼくは、進駐軍のジープなんかを見ていますから。ガムやチョコレートを投げる、兵隊さんまでね。ガムを拾ったおぼえはないけれど、それはあこがれの目で見上げていました。
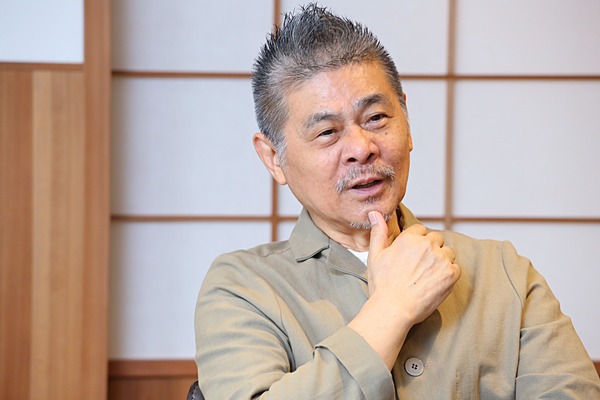
ぼくが生まれたのは1948年、戦争が終わってからたったの3年です。東日本大震災から今年で6年だと考えると、その「近さ」がわかるでしょう。
群馬県の前橋市に生まれて、大勢の人がバラックみたいなところに住んで、舗装されていないでこぼこ道に水たまりができて、父親は兵隊から帰ってきた人で。
戦時中みたいな「食うものがない」の時代は過ぎていたにしても、社会全体が貧しさで覆われていましたね。
シゲサトという名前の由来は
「重里」という名前は、父親がつけたんです。ぼくは父親が30歳のときに生まれた子どもなんですけれど、最初はシゲサトの理由を教えてくれませんでした。
「四角が多い名前がいいんだ!」とか、よくわからないことを言ってごまかして。たしかに田んぼの「田」がふたつも入っているしな、みたいな(笑)。
それが、20代の半ばくらいですかね。ようやくほんとうの理由を教えてくれました。
ぼくが生まれるちょっと前、スタンダールの『赤と黒』という小説がベストセラーになって、その主人公の名前がジュリアン・ソレルだったんですね。『赤と黒』っていうと、野心に満ちた激しい青年の、立身出世や没落を描いた物語ですよ。
そのジュリアン・ソレルにあこがれて「重里」と名付けた。だから父親のなかで重里は、音読みの「ジュリ」なんです。
若気の至りじゃないけれど、本人としては恥ずかしかったみたいですね。もう、隠れキリシタンがお仏壇の裏に十字架をしまっていたようなもので。だって、真面目な司法書士だった父親とジュリアン・ソレルは正反対の人間ですから。
なんて言うんでしょう、貧しい環境に育った父親が息子に「豊」と名付けるような、それがもっと臆面もない個人的欲望として表れた名前ですからね。
ぼく自身、「重里」には困っていました。ほかにない名前ですし、普通へのあこがれは強かったですね。
あれはいつだったのかなあ、ばあさんに連れられて小学校だか役場だかに行ったとき、ばあさんが受付で「シゲサトのサトは『里芋』の里です」って説明してて、すごくいやだったなぁ。里芋はねえ(笑)。

離婚家庭の子どもとして
普通へのあこがれということで言えば、いちばん大きかったのは自分が離婚家庭の子どもだった、という部分でしょうね。
ものごころがつく前に母親が家を出て、ぼくは父親とばあさんに育てられたんです。いまでは珍しくもない話でしょうけど、当時の田舎だと父子家庭は珍しかった。死別したわけでもありませんからね。
それで小学校なんかでも、母の日に「みんなお母さんにカーネーションを渡しましょう」と赤いカーネーションが配られるわけです。そして母親がいない子どもたちには、白いカーネーションが配られる。
泣くわけにもいかないし、悲しそうなそぶりを見せるわけにもいかない。ことばにするなら、ただただ「恥ずかしい」ですよね。みんなと違う、というその事実が。
だから小学生の2年生か3年生くらいかな、父親が再婚するって話が出てきたときはうれしかったですね。それはお母さんがほしかったというよりも、「特別じゃなくなること」のうれしさです。
やっぱり親戚の家に遊びに行っても、なにかと「かわいそうな子」扱いされていましたから。これは学校の先生からも、近所の人たちからも。
父親の再婚後にやってきた母親は、もう甘える年でもなかったし、甘えさせてくれる感じでもなかったし、関係はむずかしいですよ。
ほんとうは「お母さん」と呼ぶことにも抵抗があったけれど、それを拒絶するほど大嫌いでもない。なんだってそうだけど「大嫌い」ってことばは、「好き」の表れですから。大嫌いにもなれないくらい、遠かった。
だから、ぼくにはふたりの母親がいるはずなんだけれど、その「母親」である人たちから抱きしめられた記憶がいっさいないんです。自分から抱きついた記憶も、当然ない。
ほら、いつだったか「ローリング・ストーン」誌の表紙で、真っ裸のジョン・レノンが赤ちゃんみたいに丸くなって、オノ・ヨーコに抱きついている写真があったでしょ?
あの気持ち、よくわかるんですよ。もうね、「MOTHERー!!」ですよ。

