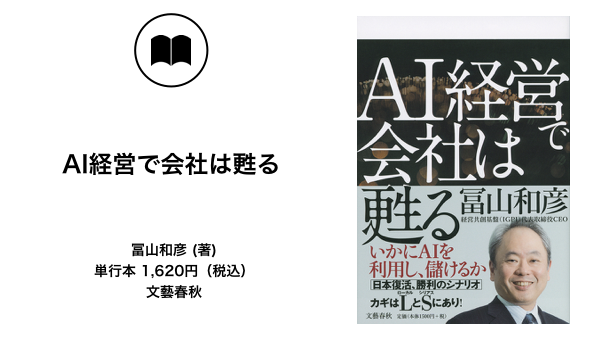デジタル革命の時代は、経営者の時代だ
2017/4/5
ほぼ「確実なこと」と「不確実なこと」
では、デジタル革命の波に飲み込まれたときに確実に起きることは何だろうか?
結論から言うと、破壊的イノベーションというのは予想ができないことが起きるから破壊的なイノベーションなのである。だから確実なことは何もないというのが正解だ。
ただ、過去のデジタル革命第一期、第二期の「歴史から学ぶ」とすれば、いくつかほぼ「確実なこと」が浮かび上がる。
ビジネスサイクルの短命化
これは、多かれ少なかれ避けられない。少なくともイノベーションの大波が引くまでは、製品やサービスはもちろんビジネスモデルレベルでも、次から次へと新たなものが登場しては、一部が残り大半が淘汰される活発な新陳代謝が繰り返される。
だから本当の脅威となる競争相手も、どこから現れるか分からない。地球の裏側の企業か、ベンチャーか、異業種か、自社の下請けか。大事なことは予断や思い込みの呪縛を捨てて、ありのままに世の中で起きていることを見つめる「白地の観察力」だ。
確率論としては、イノベーションを起こすのは自社以外である確率のほうが圧倒的に高い。経営スタンスとして自らイノベーションを追求する意思は重要だが、それ以上に誰かにやられてしまったイノベーションを自社に有利に作用させる戦略性こそが、現実経営の勝敗を決めている。
ストレートに言えば、事業ポートフォリオ、機能ポートフォリオの入れ替えを常態的かつ臨機応変に行えない企業は、非常にヤバい状況に追い込まれる。これが日本の「総合」電機メーカーに起きた悲劇である。

製品・サービス・機能のモジュラー化
これもかなりの確率で起きる。
デジタル化が進むということは、当該領域は標準化、モジュラー化が飛躍的に進みやすくなるということである。
アナログな作り込みも、よほど競争市場から見て決定的な意味を持つ領域(顧客から見れば、そこにはいくら金を払ってもいい領域)でもない限り、標準化、モジュラー化でコストが何十分の一、何百分の一に下がってしまうと吹き飛んでしまう。
日本の伝統的な優良「モノづくり」企業は、ほとんどの場合、アナログな作り込み、すり合わせが得意である。すり合わせ、すなわちAとBを何とか折り合いをつけて足し算するのは得意だが、AかBかどちらかを鮮烈に「捨てる」引き算はとにかく苦手。
すると、どうしても得意技である作り込みを過剰にやってしまい、桁違いに安いコストで標準モジュールを展開するプレイヤーに太刀打ちできなくなる罠に陥りがちだ。
はっきり言おう、製造業に限らず、「フィンテック(Fintech:ファイナンシャルテクノロジーの略)」「ブロックチェーン」の波をかぶる金融業を含め、日本の歴史ある企業の99%は放っておくとこの罠に陥る。
「日本的経営」とは、同質性、連続性、すり合わせ、ボトムアップ、コンセンサスの経営、「あれも、これも」の経営だからだ。言わば遺伝子レベルで刷り込まれているこの特性の強みを生かしつつ、それを致命的欠点としないためには、「あれか、これか」の選択のための経営のリーダーシップ、トップダウン的要素を適時、的確に作用させるしかない。
スマイルカーブ現象
いわゆるインダストリアルバリューチェーンの中で、川下側で顧客インターフェースを握り、そこでサービスやソリューションを軸とした付加価値を提供するプレイヤーと、川上でキーコンポーネント(≒圧倒的シェアを握るデファクト標準モジュールのサプライヤー)やキーマテリアルを供給するプレイヤーとが高収益をあげ、間に挟まって組立作業型の事業を営むプレイヤーが相対的に儲からなくなる現象もかなりの確率で起きてしまう。
いわゆる「ファブレス」化的な現象が、エレクトロニクス産業以外の製造業にも広がってくる可能性が高いのだ。
こうなると、どんなに素晴らしい技術や製品を持っていても、かかる産業構造の変化の中で「稼ぐ」ことのできる戦略的ポジションを取れないと、経営的には窮地に追い込まれることになる。
これがかつてデジタル革命第一期にIBMが落ちた罠であり、第二期に我が国のエレクトロニクスメーカーがテレビ事業や液晶事業で陥った「負けパターン」である。
要は、ここでも大胆に「捨てる」経営力が求められるのだ。これまた現場主導ではどうにもならない、まずはトップの「経営力」が問われる問題なのだ。

小さいこと、若いことの優位性の向上
大きな変化、それも不連続で破壊的な変化が起きるとき、既存事業者が今まで積み上げてきた経営「資産」は、あっという間にレガシーコストという経営「負債」に変わってしまうことがある。
起業ブームだなんだと言ってみても、現実経営の世界では、ほとんどの場合、ほとんどの産業で、歴史があって規模の大きい会社が有利に決まっている。
しかし、革命的な変化の時代においては、古くて大きいということは、巨大なレガシーコストを抱え込むリスク、そして環境変化のスピードについていけないリスクに対峙することを意味する。
例えば、いわゆるフィンテックのコアテクノロジーであるブロックチェーンの発展によって、既存の銀行が持っている巨大なシステム、支店網、それらを支える多くの人員が不要になれば、こうした「資産」は一気に巨大な「負債」に転じる可能性がある。要は、小さいこと、若いことの優位性が大幅に高まるのだ。
個人の立場で言えば、「古くて大きい」側でこの課題に立ち向かうか、それともここぞチャンスとばかりに自らベンチャーに身を投ずるか、という選択がリアルになってくる。
トップの経営力の時代
以上、突き詰めて言えば、もっとも「確実なこと」は、デジタル革命の時代は、経営の時代、とりわけ経営者の時代になるということだ。
逆に、ここで指摘したこと以外のほとんど全ては「不確実なこと」、一生懸命に予測し、事前に緻密な戦略を組み立ててもほとんど意味がないことばかりである。
かく言う私も、第一期(1980年代)、第二期(1990年代)は「戦略コンサルタント」として飯を食っていたので、コンピュータ、エレクトロニクス、通信分野において色々な戦略案を作ったが、今読み返すと赤面もののイタい提言だらけである。
不確実なことは不確実なものとして経営すること、これは私たちが賢者たるための「歴史からの学び」なのである。
(撮影:竹井俊晴)