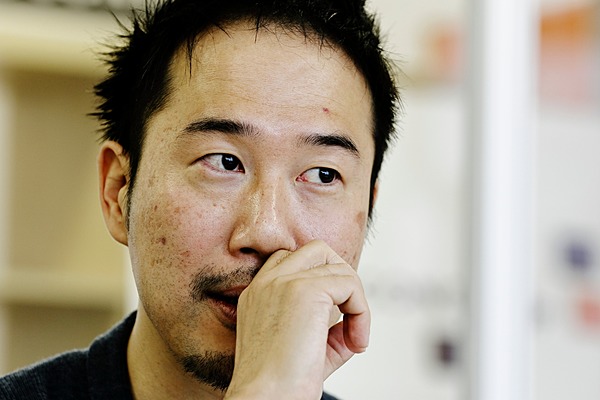【ロコンド田中】「地獄」から始まった経営者生活
2017/3/7
3月7日に上場した、靴の通販などを手がけるロコンド。一度は倒産危機にあったロコンドはどのように立て直したのか。そして、これからアマゾン、ZOZOTOWNなどの強敵とどう戦うのか。上場までのストーリーと今後の成長戦略について、社長の田中裕輔氏に聞いた(全4回)。
「お前が経営するなら、5億円やる」
──ついに上場までこぎつけましたが、一時期、ロコンドはいつ潰れてもおかしくない状況でした。田中さんが社長に就任した2011年2月時点で、ロコンドはどんな状態だったのですか?
そもそも、私は創業者ではなくて、ロコンドはロケット・インターネット(ドイツに拠点を置くベンチャーキャピタル。シリコンバレーなどで流行したモデルを他国の市場で展開することを得意とする)の100%子会社として生まれました。
私が代表取締役になったとき、会社には3人の代表がいました。売上高1000億円を掲げて、アルバイトを含めると社員も一気に約200人にまで増やして、恵比寿の超一等地にある300坪のオフィスに入居していたのです。
──スタートアップなのに?
物流倉庫もすごく立派な所にあり、社員の福利厚生も素晴らしかった。普通、ファッション業界は買い取りってあまりしないのですが、全部買い取りでしたし、半年間でテレビCMなどに10億円も使いました。
──その結果は?
大惨敗でした。
タイミングとしては、ちょうど東日本大震災があったのですが、それはきっかけでしかありません。当時、私はマッキンゼーに所属しながらインターンとしてロコンドの立ち上げをサポートしていたのですが、「明らかにこれは無いな」と思いながら働いていました。
そしてついにロケット・インターネットが撤退するという話になったのです。
もうロコンドはダメになるかと思ったのですが、ロケットのCEOと話すと、「お前が経営をやるんだったら、追加で5億円やる」と言われたのです。そこから地獄が始まるのですが。。。。

田中 裕輔(たなか・ゆうすけ)
ロコンド社長
1981年生まれ。2003年、一橋大学経済学部卒業後、マッキンゼーに入社。2007年、26歳で同社史上最年少マネージャーに就任。2009年、カリフォルニア大学バークレー校経営大学院にてMBA取得。同年、DeNA Globalにおいてマーケテイング・製品担当上級副社長を経て、2011年、ロコンドを創業。著書に『
「今の自分」から始めよう』『
なぜマッキンゼーの人は年俸1億円でも辞めるのか?』がある。
──そもそも、どうしてロコンドとの縁ができたのですか?
マッキンゼーで働いた後、UCバークレーでMBAを取ってから、DeNAのアメリカ支社で半年間くらい短期移籍のようなことをさせてもらって、2010年にまたマッキンゼーに戻ってきました。ただし、あのシリコンバレーの空気を味わってしまうと、「マッキンゼーってちょっと」というところがあって、1年間悶々としていたのです。
そんな時に、ベンチャーキャピタル(VC)の人たちとよく会っていて、そこで、たまたま縁があったのが、ロケット・インターネットの当時のCEOだったのです。
私が「起業したい」と言ったら、そのCEOが「今ロコンドに続く2社目の会社を作る準備をしているので、それと一緒にロコンドの立ち上げもサポートしてくれないか」と誘ってくれて、そこからロコンドで働き始めたのです。
──いざ働いてみると、とんでもない会社でもう倒産間近だったわけですね?
(私が参画した2月)当時はもう破産の処理を進めていたはずです。ロケットは3月中に撤退を決めて、4月に破産処理する流れで進んでいました。
その時、ロケットのCEOに上海に呼ばれて「どうする?」と問われたのですが、私はマッキンゼーに戻るつもりだったので、無責任に「こうすればいい」といろいろとしゃべったのです。
──コンサル的に?
そうです。その時初めて財務諸表を見て、厳しいと思いつつ、「ここを削ればいい」「やるとしたらコレしか無い」といった話をしていたら、「では、お前がやれよ」みたいな話になったのです。
──火中の栗を拾うことに迷いはなかったのですか?
迷いました。相当迷いましたよ。それこそ、初めて子どもが生まれる時でしたから。
──それは奥さんも反対するでしょうね。
給与の保証もなければ、会社が続く保証もない。ただ、自分で偉そうに言ってしまった以上、やってみる価値はあるのかな、みたいな感じで引き受けることにしました。
スーパー悪役としての日々
──そこから経営者人生が始まるわけですが、何から取り組んだのですか?
3段階あります。「コスト削減」「資金調達」「売上高拡大」です。
デイワンが始まって、一番きつかったのはコスト削減ですね。当時社員が200人もいたので、毎月1億円以上もキャッシュアウトがありました。毎月の売り上げが1億円もいっていない時にですよ。利益が出るどころか、売り上げ以上のコストを払うという状況だったのです。
これは「急ピッチでコスト削減するしかない」と決めて、辞めてもらう人間に辞めてもらいつつ、恵比寿のビルからも倉庫からも撤退しました。買い取った商品も返品交渉しました。最初の半年間は辛かったですね。
とにかく、投資ができない。夏はサンダルが売れる時期なのですが、お金がなくて、サンダルすら仕入れることができない。ブーツなどの冬物をひたすら返品していきました。当然、売り上げは下がっていきました。
取引先の中には、年商数億円、数千万円みたいな小さい企業もあるので、うちが返品したら相手側の企業も危うくなりかねない。それこそ、倉庫がトラックで囲まれたりとか、裁判になったりとか、労働基準監督署に入られたりしました。
精神的にきつかったのは、人を傷付ける事の方です。胸が痛かったのは、社員のリストラです。中には子供が病気の社員がいたりもしましたから。
──田中さんは優しいというか、情に脆いタイプですか?
いや、優しい方ではありません。優しかったらこんな冷徹なリストラはできていなかったと思います。
ただ、優しいかと聞かれると、優しくない気もするのですが、とはいってもやはり人間ですから、つらいですよ。特に自分に子供が生まれて、子供の顔を毎日見るのに、子供が病気の社員をリストラするというのは、どれだけ優しくない人間でもハートに来ますね。
──起業人生の始まりがリストラからという人は珍しい。
そんな例は無いと思います。デイワンから、スーパー悪役ですから。
しかも、当時の代表のうち、私が財務と人事とオペレーションの担当でしたが、お金と人のところはいちばんきついところでした。
──過去の負の遺産をつくったのは、自分の責任ではないですよね。それなのに、自分が泥をかぶることに対して、違和感はなかったですか?ハートの弱い人であれば、自分がつくったわけではない負の遺産処理のために、頭を下げられない気がするのですが。自然な感情として「なんで俺が謝らないといけないの?」とは思いませんでしたか?
そうした思いが、どこかでチラついたことが無いと言えばウソになりますが、4月に正式に5億円を追加投資してもらった時点で、たとえ過去の負の遺産だろうと私に責任が生じていると思ったので、そこはもう愚直にやるしかないという気持ちでした。
当時の私は、いわば、半年後に沈没することがわかっている船の船長だったわけです。それなのに、船にこの穴を空けたのは前の船長のせいだと言ってもしょうがない。とにかく今は、生き延びる為にやれることを全部やるしかないという感じでした。
──社長を引き受けるからには、ロコンドのビジネスに対する勝算もあったのですか?
可能性はすごく感じていました。
ちょうど(靴の通販を手がける)ザッポスのCEOであるトニー・シェイの講演を聞くチャンスがあって、話を聞くと、単純な通販ビジネスではないなと。トニーは「Delivering happiness(幸せを運ぶ)」と言っていますが、事業に意義を感じる、すごくいいビジネスだと思ったのです。
スケールも大きいですし、アメリカのザッポスだけでなく、ドイツではファッションECのザランドも成功しています。ザランドは上場していて、時価総額は1兆円程度(3月3日時点で88億ドル)になっています。
その成功を見て、2010年から2011年前半にかけて、日本、ロシア、南米、東南アジアなど世界中で同じビジネスモデルが出てきたわけです。
どん底で投資してくれた2社
──社長になって、まず「コスト削減」に取り組んだわけですが、ほかに苦労したのは何ですか?
血を止めるのが一番大変でした。
コスト削減が進んで、血が止まりきってないけれども、カサブタになり始めたら、次に資金が必要になります。
2011年9月にMBOした後は、新たに融資をしてもらったりして資金調達をしていたのですが、「客観的に考えてこんな会社に投資する会社はいるのだろうか」と思いながら、資金調達を進めた部分はありました。
5年間くらいかけて、資金調達はシリーズEまで行きましたが、シリーズDまでは、本当にあと3日遅れたらキャッシュがショートするという状況でした。資金調達はエンドレスで続く悩み、苦労、いや、課題としてありました。
──かなり断られましたか。
相当断られました。
──どれくらいの数の投資家に出資をお願いしたのですか?
数十のVCや事業会社の社長さんに会いました。いろいろ話して。
──けんもほろろでしたか?
そうですね。
我々の事業は、最初に損益分岐点をこえるまでは、相当なお金が必要になります。おそらく、損益分岐点をこえるまでに、ザランドは200億円くらい、ザッポスも60億円くらい使っているはずです。
その後のスケールの考え方が、日本と欧米では異なります。
日本の場合、どちらかと言うと、小さなお金でドーンと当てるみたいなところがあったので、その考え方からするとうちのビジネスモデルはあまり合わないという理由で、ノーという人が多かったですね。
──日本では、最初に大きく投資して、赤字を続けるのはなかなか理解されません。
基本は、楽天しかり、(ZOZOTOWNの)スタートトゥデイしかり、早期に、小さく黒字を作りながら、会社を大きくしていくやり方だったので、そこに後発組として追いつくには、大きく投資する必要があります。しかし、それを納得してもらうのが大変でした。
──もっとも助けてくれたのはどこの会社ですか?
2社あります。
1社は、一番最初に投資してくれたリードキャピタルマネジメントです。旧アントキャピタルというプライートエクエティから独立したブティック系のVCで、2011年9月のタイミングで投資してくれました。
どう客観的に考えても投資するのはありえないという時期に、5億円を投資してもらったのですが、その翌月には借金の返済などで約3億円が消えてしまいました。
しかも、毎月5千万円くらいキャッシュが足りない状況で、2、3カ月したら力尽きるのがわかっている状況でした。他のVCも誘ってもらったり、すごく助けてもらった会社です。
2社目が(スポーツ用品販売などを手がける)アルペンです。シリーズDで入ってもらったのですが、10億円という、当時のわれわれからすると大きな金額を投資してもらいました。今でも、いろんな事業で提携させてもらっています。
──2社はロコンドや田中さんのどこに可能性を感じたのですか?
リードキャピタルは、投資方針が日本のVCと少し違っていて、どちらかというと多少リスクがあっても、ある程度株式比率を持って一緒に成長しながら大きくしていくという考え方でした。
そういう意味では博打(ばくち)ではありましたが、事業の可能性は感じてくれていました。全世界で広がっているビジネスモデルですし、このビジネスが来ることは何となく分かる。ただ、このタイミングで投資して良いかは悩みどころだったはずです。
──アルペンはどうですか?
一番大きかったのは、シナジーを強く感じてもらった点だと思います。
当時ニューバランスのスニーカーブームが始まったころで、ニューバランスのスニーカーはどこに行っても買えない時期でした。しかし、アルペンでは、ニューバランスの靴が40%オフで売られたりしていて、在庫が多くあったのです。
アルペンに行くお客さんと、ロコンドやセレクトショップに行くお客さんは違います。実際、アルペンで売っているニューバランスの靴を、ロコンドで正規の値段で売ってみたら売り切れてしまったのです。
商品の共通性はありながら、顧客が違う。リアルに強いアルペンとECが強いロコンド。顧客という点でも、チャレンジという点でもすごく互換性があると感じてもらって、「もっと組もう」ということになったのです。
黒字化に涙
──コスト削減、資金調達にメドがつき、3段階目の「売上拡大」に力を注ぐことができるようになったわけですね。
私が経営を始めてから、1年半は売り上げがほぼフラットという状況が続きました。
これは精神的に苦しかった。社内の士気が上がらないのです。やっぱりみんな売り上げを一番見ますよね。赤字でも売上高がグーンと上がっていれば何となく士気が上がるのですが、売り上げが上がらないのですごくつらかったですね。
──1年半も退却戦が続きますと疲弊します。
病気から生き延びる事だけに集中していましたから。
──その1年半の間に、かなりの人が辞めましたか?リストラも含めて。
辞めてもらった人間も当然いますし、辞めたメンバーもいます。今の私から見ても、当時のロコンドには将来性は感じられなかったのだと思います。
──この地獄の1年半を一緒に耐えたメンバー同士は深い絆ができていそうですね。
そうですね。2015年10月に初めて黒字化した時には、涙を流すメンバーもいました。

現在、代々木のオフィスには68名の従業員が働いている。
──今の中核メンバーは、当時を知っているメンバーがほとんどですか?
2011年の地獄を知っているメンバーが3分の1、2011〜2013年の士気低下モードの中で入っていたメンバーが3分の1、ここ2、3年くらいで入ってきたメンバーが3分の1というミックスです。
──その後、急に売上高が上がり始めますが、何が理由だったのですか?
そこは論理的に説明できる部分と出来ない部分があります。
* 明日掲載の「武器はITと物流。これからの成長戦略」に続く。
(撮影:竹井俊晴)