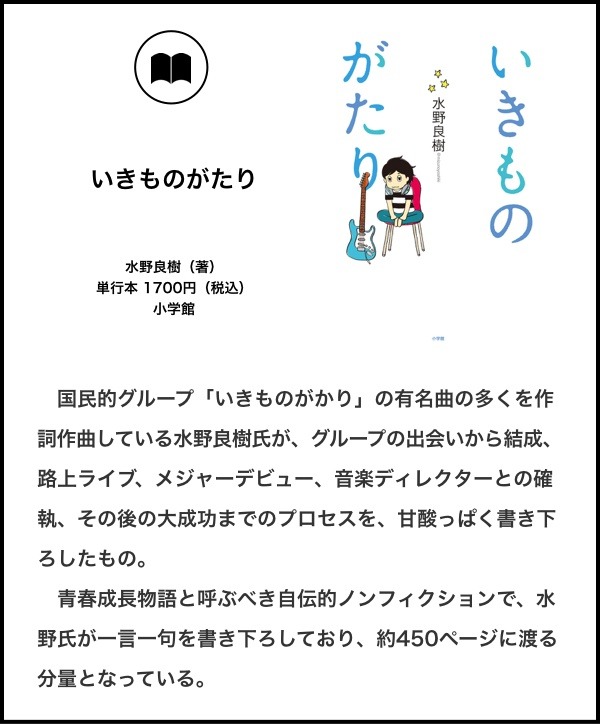【水野良樹×糸井重里】表現者は「山の下り方」が難しい
2016/8/29
第1回: 言葉は空気。何も言わない伝え方もある
第2回: 「寂しさ」をずっと考えてきた
第3回: 表現者は山の下りかたが難しい
第4回: 音楽の新しい“球場”を作りたい
第5回: 「夢」に手足を付けて届けたい
第2回: 「寂しさ」をずっと考えてきた
第3回: 表現者は山の下りかたが難しい
第4回: 音楽の新しい“球場”を作りたい
第5回: 「夢」に手足を付けて届けたい
新たな山に移れる人、移れない人
糸井:水野さんは、今は曲作りが面白いという状況にあるようですが、いつかはもうこれ以上は作れないという時期が自然とくるかもしれません。そのときに、次のことに飛び移らないと、生きていけません。
人は降りるのが苦手なものですから。
音楽家の場合、意地悪な言い方をすると、一生に作った曲のエキスが最初の3枚にすべて入っていると思います。
そのエキスをすべて捨てて新たな山に移ることができる人と、できない人がいます。

糸井重里(いとい・しげさと)「ほぼ日刊イトイ新聞」主宰。1948年、群馬県生まれ。コピーライター、エッセイスト、作詞家、ゲーム制作などマルチに活躍。70年代からコピーライターとして注目され数々の広告賞を受賞。98年に毎日更新のウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」を開設。著名人やクリエイターなどの連載を始め、ほぼ日手帳や様々なオリジナルグッズを販売。東京糸井重里事務所は、イノベーションを起こした事業を表彰する「ポーター賞」を2012年に受賞した。
だいたい最初の3枚を編集し直すのがポピュラーソング・ライターの一般的なパターン。それはそれでいいと思います。最初の3枚が「いいね」という世界観をもう確立したのですから。
水野さんの場合でしたら、寂しさという衝動で社会とつながれる状況がなくなった、と。では「どうするんですか?」というのを、音楽家の先人たちはずっとやってきました。
その中で、いちばんカッコイイ人のまねをすると、うまく山を下りられるかもしれませんね。やはり、すごいと思われている人は、寿命が短いものです。
ビートルズのような存在はまずいません。
水野:そうですね。亡くなってしまった人以外は。
糸井:ずっと歌い手(パフォーマー)として長く生きていく人もいます。
たとえば、キャロル・キングは、今はライブがメインですよね。同じ曲でずっとやってもいいんです。
ローリング・ストーンズは70歳を過ぎて、昔の曲でライブをやっていますし、ポール・マッカートニーもまだ曲を作っています。音楽家の人生は、先人の例が山ほどあって面白いです。
でも、30代だったら、まだ余裕で全力疾走できますね。
水野:走れますけど、どっちに行こうかと迷います。
糸井:世界制覇できるくらいの気持ちで走れるんじゃないですか?
水野:いやいや、そんなことないです。
でも、寂しさがパワーの源になっているのは継続中です。路上ライブにたとえると、10~20人くらい集まりだすと、この人たちにどう気に入られるかばかりを考えてしまいます。
この10~20人が自分たちを応援してくれるようになるからです。

水野良樹(みずの・よしき)
「いきものがかり」のリーダー、ギター担当。1982年、静岡県生まれ。5歳より神奈川県で育つ。1999年、高校生のときに現メンバーの山下穂尊(ギター&ハーモニカ)、吉岡聖恵(ボーカル)といきものがかりを結成。明治大学中退、一橋大学卒業。2003年にインディーズ・デビュー。06年にエピックレコードジャパンからシングル「SAKURA」でメジャー・デビューした。
「いきものがかり」のリーダー、ギター担当。1982年、静岡県生まれ。5歳より神奈川県で育つ。1999年、高校生のときに現メンバーの山下穂尊(ギター&ハーモニカ)、吉岡聖恵(ボーカル)といきものがかりを結成。明治大学中退、一橋大学卒業。2003年にインディーズ・デビュー。06年にエピックレコードジャパンからシングル「SAKURA」でメジャー・デビューした。
実力は突き詰めると筋肉
水野:でも、そうやって知り合って、わかりあった人としかつながれないのは、寂しいなと思ってしまうこともあります。曲とは、わかりあえない人とつながるためのヒントのようなものだと思うからです。
だから、路上ライブの前を通り過ぎていく人ともつながりたいけれど、どうしても集まってくれた人との関係性が濃くなってしまう。
それが寂しいと感じます。
ファンになってくれた人には、とても失礼な言い方で恐縮ですが。
糸井:生き物は、閉じていたら死んでしまうので、手を伸ばし続けるんです。路上ライブは、お客さんが来てくれるだけでなく、自分から出かける要素もあります。
生命の歴史も、筋肉が初めてできたとき、出かける要素が加わりました。
最初は動くこともできず、周囲のエネルギーを取り入れて出すだけでした。でも、筋肉ができて、栄養を取りに行くことができるようになって、その次は、神経系が発達し、どっちに行けば効果的か、どんな罠(わな)を仕掛ければいいかを思索しだします。
そう考えると、「いきものがかり」は、今ちょうど筋肉が発達した生き物となっているから、ムンムンしているんじゃないですか(笑)。
水野:ムンムンですか(笑)。
糸井:実力って、突き詰めると筋肉のことです。
その筋肉を使って、お客さんを獲得することもできるし、新しい世界をのぞきにも行かれます。だから、思うままに走ればいいだけです。それで楽しいはずですが、やがて必ず厄年がやってきます。
水野:また問題が起きると(笑)。
糸井:そうです。人と通じたと思ったら、まだ通じていない世界の大きさを知り、がっくりくるんです。
水野:糸井さんの著書に、万能感で突っ走ってきたけど、それが崩れた時期があったと書いてありましたね。
糸井:僕の万能感が崩れたのは40歳のときです。
やりたいことは、全部やれるだろうと思って生きてきて、ふと気づいたら、だれも自分のことを知らないし、だれも自分のことを認めてくれない。目の前に、壁を越える大山が立ちふさがっていて、これが実際の世界だったのだと気づかされました。
アーティストも、コピーライターも、大きなサブカルみたいなもの。

40歳で、挫折を認識できてよかった
糸井:「世界の本体は、実はこっちかよ」と気づいたとき、とても寂しかったです。自分が通用しなくなった寂しさだけでなく、これはもう生まれ直さなきゃダメじゃないかと……。
水野:えっ、そこまで落ち込んだんですか!
糸井:はい。体が元気だったからよかったけど、あそこで病気にでもなったら厳しかったでしょうね。
水野:今、振り返ってみると、その大きな山に出会ったことは、良いことでしたか?
糸井:人生で必ず出会う山だから、しっかり挫折みたいなものを認識できたことは良かったと思います。
振り返ると、あの時期にいちばん人生について、自分について考えましたから。
水野:その大きな山をどう越えたんですか?
糸井:ずうずうしいまでの楽天性もありました。
ジタバタすれば何とかなる、という感じです。サドンデスに持ち込んで、勝つまで戦えばいい。そこに僕の“丈夫さ”があるのでしょう。
結局、稼ぐお金の額や自分の力の大きさではなく、自分で勝ったと思えれば勝ちです。
その意味では、だれでも勝てるはずなんですけど、“負け慣れ”マインドになるとキツイですよね。まさに「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ(命を捨てる覚悟ができれば急流でも身体が浮かぶものという意味)」です。
「開き直る」でも「ヤケになる」でもなく、いままでしがみついていたものから手を離したら、意外に泳げたなというイメージです。だから、世の中に出る方法よりも、下りかたのほうがずっと難しいんです。
山を登っている途中だと思っていたら、突然もう登れないということがわかって、引き返そうにも、下りかたがわからない。ヘリコプターが飛んできてくれれば別ですが。
そういえば、宇多田ヒカルさんの下りかたは印象的でしたね。
水野:宇多田さんは、活動を再開してニューアルバムを出されるそうです。
糸井:見習うのもいいかもしれませんね。いったん活動を完全に止めて、また再開できたら、そのあとはもう大丈夫かもしれない。
いったん下山してイノベーションを起こす
水野:僕はまだ山の下りかたはわからない。だから、下山は怖いと思っていました。
糸井:そういえばトップアイドルのグループがいちばん上り坂のとき、僕は1年くらい休養すればいいと思いました。
歌手を休業してどこかの会社で営業に出たら、有名人だから「よく知っていますよ」と言われますよね。
知らない人から「知っていますよ」と言われるのは、路上ライブより大変です。
その苦労を1年味わって、その間に踊りの練習もして、2年後に復帰したら、ものすごく大きくなっていると思うんです。
水野:なるほど。そういうやり方もあるのですね。
ふつうは、「知っていますよ」と言われる世界から逃げたいから休養するんです。
でも、「知っているよ」と言われて対応することが糧になるとは気づきませんでした。どうすれば、糸井さんみたいな気づきが得られるのでしょう?
糸井:僕は何事も「もし◯◯だったら」と、本気で考えます。
もし有名人が営業マンになって、「あなたに来てもらっただけでうれしい」と、お客さんから言われたら、それはかなりツライだろうなと、考えます。
水野:考えてみると、ホントにつらいですね。
糸井:「会えてうれしい」と言われた後、答えのわからないような課題を与えられたりします。そのとき、歌を作っていたときの「みんなを驚かしてやるぞ」という下品さが浮かび出てくるかどうかが問われるのです。
水野:急に就職してみたくなってきました。休養したら、糸井さん雇ってください(笑)。
糸井:きっと面白い体験ができますよ。
僕も「もしゼロからこの仕事を始めたら、どうなるかな?」と、いまでもいろいろ考えます。

下りも上りと同じぐらい重要な要素
糸井:でも水野さんは、たとえばマドンナはなぜライブなのかなど、そういう領域を考える人になったほうがいいでしょう。マドンナは、音楽家として世界でいちばん多く稼ぎ、いちばん最初にライブに行った人ですよね。
僕はビートルズ世代ですが、ジョン・レノンがやっていたことは、音楽家でなくてもすごかったと思います。『アイ・フィール・ファイン』の曲の最初に、あの変な音はなぜ入れてあるのか。
ギミックそのものです。
水野:だから、あれはなにかと言い合うのが楽しかったですね。
糸井:加瀬邦彦さんという『TOKIO』の作曲家の方が、レッド・ツェッペリンが来たときに、ドラムの音を再現するのにデータがまだなかったから、ドラムヘッドを半分破いて、中に雑巾を詰めてたたいたという逸話があります。
そういう努力が何かを進化させるのだと思います。今、バンドをやっている人たちが違う頭を使うというのは、邪魔にはならないと思います。
大瀧詠一さんは、それをずっと考えていましたね。
水野:大瀧さんは音楽の職人であることに、強いこだわりのあるイメージがあります。
糸井:「電気は、同じコンセントから引いても波があって、いちばんいい波の電気を取りたい」と大瀧さんは言ったのです。音楽をよくしたいという意味ですが、「それで作り上げた楽曲(『A LONG VACATION』)で、10年は飯が食える」とも彼は言いました。
1枚アルバムを出しただけで、10年も食えるのはすごいことです。
水野さんも、停滞感があるなら、思い切り馬鹿なことを考えたらいいんです(笑)。馬鹿なくらいなことをやらないと、イノベーションは起こせません。
イノベーションには、上りだけでなく、下りの過程も入っています。下りも、上りと同じくらい重要な要素です。
(構成:栗原 昇、撮影:池田光史)
*明日公開の「 音楽の新しい“球場”を作りたい」に続く