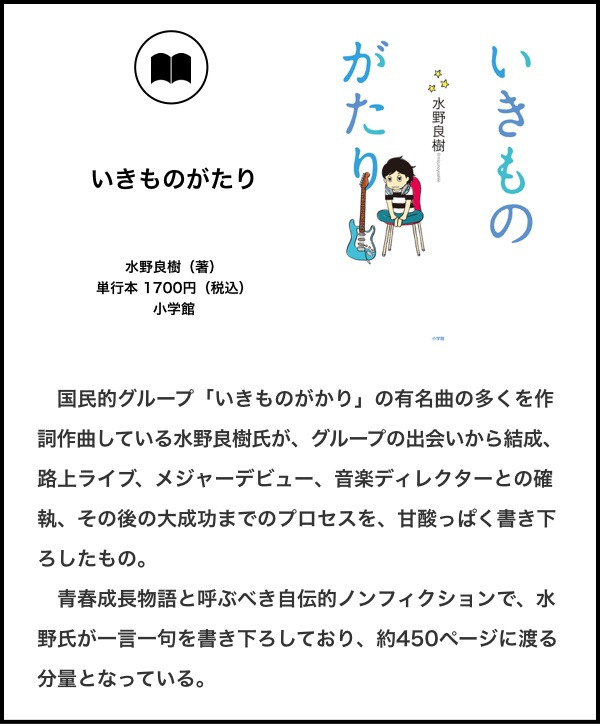【水野良樹×糸井重里】言葉は空気。何も言わない伝え方もある
2016/8/27
いきものがかりは、何も言ってない
水野 :今回の対談は、僕が言葉を扱うプロとして経験豊富な糸井さんからお話を聞き、いろいろ勉強をさせていただくという企画です。
数日前から糸井さんに何を聞けばいいかずっと考えていて、やはり糸井さんとつながるなら、犬の話かなと思いました。というのは、糸井さんは犬や猫と人が親しくなる『ドコノコ』というアプリを出していて、僕も犬を飼っていますから。
実は、昨日の深夜、家に帰ったとき、犬を起こしてしまったんです。
そうしたら、すごく嫌そうな目で僕を見てきて、その目のまま体をねじって、おなかを上にしました。これは「なでて欲しい」というサイン。起こして申し訳なかったから、なでていたら、今度はとても喜んでいる表情になりました。いつものことですが。

水野良樹(みずの・よしき)
「いきものがかり」のリーダー、ギター担当。1982年、静岡県生まれ。5歳より神奈川県で育つ。1999年、高校生のときに現メンバーの山下穂尊(ギター&ハーモニカ)、吉岡聖恵(ボーカル)といきものがかりを結成。明治大学中退、一橋大学卒業。2003年にインディーズ・デビュー。06年にエピックレコードジャパンからシングル「SAKURA」でメジャー・デビューした。
このときリハーサルで疲れていたせいか、犬としゃべっているような気になったのですけど、実際に言葉はありません。
あれ、この状況は糸井さんとの会話のヒントになるのでは……と。犬の飼い主なら、犬と会話している気になったり、コミュニケーションをガッチリ結べていると感じる瞬間が必ずあるはずです。それが昨日、僕にもあったのです。
言葉のあるコミュニケーションと、言葉のないコミュニケーション。どっちが豊かだったり、良かったり、あるいは何が足りなかったりするのか。
そういうことを、今日は糸井さんと話して考えたいですね。
糸井 :僕もそれは考えたいですね。
たぶん、ずっと僕がテーマにしていることです。「いきものがかり」というバンド名に、すでに今の話が含まれていると思います。極論すると、何も言っていませんよね。
水野 :おっしゃる通りです。
糸井 :何かを言わないようにしている人の名づけ方だと思います。
たとえば、「パイオニア」という名前だったら、「第一人者になるぞ!」という強い意志が感じられます。

糸井重里(いとい・しげさと)
「ほぼ日刊イトイ新聞」主宰。1948年、群馬県生まれ。コピーライター、エッセイスト、作詞家、ゲーム制作などマルチに活躍。70年代からコピーライターとして注目され数々の広告賞を受賞。98年に毎日更新のウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」を開設。著名人やクリエイターなどの連載を始め、ほぼ日手帳や様々なオリジナルグッズを販売。東京糸井重里事務所は、イノベーションを起こした事業を表彰する「ポーター賞」を2012年に受賞した。
「何も書かないこと」が大事だった
でも、いきものがかり(生き物係)は、学級委員でもなく、風紀委員でもなく、秀才でも、天才でもない。
空いたスペースを担当するというか、これなら自分でもできそうだ、と手を挙げるのが生き物係ですよね。
水野:まさに、その通りです。
糸井:ふつうのバンドの自己主張とは違うところで、歌を歌っているところが新鮮です。バンド名で、以前から感じるところがあったんです。
水野:それはうれしい限りです。
種明かしをすると、「いきものがかり」という名にしたのは、たまたまメンバーの山下穂尊と小学校時代、一緒にクラスの「生き物係」をやっていたからです。
今、糸井さんが言ったように、僕たちはあまり自己主張をせず、自分たちでなければ成立しない言葉や、自分たちが演奏しないといけない歌というところから、なるべく外れようとしてきました。
それを大事にしているので、今日糸井さんにそのことを気付いてもらってうれしいです。
糸井さんは、コピーを書いたり、文章をサイトに毎日アップされていますが、自分が発信した言葉に対して、自分とのつながりは、どう考えていますか?
糸井:水野さんが想像するように、まさしく僕も「生き物係」です(笑)。自分が言ったかどうかは、僕にとってはどうでもいいんです。
たとえば、小さい娘さんの誕生日をお祝いしているお母さんに、娘さんが「お母さん、生んでくれて、ありがとう」と言ったという話があります。そういう言葉がサラッと出る。そういう言葉をもし自分が書けたら、「出た!」と思います。
言葉というのは空気のようなもので、いい匂いのする空気で、みんなが心地よくなれば、だれがその空気を出したかは気にしません。
これと同じものを「いきものがかり」に感じました。
特に『風が吹いている』は、「何もないよ」という内容の歌詞になっていますね。
水野:そうです。
『風が吹いている』を作った2012年は、前年に東日本大震災が起きて、世の中がバラバラという状態でした。原発の問題にしても、いろいろな人の正義がぶつかっており、そこには僕の意見や正義もあります。
でも、自分の意見はこうだ、と歌の中で言っても仕方がないと思ったのです。
ただ風が吹いているという、同じ場にバラバラの人がいることを書ければいい。だから、意見や主張っぽいものは「何も書かない」ことが大事だったのです。
糸井:人がいてもいなくても、風は吹いていますしね。昔、ボブ・ディランが『風に吹かれて』という曲を作りましたが、この曲にも混じっていた概念ですね。
つまり、風はいつの時代にもあります。
あるけど、見せられないもの。水野さんには、そういうものに対する敬意や愛着があるんだなあと感動したので、当時水野さんのTwitter宛てに曲の感想を書き込んだのです。
「分かってもらいたい」はしたくない
水野:その糸井さんの書き込みがとてもうれしかったんです。ありがとうございます。
ところで、糸井さんは「自分が書いたことはどうでもいい」と言いましたが、それで葛藤する時代はありませんでしたか? 今の僕と同じ30代のとき、糸井重里という名前が世に広まり、名前だけで人が集まる状況もあったと思います。
「これは自分が出した、作った言葉だ」と言いたい時期はなかったのですか?
糸井:コピーは匿名が基本ですから。
だれかが勝手にまねをしていたら、「それは俺だよ」と言ったでしょうけど。あとは、近くの人、社内や妻が「いいわ」と褒めてくれたら、ものすごく自慢げに言うと思います。でも、知らない人から褒められるのはどっちでもいいです。
水野:僕もだいたい同じような感覚です。
糸井:その感覚は、村上春樹さんも同じでしょうね。
彼は最初に奥さんに作品を見せるそうですが、ぜんぜん褒めてもらえない。初めて褒めてもらえたのが『ノルウェイの森』だったそうです。僕も、社内で「これすごくいいですね」と言われると、めちゃくちゃうれしいです。
水野:では、『おいしい生活。』のように、社会に影響を与える言葉があります。そういう言葉に、不安を感じることありませんか?
糸井:それは、あります。コピーは作者に関係なく、広がっていく。その道のりを想像しながら書いているから、当然悪く思われることも想像しています。
『おいしい生活。』のときは、当時の西武百貨店社長の堤清二さん(故人)が決裁しましたが、「これが世に出て、堤さんに女性問題などが出たら、『堤清二のおいしい生活』と、週刊誌に書かれますよ」と言ったんです。
覚悟してもらう必要があるから「それはいいですか」と確認しました。今だったら炎上という事態がありますよね。
ちなみに、糸井重里と言ったら、商売上手という言葉が必ずついてきます(笑)。
「あれは大金をもらってるにちがいない」とか(笑)。仕事をしないでお金をもらったことは一度もありませんけど。あるいは「弱い人の味方にならない人だ」という言葉も。そう言う人から見ると、全部本当のことだと思えているんでしょう。
水野:それらの言葉を受け入れてしまうのですか?
糸井:受け入れたくはないですが、「それは違うんだよ」と言ったところで、思い込んでいる人の考えを変えられるだけの自信が僕にはないです。
当然傷つきますが、傷つくネタは山ほどあって、なんとか誤解を解きたいと思っていると、それがライフワークになってしまうんです。
僕は「みんなにわかってもらいたい」をライフワークにはしたくない。
そうではなく、やりたいことをやる方向に舵を向けます。何か新しいことを広げたほうが、喜んでくれる人が増えますから。
表現者はヘンな生き物
水野:僕の場合は、「みんなにわかって欲しい」という気持ちがまだ強くて……。
たとえば、曲には無名性があったほうがいい。でも、そのことをわかってもらうためにガタガタと説明している自分がいて、結局、無名性と矛盾した行動をしてしまう。
その気持ちをなかなか止められません。
糸井:やはり表現で生活している人は、みんなどこかに弱点や傷が過去にあったりして、そもそもヘンな生き物だと思うんです。
水野さんは詞も書きますよね。
すると、暮らしの中で、これは詞になるかなというネタがいっぱいある。そんな視線の人って、ヘンだと思うんです。そんなこと考えてないで、サッサと飯食えよっていうのがふつうです。
そんなヘンな立場だけれど、じゃあ辞めてしまえるかと言うと、辞められませんよね。だったら、ヘンな場所にいることは仕方がないとして、自分がもっと楽しくなる方法を探すしかないでしょう。
僕の場合、自分が見たものに対して、「わたしもだ!」と反響をいただくことがものすごくうれしくて、救われたという気持ちになります。
僕の言葉で他人が救われたという話が重なったら、ますますうれしいですよね。だから、表現者を辞められなくなり、さらにスタッフとしてサポートしてくれる人たちも増えていく。
辞められないことばかりになっていくんだと思います。
たぶん水野さんは、もう表現者を辞めたい、辞められないをしょっちゅう行き来しているのでしょう。それは僕も同じです。
「もうや~めた」と言っていた時代がけっこうあります。若いころは、自分が飽きてきたとき、飽きないよう頑張ろうという何かがなかったんです。
でも、今やっている「ほぼ日刊イトイ新聞(ほぼ日)」は、辞めるつもりがない仕事です。なぜなら、読んでくれる人、応援してくれる人まで含めて、すべて自分になってしまったからです。
たぶん歌を歌う人にも、そういう部分はあるでしょう。
水野:ある意味、みんなの人生を背負うわけで、けっこう苦しくないですか?
糸井:苦しいけど、うれしくもあります。
子育てと同じで、放棄できない義務感以上に、ちょっと余計に言葉を覚えた、笑いかけてくれた、歩けるようになったとか。それが楽しいのと同じです。
モクモクと入道雲のようなものがあって、この雲がもっと続けばいいのにと思うでしょう。
雲や海の作れっこない遠さに似てくるんです。この広さを畳んでしまうことはできないから、いい方向でどうやって残すかを考えるようになるんです。
水野:そうなんですか。僕は、まだまだ糸井さんの境地にはほど遠い状況ですね。
(構成:栗原 昇、撮影:池田光史)
※明日掲載の「
『寂しさ』をずっと考えてきた」に続きます。