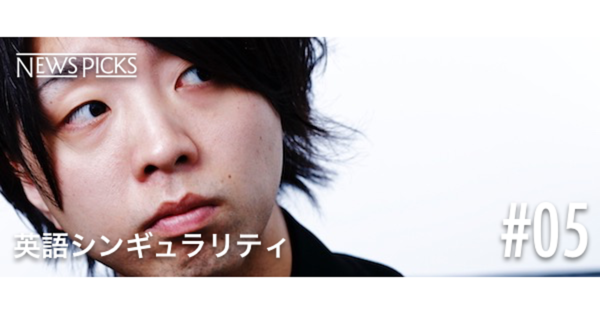【落合陽一】英語学習は不要?ロジックと中身が勝負の世界になる
コメント

注目のコメント
基本的に、中身がないと誰も話を聞いてくれないのはその通り。だが、英語圏でコミュニュケーションをとろうと思った時に、任天堂の社長とかイチローのように、何人だろうが世界中の人が興味を持つような人物を引き合いにだしたところで、凡人にとってはほとんど参考にならない。同時通訳をつけられるような立場の人間にしてもそうである。参考になるとしたら、自分の中身を(世界のみんなが興味を持ってくれるぐらい)磨け、以上である。問題は、英語圏でほとんど自分が興味を持たれていない状況から、どう自分をアピールし興味を持ってもらえるのか、である。スピーチを提供する機会すら与えてもらえない時に、どうその機会をもぎとるか、である。よしんばスピーチの機会を与えられたとしても、その会議の後、夕食会やちょっとしたパーティで見知らぬネイティブの他人とテーブルを囲んだ時にどのように話を展開するか、である。ネイティブ達は、平気でスラングや社会的な文脈がわかっていないと理解できない比喩を多用してくる。こちらがアジアン英語だと分かるとあからさまに興味を失う人たちもたくさんいる。要は、自分の言葉で語れないと、ビジネスチャンスを失うどころか、全く相手にされないのだ。ちなみに、日本に来ているネイティブや欧州人が英語を話すときは、ものすご〜く気を使ってゆっくりと、そして日本人が分かりやすいように言葉を選んで話してくれていることに、みんなもっと敏感になったほうがいい。
イチローも英語が話せるのにインタビューの取材を受けるときは必ず日本語で話します。微妙な表現を話すには母国語が一番、ということで。自分も英語を仕事で使ってますが、その気持ち良く分かります。とりあえず、まず、英語で相手が何を言ってるのか分かることが大事。伝えるのは最悪、ジェスチャーでもいけますからね。