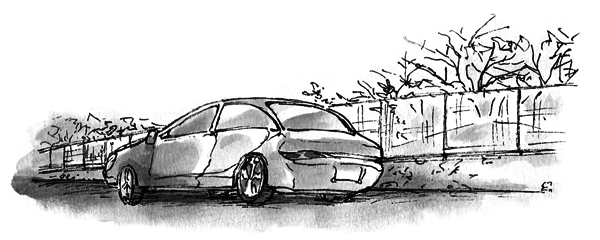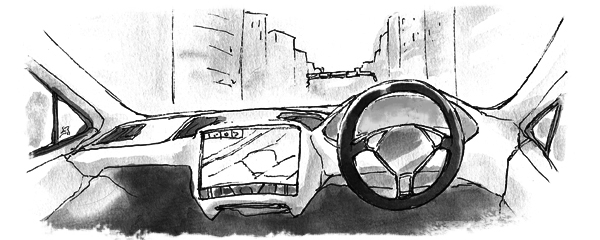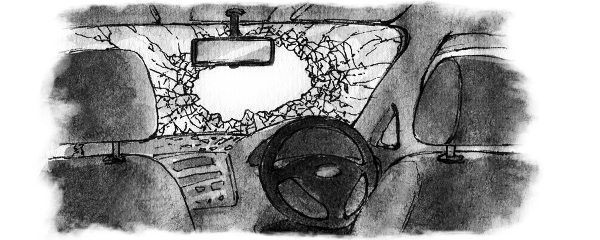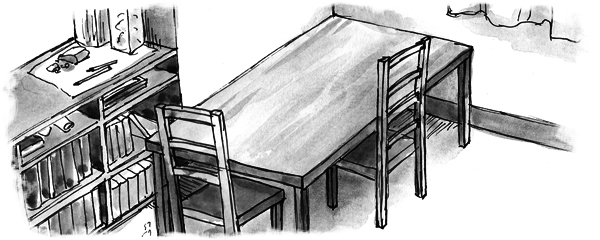【連続小説】「ディスラプション」Season1(中編)一気読み
2016/7/2
7月4日(月)から連続小説「ディスラプション」Season2がスタートします。それに先立ち、昨年公開した「ディスラプション」Season1(全48話)を3日連続で無料公開いたします。
7月1日(金)「ディスラプション」Season1(前編)1~18話
7月2日(土)「ディスラプション」Season1(中編)19~36話
7月3日(日)「ディスラプション」Season1(後編)37~48話
「ディスラプション」Season1
大手電機メーカー勤務の「大企業男」、電気自動車を開発する「スタートアップ男」、2人の間で揺れ動く大手広告代理店勤務の女──。それぞれの視点を通して3人の野望と挫折を描き、安定か夢か、男の価値とは何かを問う。
探り合う人々
午前10時に青山の公園前に行くと、真っ赤な「アクティZ」が止まっていた。
恵理香はクルマについて語れるほどの知識はないが、流れるようなラインがカッコいいと思った。銀色に光るホイールのデザインも変わっている。
「おはよー」
クルマから健吾が現れた。ダークブラウンのレザージャケットを着ている。あたりには誰もいない。
「おはようございます。試乗会に参加する人、ほかにいないんですか」
「平野さんだけだよ」
「えっ」
予想通りではあるが、恵理香は意外なフリをした。健吾はエスコートするように助手席のドアを開ける。
「どこまで走るんですか」
「ヒミツ」
「今日は午後に社内でミーティングがあるんです」
恵理香はつい口走った。本当は変更可能な予定だ。健吾はちょっと残念な顔をした。
「そんなに遅くならないよ。何時まで平気?」
「うーん、2時ごろまでなら」
「けっこうあるじゃない」
健吾の顔がくしゃっとなった。あの笑顔だ。
“門限”など設定しないほうがよかっただろうか。健吾に軽い女だと思われたくない。でも、なるべく長くいたいという葛藤が言わせた時間だ。
そのくせ買ったばかりのシルクの下着を身につけている。もちろん今日、何かがあるとは思っていないが、万が一に備えてだ。
それに特別な下着をつけていると、内側から自信があふれてくる気がする。
「クルマの充電はされてます?」
「されてる、されてる。もし切れそうになっても、地図の雷マークを押すと……」
前面に大きなディスプレイがあり、健吾は長い指でタッチした。恵理香はドキドキする。
「雷マークを押すと、充電ステーションが表示されて一番近い場所がわかる。六本木、丸の内、横浜にもあるから安心して」
「まるでパソコンみたいですね」
「そう。電気自動車は『走るパソコン』とか『走るスマホ』って言われてるんだ。じゃあ、行くよ」
健吾はドライブモードにして走り出す。恵理香がキョトンとしてこちらを見た。シャンプーの香りがふんわり漂う。
「振動がないから走ってる感じがしない! すっごい静かですね」
「エンジンがなくて排気音もないからね。音楽もクリアに聞こえるよ」
ディスプレイにタッチする。
「ネットラジオを流すね。ストリーミングで世界中の音楽を聞ける」
「これはどこの国のですか」
「イギリスのジャズ専門のFM。よく聞いてるんだ」
「そういえば毛利さん、イギリスに留学されてたんですよね」
「うん。ジャズはその頃にハマった」
「なんか部屋の中にいるみたい」
恵理香は曲の流れに身をまかせている。リラックスしてきたようだ。
クールに振る舞いながら、ときどき無防備な面をのぞかせる。心を開かせるには少し時間がかかるだろう。
健吾は“試乗会”の時間を平日の午前中に設定して正解だったと思った。
「ちょっとスピード上げるよ」
アクセルを踏み込む。
「ワーッ」
恵理香は無邪気に声をあげる。
「静かに加速して面白いでしょ。時速100キロに到達するのに数秒。市販されているセダンでは世界最速レベルなんだ」
「すごい……」
女が「すごい、すごい」と笑顔で聞いてくれれば、男はずっと話したくなる。
「急発進、急加速すると、電気の消費量がぐっと上がっちゃうけどね」
「えーっ」
恵理香が笑う。
「高速道路で一定の速度で走れば、エコ運転になるよ」
健吾は高速に入った。
「新しい機能が追加されると画面に表示が出て、ネット経由でバージョンアップできる。簡単なエラーなら遠隔操作で直すこともできる」
「ほんとに『走るパソコン』ですね」
気持ちよく説明しているうちに、鎌倉が近づいてきた。高速を降りて、しばらく運転する。
海が見えてきた。海岸の駐車場にクルマを止めた。
「散歩しよっか」
「はい」
恵理香と砂浜をゆっくり歩く。真冬の太陽は昼だというのに低い位置にあり、日差しは弱々しく海原を照らしている。
突然、恵理香が後方で止まった。片方の靴を脱いで砂をトントンとはらっている。その姿が何ともかわいい。
「ごめん。靴、汚れちゃったね」
「いいんです。あ……」
恵理香がよろけた。とっさに健吾は手を差しのべる。
「すいません」
健吾の顔を恥ずかしそうに見上げる。恵理香の長い髪が潮風にたなびく。あのいい香りが健吾の鼻をくすぐった。
優司はソニップ電機の社員食堂でカツカレーをかきこむと、湾岸のオフィスを足早に出た。
午後から本社の経営企画部に対し、春モデル販売促進キャンペーンについて説明する。
なんとなく胃が重苦しいのは、食べたカツのせいばかりではない。本社勤務の同期と会うのがだるいのだ。
ソニップは部門によって本社までの距離が違う。
本社は東京・丸の内にあり、経営陣が鎮座している。そこから神奈川方面に向かって、マーケティング部や研究開発部と放射状に遠のいていく。子会社は千葉や埼玉、関西、東北に点在する。
「本社からの距離は、学歴とほぼ比例している」と言ったのは、同期の岡崎俊太だ。
「斉藤、久しぶり。ミラーレス、調子いいみたいだな」
会議室でプレゼンの準備をしていると早速、岡崎が話しかけてきた。
岡崎は最高学府の東都大学経済学部出身である。会社派遣でアメリカに留学し、帰国後、経営企画部の係長になった。「同期の出世頭」と呼ばれている。
なぜ文系エリートが理系エリートよりも出世するのか、優司は納得がいかない。
メーカーはモノをつくって稼いでいるのだから、理系エリートが偉くなって当然ではないだろうか。
入社以来、そう思い続けてきたのだが、幸か不幸か優司はマーケティング部に異動になった。
そして気づくと、文系エリートと同じコースを走らされている。そのトップを走る岡崎がうっとおしい。
だから軽くいなすことにする。
「いやー、忙しくなるばっかりだよ。上司は仕事を丸投げするし、俺は毎日、子会社のケツをたたきまくってる」
「そっか。こっちはたたいても言うこと聞かないやつらを相手にしてるからなあ。アメリカや中国、韓国との交渉は、タフじゃないと務まらないよ」
岡崎はわざとらしくため息をついた。
同期の田代愛が通った。たしか役員の秘書をしているはずだ。
髪を束ねてキリッとした印象だが、小柄でぽっちゃりしているのがそそられると、一部の男性社員に人気がある。
「田代、ソニップナインの男と付き合ってるらしいぞ」
岡崎が声をひそめた。
「まさか。本社の女が“子会社”と付き合うわけないだろ」
ソニップナインはカーナビをつくっている子会社だ。
「30過ぎて焦ってんのかもな」
二人は共犯者のように笑った。男が本丸を目指して戦っている間に、女は都落ちしていくのかもしれない。
優司はうっかり岡崎に気を許した。
「そういえば俺、この前、社長賞、取ってさ」
「ああ知ってる。中谷社長、交代するってよ」
「えっ」
「やっぱりテレビがダメになってエレキ事業が復活しないからな。ほかが多少、業績が良くても再建は無理だろ」
ミラーレスの功績を「ほか」の一言で片づけられた。まったくいまいましい。
技術のことを何も知らないやつが本社で偉そうにふんぞり返っていることに、優司はやはり憤りを感じる。
ソニップ電機の社長は文系が続いていた。エレキの復活というなら、技術に精通している人間がトップに就くべきだ。
しかし、岡崎の前で動揺を見せたくない。優司は努めて冷静に聞いた。
「次の社長は誰なんだ?」
「まだ正式発表前だからなあ……」
岡崎はさんざんもったいつけてから口を割った。
「ハロルド・スプリングフィールド」
「誰だよ、それ」
「アメリカ法人ソニップの役員。元テレビプロデューサー」
「は?」
経営陣の考えることはつくづく意味不明だ。
会議室に人が集まっていた。優司は気を取り直してプレゼンを始める。
「みなさん、『カメラ女子』がよく撮る三大被写体をご存じですか」
経営企画の連中を見渡してスライドを映す。
「空、ペット、カプチーノです。この3つをブログやSNSにアップしている女子は、最近『バカ女子』とお笑い芸人に揶揄されています。誰でも撮れるし、見せられたほうも、ふーん……で終わってしまって、話題がまったく広がらない」
クスクス笑いが起きた。
「もっとツッコミを入れたくなってコミュニケーションが広がる、かつソニップのカメラだからきれいに撮れる被写体を提案したい。そこで春モデルでは、『ブサかわペット、撮って送ってね』キャンペーンを企画します」
ブサイクだがかわいい、撮影者の愛情がこもった犬猫の写真を大量に見せていく。
「腹、減ったなあ。昼、江ノ島で食べようか」
健吾は「アクティZ」を充電している。急速充電器が設置されている海岸沿いの自動車販売店から、江ノ島が見えた。
恵理香は優司と来たことがあるのを思い出した。たしか初デートだ。展望灯台に上がり、オレンジ色の夕日を眺めていたらキスされた。
さっき健吾と手が触れただけで電流が走ったのに、どうなってしまうのだろう……。
一瞬の沈黙を破り、健吾は快活に提案する。
「映画の寅さんに出てきた有名な店があるの、知ってる?」
「寅さん、シブいですね」
「そう? 俺、好きなんだよね」
当たり前だが、まだ健吾の好みを知らない。
「そこのどんぶりでも食べて帰ろうよ」
「カエロウヨ」、この一言で恵理香の心を寂しさと安堵が同時に襲った。
結局、健吾とシラス丼を食べただけで帰ってきた。
博通の前に着いたのは、恵理香が告げた“門限”の2時ちょっと前だ。健吾は信用できる男である。だが、信用がこれほど物足りないものだとは思わなかった。
「平野さん、運転しなかったね」
「いいんです。私が運転したら、きっと事故っちゃいますから。試乗会、楽しかったです。ありがとうございました!」
恵理香は社交辞令と思われないように、声のトーンを上げた。
「仕事がなければ、もっとゆっくりドライブできたのに」
「すみません。これから毛利さんに登壇していただくイベントの打ち合わせなんですよ。年明けになりますが、よろしくお願いします」
「年明けかあ……」
健吾は何か言いたげな顔をした。今週末はクリスマスだ。しかし、その話題には触れない。
車窓の向こうの街路を気ぜわしい人たちが行き交う。
「また連絡する」
名残惜しそうな表情で恵理香を見つめ、片手を差し出した。握手しようということらしい。
恵理香も片手を差し出すと、健吾は強く握った。痛いほどにだ。熱くて大きな手に包まれた。
「連絡待ってます」
恵理香は笑顔でクルマを降りる。
「アクティZ」は音もなくゆっくり動き出し、健吾を連れていった。
博通の社内にあるダイニングカフェは、ランチの時間を過ぎても人が絶えない。
社員のクリエイティビティを最大限に引き出すために設計されたという開放的な空間には、さまざまな形状や素材のテーブルと椅子がある。通路の動線も曲線的だ。
1人用のソファで雑誌を読んでいる者や、窓際のカウンター席でノートパソコンを広げている者がいる。
恵理香とデザイナーの久保幸雄は「ファミレスブース」と呼ばれるボックス席に陣取った。ここは背もたれが高く奥行きがあるので、話し声が漏れにくい。
幸雄がデザインしたイベントのパンフレットを恵理香は念入りにチェックする。10人の起業家の写真をコラージュしたものだ。
恵理香は頬杖をついた。視線の先は写真の中の健吾である。
「ステキね」
「何かあった? いつも必ずダメ出しするのに」
ゲイの幸雄が恵理香の様子を怪しむ。ガチムチ系の体にボックス席は窮屈そうだ。
そこへライフスタイル総合研究所の山口芽衣が通りかかった。
「何してんの?」
幸雄を奥に押しやって座った。他部署の人間とのこうした偶然のコミュニケーションを促すために設計されている。
しかし、3人は同期でもともと仲がよく、しょっちゅう会っている。優司と出会ったホームパーティも幸雄が開いたものだ。最近は“彼”と同棲中なので開かない。
「何かあった? 頬杖なんかついて」
芽衣も聞いてくる。芽衣はインド人のコンサルタントと大学時代から8年も付き合っている。だが親が外国人との交際を認めていない。
芽衣自身にも迷いがあるのか、たまに日本人と付き合う。その1カ月ほどの間、インド人を遠ざけてはよりを戻すのを繰り返していた。
幸雄も芽衣も、いわば“1人ダイバーシティ”だから鋭くて繊細である。
「新しい男、誰?」
芽衣がいきなり尋ねた。
「そんなのいないって」
恵理香の言葉を無視して、芽衣はテーブルの下を見る。
「新しい変わった靴。砂で汚れてる。絶対、何かあったよね」
恵理香は降参した。隠してもどうせこの2人にはバレるのだ。写真の健吾を指した。
「いい男じゃないの!」
幸雄が叫んだ。
「ワケのわかんないスタートアップ男よ」
「出た! 安定志向。もっと直感に従いなさいよ」
「だけど現実も大事よねえ」
芽衣は健吾の会社の業績をパソコンで調べ始めた。
恵理香に言わせれば、3人とも直感と現実の狭間で揺れていると思う。
浮かび上がる事実
優司はオフィスの自分の席でハンバーグ弁当を食べている。今朝、出勤途中にコンビニで買ってきたものだ。
今日はマーケティング部の長谷川部長と面談があり、異動や昇格もその場で告げられる。部員は部長とアポを取った順に会議室へ行くため、自分の順番を席で待っているのだ。
以前、取材を受けた情報誌の副編集長が「社内でコンビニ弁当を食べているようなやつは出世しない」と言ったのを思い出した。人脈がなく、視野が狭い人間という意味らしい。
だが、のちにその副編集長から異動のあいさつメールが来た。署名にはカタカナの奇妙な部署名と肩書が載っていた。
聞くところによると、ろくに仕事もせず、経費で会食と旅行三昧だったのが上層部の耳に入り、部下のいない新設の部署に飛ばされたという。「コンビニ弁当」は自分を正当化する話だったのだろう。
前田係長が面談から戻ってきた。彼の動向次第では自分が係長になるかもしれない。優司は期待を悟られぬように尋ねた。
「どうでした?」
「いやー、異動だよ。総務に行く」
どうして?と言いかけたとき、トゥルル、トゥルルと内線電話が鳴った。渡瀬綾の席だ。次の面談は綾のはずだが、ランチに出かけたまま戻っていない。
優司は舌打ちして電話を取った。
「もしもし……いえ、私は斉藤です。渡瀬は席を外していまして……。はい、すぐに行かせます」
綾の携帯電話にかけるなり、優司は怒鳴った。
「いつまでメシ食ってんだよ。今日、面談だろ。部長が呼んでるぞ」
「ああ、女性誌の編集者とランチしてたんですよ。部長に電話入れときます。何なら斉藤さん、先にどうぞ。私はその後でいいですから」
悪びれる様子もなく、プツッと切られた。
まったく、あいつの無礼さとルーズさは目にあまる。これまで女だと思って手加減してきたが、きつく叱ってやらなければならない。
それよりも、もっと従順で気の利く後輩が異動してこないものか……などと考えながら会議室へ急いだ。
長谷川部長の前で目標設定シートを広げる。個人目標は達成できた。部署全体の課題と改善点として、綾の勤務態度についてもちらっと伝えたが、
「こらえることも必要だ。がんばってくれ」
と妙な励まされ方をした。昇格も異動もなく、面談はあっさり15分で終わった。新しい係長が誰なのかも教えてくれなかった。
30分後、綾がハイヒールをつかつかと鳴らしてオフィスに戻ってきた。優司の真横に立つ。
「斉藤さん、私、係長に昇格しましたんで」
「係長?」
声が上ずった。
「どこの?」
「ここのです」
絶句して立ち上がった。が、全身の血が逆流してふらつく。
まさか後輩に抜かれるとは思ってもみなかった。ましてや女に負けるとは……。こんな人事は何かの間違いではないか。
「本当に?」
やっと声が出た。
「斉藤さん、私、『カメラ女子』が来てるって話しましたよね?」
何のことを言っているのかわからない。
「女の子も本格的な写真を撮りたがってるのに、一眼レフは大きくて重くて持ち歩けないって。私の意見を勝手に取って自分の手柄にしないでくださいよ」
その会話はなんとなく覚えているが、企画に膨らませて実行したのは自分だ。そんなことを綾は恨んでいたというのか。
周囲が息を潜めて様子をうかがっている。
「外で話そう」
肩に手を置くと、綾は肩をブンと回して振り払った。
「いいえ、ここで話しましょう。これからは私が上司ですから、あなたの指図は受けません」
その夜、前田係長に連れていかれたバーは、ジャズが重低音で流れる、おそろしく照明の暗い店であった。
メニューも読みづらいほどなのに、マスターは黒いサングラスをかけている。
カウンター席で前田はマッカランのロックをちびちびやる。
「なんであいつが! 俺が結果を出したのに……業績に貢献したのに……」
優司はぐいっとあおり、グラスをたたきつけるように置く。さっきから堂々巡りの問いを続けている。
「前田さんだって、どうして総務に異動なんだか」
前田は灰皿を引き寄せ、タバコに火をつけた。喫煙者とは知らなかった。
「ずっと禁煙してたんだけどなあ」
煙を肺まで入れるように深く吸う。
「前は4階に広い喫煙ルームがあったのに、1階の狭い一角に追いやられただろう。エレベーターでいちいち降りるのが面倒くさくて、禁煙した人間が多い。俺もそうだった」
タバコを吸わない優司は内心、喫煙者が1日に何度もタバコ休憩を取ることを快く思っていない。非喫煙者より生産性が悪いからだ。
「まだ吸ってる人、いますよね」
「『人事はタバコ部屋とゴルフ場で決まる』って言うだろう」
「聞いたことないですよ」
「一昔前の常識だ。渡瀬はタバコも吸うし、ゴルフもやる。役員連中にかわいがられてる」
「役員って、この間も言ってましたね。誰かの愛人なんですか」
「大江弘之さん」
前田は躊躇なく答える。
「えっ、大江さんって、テレビの開発部長でしたよね。俺、新人だったから話す機会はほとんどなかったですけど」
優司は宴会の席で大江を遠巻きに眺めていたことを思い出した。
「大江さんは次期副社長だ」
「えーっ! まだ若いでしょ」
「49歳、役員30人ごぼう抜き」
「へえ、すごいですね」
「切れ者で恐れられているよな。子会社の社長もやってる」
カーエレクトロニクス事業のソニップナインである。
「でも信じられないですよ。大江さん、あんなの愛人にするかなあ。渡瀬って男勝りじゃないですか」
「太鼓持ちの男より、生意気な女が好きな上司もいる」
綾は大江に猛アピールしただろうのか。俺のことを貶めながら……。優司は目の前が一層暗くなった。
自分のほうが大江と近い位置にいたのに、とんだ場所で出し抜かれたのが悔しい。
「そんなことで人事が決まるんですか」
「そんなことがサラリーマンは大事なんだよ。結果を出せば出世できるほど単純じゃない。正攻法で勝てれば誰も苦労しない」
前田は自分を諭すように言う。グラスを揺らして氷を鳴らす。カウンターの片隅にいたマスターに同じものを2杯頼んだ。
優司はどれだけ酒を飲んでも怒りが収まらなかった。前田と別れた後、恵理香のマンションに行く。
こういう日は女に慰めてもらいたい。だが同情されたくはなかった。
恵理香がボクサーパンツを履いている日は、前戯がまるで格闘技のようになる。
今夜は早々に恵理香を裏返しにした。脱がしてしまえば女のしなやかな肉体が現われる。
くびれたウエストに片手をかけ、いきり立つものを押し込んだ。恵理香は身じろぎもせずシーツに突っ伏して、白い腰だけをこちらに向けている。
恵理香には言ったことがないが、この角度から見る眺めが好きだ。征服感でいっぱいになる。
片手で施すように胸をつかみ、もう片方の手で罰するように尻をつかむ。テンポを上げると、恵理香は横顔を見せて目を閉じた。
襞が男にまとわりつき、波打ってくる。優司はたまらず激しく連打し、最後に深く突く。抱えていた怒りは白い液となって暗闇に放出される。
昨夜はクリスマスイブだというのに、優司はまた深夜に酔っぱらって部屋に来た。
相当イラついていたと、恵理香はコーヒーを淹れながら思い返す。
優司をそろそろ起こさなければ。これから箱根の温泉に行く約束だ。宿は父親の勤務先の保養所だという。
「箱根に保養所って集中してるじゃん。不況で手放した会社も多いけど、三友重工はまだ持ってる。そこらのホテルより豪華で安いから、昔から家族でよく利用しててさ」
そう屈託なく話していた。クリスマスに恋人を連れていくのは手抜きなのか鈍感なのか、恵理香は測りあぐねている。
だが、たぶん育ちの良さからくる悪気のない鈍感さなのだろうと片づけた。
優司の父親は財閥系の三友重工で重役をしているらしい。母親は専業主婦で、3歳下の弟は大学病院で外科医をしている。
つまりは相当なエリート一家で、サラリーマンとしては裕福な家庭で育ったのだ。
両親から愛情と教育を当たり前のようにふんだんに与えられてきたに違いない。
「いったん家に戻って着替えてくるよ。荷物もあるからクルマで行こう」
優司の自宅は横浜の郊外にある。
「恵理香もちょっと寄っていけば」
と軽く提案された。2年付き合っているが、家に行ったことはない。
「土曜だよ。ご家族がいるでしょう?」
「別にいいじゃん。俺がいつも恵理香んちにいるのも知ってるから」
保養所といい、恵理香を家族の一員とみなしているのだろうか。
それにしても31歳の男が実家暮らしなのは、恵理香の不満の1つであり、羨望の対象でもある。
「1人暮らししないの?」
と聞いたことがある。優司はこう言った。
「家にいたほうがラクじゃん。家賃はいらないし、カネも自由に使える」
それはよく雑誌に書かれている「男が結婚に踏み切らない理由」だから、恵理香はムッとした。それに優司が得ているメリットは、恵理香が自力でまかなっているものである。
優司の家は、かつて私鉄沿線が売り出した新興高級住宅地にあった。敷地面積はさほど広くはないが、庭もある。
「まあ、恵理香さん」
母親の美奈子が出迎えた。好奇と不信の目を向けられ、恵理香は少し気を張る。
「優ちゃんったら、突然なんだもの」
優司は2階の自分の部屋にさっさと行ってしまった。
「あなた、恵理香さんよ。ほら、優司の……」
父親の和彦はダイニングテーブルで新聞を読んでいた。
「はじめまして、平野恵理香です」
「いらっしゃい」
老眼鏡をずらす。威厳のある風貌だ。
「ちょうど紅茶を淹れていたところなのよ」
テーブルの上に、バラの花の部分だけを切って水に浮かべた皿がある。
テーブルクロスの四隅には、熊の形をしたゴールドの重りが付いていた。ピンと張るためのものだ。
センスがいいのかよくわからない。上流を目指しながらもなりきれない中途半端さを象徴している気がする。
美奈子はウェッジウッドのティーセットを厳かに置き、和彦の隣に座った。恵理香の正面に2人、面接のような形になる。
「いつも優司がお邪魔して悪いわね。ご実家はどちらでいらっしゃるの?」
「茨城です」
「だからお一人住まいでいらして……。親御さん、心配でしょうね」
恵理香は曖昧にほほ笑んだ。
「茨城って日の丸製作所のお膝元ね。お父様は日の丸の方とか? あなた、大きな工場があったわよね」
「ああ」
和彦はぶしつけな妻を制すわけでもない。
「いえ……不動産関係で」
「不動産関係、まあ、そうなの。地主さん、とか?」
「いえいえ……」
どうやって切り抜けようかと考えていたら、優司がリュックを背負って降りてきた。
「準備オッケー。行こうか」
「うん」
優司は父親が所有する国産高級車「スローン」のエンジンをかける。
ブオンと音がして振動するのを、恵理香は助手席で体感した。重厚感のある内装は、「アクティZ」の近未来的な軽さとはまるで違う。
これから行くコースはこの間、健吾とドライブしたコースと途中まで同じだ。
優司のコースの先には古いけれどもどっしりした大企業の遺物が建っている。一方、健吾のコースの先には霧がかかっている。
2つのコースを同時に走ることはできない。しかし、恵理香はまだ決断できないでいる。
「優司のお父さんとお母さん、ハイソな雰囲気だった」
皮肉にならないように表現に気をつけたが、優司は褒められて当然という顔をしている。単に家や家族を自慢したかったのだろうか。
「恵理香、正月はいつ帰省するの?」
運転しながら聞いてくる。
「まだ決めてない」
それは嘘である。いつも元旦に帰り、1泊だけして東京に戻る。
「そんなに遠くないのに、あんまり帰省しないよね」
優司は不思議がった。帰りたくない理由は、結婚話が出たら話そうと思っている。
生じる亀裂
恵理香は大みそかを1人で過ごすことにしている。食材を多めに買って料理をしながら1年を振り返り、遠く離れた世界に行ってしまった家族を想う日なのだ。
人の気配がなくなるマンションの一室で、胸が痛くなるほどの孤独に自ら追い込み、じっと耐える。まるで修行僧のようだが、恵理香はこの苦痛が嫌いではない。
これを乗り越えれば強くなり、真っさらな自分に返れる気がするのだ。
恵理香が5歳のとき、父親が死んだ。
どうも記憶がぼやけているのだが、年の瀬に父の運転するクルマの後部座席に恵理香が乗っていて、荷物が振動で下に落ちた。
「あっ」と恵理香が声をあげると、父が後ろを振り向いた。
次の瞬間、フロントガラスが粉々に砕け散っていた。あとは救急車のサイレンの音と、血だらけの父の姿しか覚えていない。
父の死後、母の智子は准看護師の資格を取り、母子寮のある総合病院で働き出した。稼ぐために夜勤シフトを積極的に入れていたようだ。
恵理香が小学校高学年になり、1人で留守番ができるようになると、スナックでも働いていたらしい。
「平野さんのお母さんはスナックヅトメ。ミズショウバイだから遊んじゃダメ」
親に注意された同級生が、一斉に恵理香を避けるようになった。同級生も自分も「スナック」が何かをわかっていなかった。
母に意味を尋ねると、ひどく悲しい顔をして、
「ごめんね」
と恵理香を抱きしめた。その肩が震えていたので、恵理香は聞かなければよかったと後悔したのを覚えている。
翌日から母は正看護師になるための勉強を始め、1回で合格した。そんな母が恵理香は誇らしかった。
忙しく働く母の娯楽は本を読むことだ。図書館で借りてきて、夜勤や家事の合間に読み進める。
やがて難しい漢字も読めるようになった中学生の恵理香に、面白かった本を薦めるようになった。
返却期限があるので急いで読む。感想を母と娘の少ない時間に伝え合う。それが楽しくて「読書ノート」をつけ始めた。
母が先に書き、次に娘が書く。成長するにつれて、娘が先に書くことが多くなった。
「国語の先生になろうかな」
高校生になった恵理香が相談すると、母は「手に職をつけなさい」と助言した。女手一つで子どもを育ててきただけに、その言葉には重みがあった。
恵理香は理系を選択し、東京の国際宇田塾大学情報科学科に進学する。とりあえず英語とプログラミングを身につけようと考えたのだ。
もちろん奨学金制度を利用するつもりだったが、合格を知らせると母は1冊の通帳を出した。
「これ、恵理ちゃんに」
「こんなに?」
そこには4年分の学費と生活費を払えるだけの金額が記されていた。わが母ながら感心したものだ。
そんな母を1人残していくのは忍びなかったけれども、母は優秀な娘をもって鼻が高かったようだ。東京に発つ日、笑顔で見送ってくれた。
就職はぼんやりとメーカーをイメージしていた。しかし、大学2年のときに先輩に誘われ、博通でアルバイトをして気持ちが動いた。
広告代理店は言葉のセンスや教養が問われる。英語もプログラミングも生かせそうな部署があった。
ここなら自分の「好き」と「スキル」を生かし、新しい力を発掘できそうだ。ユニークで最先端な人たちとも切磋琢磨したい。
考えてみれば、母は狭い世界しか知らず、食べていくために限られた選択肢の中から看護師を選ぶしかなかった。
人生の可能性はなるべく広げておいたほうがいいのではないか。恵理香はそう判断して博通に決めたのだった。
それなのに、広い世界をひらひら舞っているうちに27歳になり、男にすがっている。なぜこうなってしまったのだろう。
内定を母に電話で報告するとき、「手に職ではない」と怒られるかと思ったが、意外なほど喜んでくれた。
「博通って有名な広告代理店でしょ。お給料も高いんじゃない?」
「まあ、そこそこ」
「あっ、女優の桜井かれんのダンナがたしか博通よね」
看護師仲間の間では芸能ネタが共通の話題だから、母も詳しい。
「CMプランナーの中田さんね。大御所すぎて雲の上の人だけど」
「芥川賞作家の溝口颯太郎も博通出身よ。『翡翠の森』、読んだ?」
「読んだ読んだ。すっごい面白かった」
実家にいた頃のように本の感想を言い合い、懐かしくなった。
母ひとり子ひとりなのに、故郷を離れて東京で就職する親不孝……。罪悪感にかられていると、母が言った。
「恵理ちゃん、近々帰ってこられる? ちょっと話したいことがあるんだけど」
「何? 気になるから今話してよ」
「電話じゃ話しにくいから」
週末、実家のマンションに帰省すると、
「お母さん、再婚しようと思うの」
と報告された。恵理香は衝撃を受けた。母が「女」を復活させたことにだ。
当時、母はまだ48歳だったから、父の死後に恋愛の1つや2つ、あったかもしれないが、それまで幸い気づかなかった。
母から夫を奪い、長年、苦労させてしまった負い目はある。母は自分を恨んでいるのではないかと思ったこともあった。
母には幸せになってほしい。簡素なダイニングテーブルの上で毎日孤独にご飯を食べて老いていくのは、娘としてつらい。
それでも、母の再婚に葛藤があった。
「相手はどういう人?」
「病院の患者さんだった人」
「何歳?」
「ひと回り年上、60歳」
「えっ、そんなおじいさんと……」
「おじいさんってほどじゃないわよ」
「何してる人?」
「日の丸製作所の部長さんをしていたんだけど、定年になったの」
死んだ父は若い頃に職をいくつか変えた後、不動産会社の営業マンになったと聞いている。
「休日が普通の人と合わない者同士、くっついたの」
と母が照れながら話してくれたことがあった。
「その人、お金でもあるの?」
「お金なんかいらないわよ。お母さん、自分で稼げるんだから」
「だったらなんで?」
その男は定年退職後、腰椎の椎間板ヘルニアが悪化して手術することになった。
母が担当看護師になり、「手術には家族の同意書が必要」と告げると、困り果てた。
5年前に離婚して、息子と娘は東京と大阪で独立している。2人とも忙しいので、わざわざ呼び寄せたくないという。
どうにか連絡させて、娘がやって来た。手術に付き添ったが、仕事があるからとすぐに帰ってしまった。
「康介さんに頼まれて、こまごましたものを売店に買いに行ってあげたり、子どもの話をしたりするようになったのよ」
康介という名前なのかと、恵理香は母の再婚相手を急にリアルに感じた。
「手術して老後が怖くなったみたいで、そばにいてほしいって言われて」
「要するに寂しいもの同士、くっつくってことね。私が地元で就職しないから?」
つい強い口調になってしまう。
「そりゃあ寂しいけど、それ以上に恵理ちゃんが自立したのがうれしいのよ。でも、いつかお母さんのことが重荷になるときがきっと来る。娘の負担にだけはなりたくないの」
「まだ若いんだから好きなことして人生楽しめばいいじゃない」
「旅行やお稽古事もしてみたけど、そんなに楽しくないのよ」
母は苦笑する。
「やっぱり働くのが好きだって思った。人の世話を焼いて必要とされるのが幸せだし、家族がいたらもっと幸せね」
大学生の恵理香には、ずいぶんこじんまりとした幸せに思えたものだ。母の気持ちをおぼろげに理解したのは、就職して数年経ち、働く喜びとしんどさを実感してからである。
間もなく母はマンションを引き払い、安井康介の家に引っ越した。
恵理香が訪ねていくと、母と康介が並んで出迎えた。康介は恰幅のいい男だったが、まだ若い母とは釣り合わないように見えたのは娘の欲目だろうか。
玄関は知らない家の匂いがした。家具は別れた妻が住んでいた頃のものをずっと置いているらしい。
居間の白々とした蛍光灯の下で、母は恵理香が見たことがない赤い口紅を塗っていた。
このとき、恵理香は「実家」を失ったことを知った。もう「ただいま」と言って帰れる場所はないのだ。
今年の元旦も、よそよそしい家で母のつくった雑煮とおせちを食べた。
明日には東京に戻る。「帰る」ではなく、「戻る」だ。東京の自分の部屋は「家」という感覚がない。寝て起きるだけの空間である。
恵理香は安住の地がほしかった。たしかなものがほしい。それを求めてさまよう旅人になる。
優司は弟が正月に帰ってくるたびに、母が普段よりはしゃぐことに気づく。
「永ちゃん、薄着じゃ風邪ひくわよ」
と医者の永司に注意してセーターを羽織らせたりする。かわいくて仕方ないのだ。
優司は私立の中高一貫校から東都大学を目指していたものの、不合格であった。
それでも一流私大の慶西に受かったのだから、親の体面は保ったと思ったのだが、違ったようだ。
東都大出の父は永司に「お前は医者になれ」と言い出し、母は勉強に集中できる環境づくりに全力を注ぎ始めた。
永司は親の期待に応え、東京聖医科大学に合格する。
合格発表の掲示板の前で永司が胴上げされる写真が「週刊マンデー」に載り、両親は何十冊と買い占めて親戚に配った。
都内の大学病院で外科医をしている永司は、買い物をする暇もないほど激務だ。
母は定期的に永司の服や日用品を買い、永司のマンションへ掃除に行っている。
そのたびに、
「洗面所に女性のアクセサリーが落ちてたわ」
「マンションの玄関前に女の子が思いつめた表情で立ってたわ」
などと心配そうに報告する。優司はわざとからかった。
「医者になったら、どんな男でも女が殺到するよ。永司なんか若くてまあまあイケメンだから、婚活パーティーとかに行けば女が突進してくるんじゃないかな。その前に、まわりの看護師がほっとかないよ」
すると案の定、母は顔をしかめるのだ。
その夜、久しぶりに家族4人がそろい、水入らずで正月料理を囲んだ。
「永ちゃん、学会で手術の最新技術を発表したんでしょ。お父さんに話してあげたら」
母はかいがいしく永司の好物を皿に取り分けてやる。
だが永司は口数が少なく、箸も進まない。しきりに父と母のおちょこに日本酒を注いでいる。
父は上機嫌だ。
「お前たち、今年いくつになる?」
「俺は32歳」
「僕は29歳」
「いい年だな。そろそろ結婚を考えたらどうだ」
「優ちゃん、クリスマスに彼女を連れてきたのよ」
酒をあまり飲めない母は顔が赤くなっている。
永司は神妙な顔で箸を置いた。
「話があるんだけどさ」
咳払いをして座り直した。
「僕、結婚するから」
両親は驚いた。もちろん優司もだ。
「誰と?」
母が尋ねた。
「同じ病院の看護師」
「やめてちょうだいよ! もっといい人、いくらでもいるでしょう?」
手塩にかけて医者にした息子を看護師ごときに持っていかれるのが許せないのだ。
母が看護師に少なからず差別的な感情を抱いているのは、永司も知っている。
「年は?」
父が質問した。
「38歳」
「えっ、10歳も上?」
母が信じられないという顔をする。
「そんなの絶対に認めないから! 結婚したら縁を切るわ!」
「認めるも何も妊娠してるんだ。今、4カ月」
ひいっと母が悲鳴をあげた。父はうーん……と低くうなったきり黙ってしまった。
優司は永司の背中をぽんぽんとたたき、2階へ上がらせる。永司の部屋は、大学を卒業して出ていったときのままにしてあり、母がときどき掃除している。
「お前、ナースロックには気をつけるって言ってたじゃないか」
「ナースロック」というのは、看護師が医者と結婚に持ち込むために使う技のことだ。「今日は安全日よ」と言って避妊させず、行為の最中、腰に両足を回してロックする。
これは何年か前に永司から聞いてゲラゲラ笑った話である。
「兄貴、そんなんじゃないんだ。彼女のことは本当に好きだから結婚したいんだよ」
永司は相手の看護師がいかに献身的に自分を支えてくれるかを語る。
「看護師が献身的なのは当たり前だろ。とくに医者には」
優司がちゃかすと怒った。
「彼女は医者だろうが身寄りのない貧乏な患者だろうが、誰とでも分け隔てなく接する優しい人なんだ。そこを僕は尊敬してる」
優司には、世間知らずの弟が年増のナースの策略にはまったとしか思えない。
「なあ、4カ月ならまだ堕ろせるんじゃないか」
「いくら兄貴でも言っていいことと悪いことがあるよ!」
永司は怒鳴った。
「誰が何と言おうと僕は彼女と結婚する。そして温かい家庭をつくる! だいたいお母さんはなんであんなに看護師を見下すんだよ。お父さんの地位を自分の地位と勘違いしてて、僕が医者になったら今度は自分が医者みたいな顔をしてるじゃないか」
「だけどソニップの社員みたいな顔はしないよ」
優司は寂しく笑ったが、永司は否定した。
「うちの家電、全部ソニップでそろえてるじゃないか」
たしかにそうである。母はテレビもパソコンもすべてソニップ製品に買い換えた。
階下で母がさめざめと泣く声が聞こえてくる。
優司は恵理香と結婚しようと思った。4つ年下で一流大学卒、博通に勤務していて、おまけに美人だ。
母も父もきっと喜ぶに違いない。1週間前、バタバタ家に連れてきたときの恵理香の印象は、まあ良かったみたいだ。
本当は何か肩書がついてから結婚したいと考えていた。しかし後輩の綾が係長になり、もはや格好がつかないのは一緒である。心機一転頑張るしかない。
恵理香をきちんと両親に紹介するのはいつにしようか。優司はカレンダーを探した。
*明日のSeason1(後編)19~36話に続く。
(イラスト:永井結子)
*7月4日(月)からSeason2がスタート。日曜日をのぞく毎日公開(有料)。