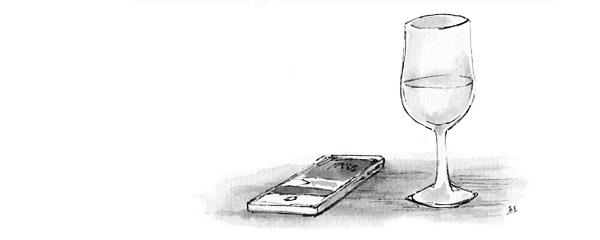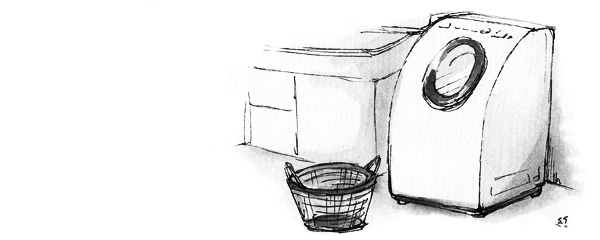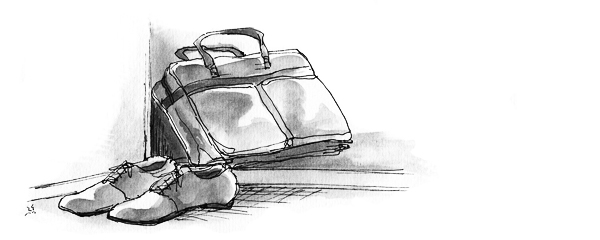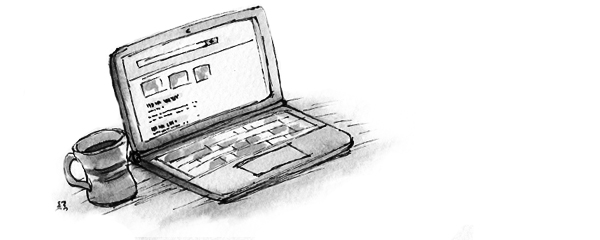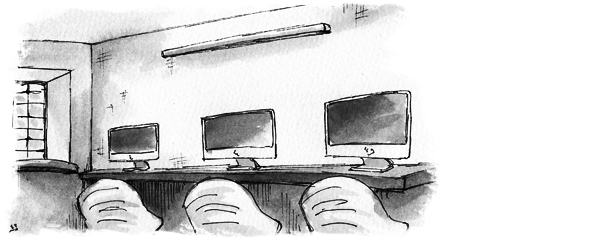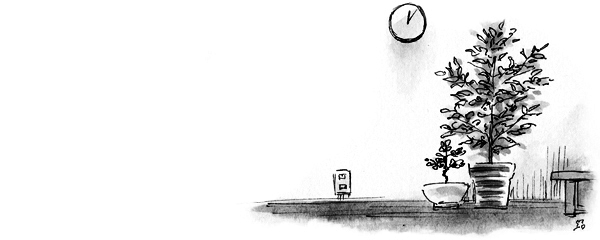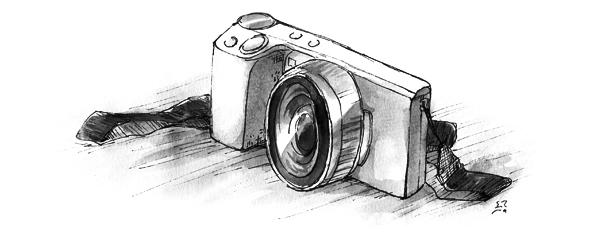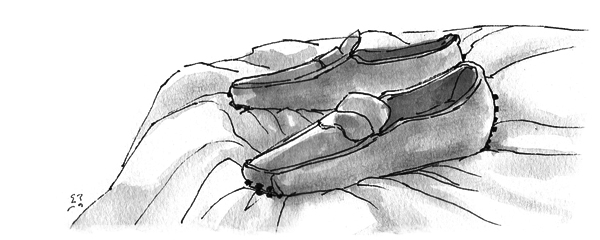【連続小説】「ディスラプション」Season1(前編)一気読み
2016/7/1
7月4日(月)から連続小説「ディスラプション」Season2がスタートします。それに先立ち、昨年公開した「ディスラプション」Season1(全48話)を3日連続で無料公開いたします。
7月1日(金)「ディスラプション」Season1(前編)1~18話
7月2日(土)「ディスラプション」Season1(中編)19~36話
7月3日(日)「ディスラプション」Season1(後編)37~48話
「ディスラプション」Season1
大手電機メーカー勤務の「大企業男」、電気自動車を開発する「スタートアップ男」、2人の間で揺れ動く大手広告代理店勤務の女──。それぞれの視点を通して3人の野望と挫折を描き、安定か夢か、男の価値とは何かを問う。
結婚向きの男
「少し遅くなるよ」
斉藤優司から平野恵理香のスマートフォンにメールが来たのは、金曜日の夜11時を少し回った頃だ。
優司が遅くなるのは最近、珍しくない。恵理香はかすかにホッとしてノートパソコンを開き、別の男の名前を検索した。「毛利健吾」──。
優司が勤務するソニップ電機は、2010年の今年も赤字が続いているらしい。業績不振の主な原因はテレビ事業だ。優司はマーケティングの担当だが人員が減っている中、この12月も残業が多い。
金曜夜に恵理香のマンションにやって来て、週末を一緒に過ごすという2人のパターンが崩れ始めていた。
といっても、大手広告代理店の博通に勤める恵理香の生活も変則的である。
今夜は技術系のWebサイト「テックNEWS」の編集長、竹井剛に呼び出されて会食だった。来年早々に開催するイベントの主催者だ。
デジタルメディア局の恵理香は先日、営業に連れられて、竹井にイベント企画を提案した。
「若者に人気のあるスタートアップの社長を何人か集めてイベントを開きませんか。SNSを使って拡散が見込めますし、イベントの記事を掲載すればページビューや会員登録数も増えますよ」
竹井が指定してきた西麻布のバー「Zero」は駅から歩くには遠く、タクシーを使わなければ行けない距離にある。
後部座席で億劫な気分と戦っていると、メールが送られてきた。
「平野恵理香 様
入口で暗証番号を入力して。3939E。会員制の店です。
竹井剛」
住宅街にあるバーは、入口までの通路の両側がステンレスの壁になっている。うっかり見落としそうな低い位置に真四角のくぼみがあり、その奥にマンションのオートロックのようなボタンがあった。
こういう店が今、流行っているのだろうか。恵理香はおそるおそる暗証番号を押した。
「サンキュー、サンキュー、エンター」
静寂の中でウィンと鈍い音が鳴り、ドアが左右に割れた。
黒服の男が「ようこそ、お待ちしておりました」と現われる。案内されて真っ暗な階段を上がった。
「こちらで竹井様がお待ちです」
「やあ。ここ、わかりにくかったかな」
「はい、ちょっと」
竹井は先にワインを飲んでいた。
「わざわざ行きにくいところに店をつくってるんだよ。来る人を選ぶんだ。IT企業の社長がよく使ってる」
恵理香は個室を見回す。IT企業の社長はこういう場所で夜な夜な飲んでいるのだろうか。
オーク素材の大きなテーブルはいかにも高級そうだが、ファブリックのソファと数個のクッションは柄と素材がちぐはぐである。
恵理香は違和感を覚えた。だが、率直な感想を口にすると恥をかきそうだ。
おそらく「シャビーシック」というスタイルで、あえてみすぼらしい感じを出しているのだろう。デザイナーの友人が「トータルコーディネイトが、一番センスが悪い」と言っていた。
だから恵理香は、
「ステキなお店ですね」
とだけ言ってコートを脱いだ。
明るい色のカシミアのセーターを着てきて正解だった。ほの暗くやわらかい間接照明は、恵理香のバストラインを品良く浮かび上がらせているはずである。
クライアントの男に媚びているのではない。上質なものを着こなしていないと、仕事ができない人間だと判断されてしまうことがあるのだ。いわば衣装は武装である。
竹井は満足げな顔で、黒服の男にオーダーした。
恵理香はテーブルの上に資料を広げて説明を始めた。
「イベントに登壇していただく10人の起業家はこの方々です。告知したその日に参加申し込みの定員オーバーになったんですよ」
「それはうれしい誤算だな」
49歳にしては白髪が目立つ。「テックNEWS」は直販誌を出しているが、部数が激減しているという。それに伴い、Webに力を入れていた。
「キミが今回の企画を持ち込んできたとき、正直、こんな若い子に何ができるんだって期待してなかったよ。でも、あんまり熱心にプレゼンするから、一度任せてみる気になったんだ」
「私、若くなんてないですよ。もう27ですから。会社では新入社員の子におばさん扱いされてます」
恵理香はシャンパングラスをゆっくり傾けて、冷えたクリュッグを飲んだ。のどに竹井の視線を感じた。
「27なんて、一番いい時じゃないか」
おそらく27歳でも35歳でも、「一番いい時だ」と女に言うのだろう。
竹井の膝がいつの間にか恵理香の膝に当たっている。それをあからさまに避けるでもなく、恵理香は足を組み替えるふりをして離した。
仕事先でのさまざまな誘惑を、相手のプライドを傷つけないようにかわすのも、広告代理店の女が仕事をするうえで身に付けるべきテクニックである。
とにかく広告費をたっぷり使わせて、長く継続してもらわないといけない。
暗い階段を下りるとき、竹井は危ないからと恵理香の手を取った。
「もう一軒、行こうよ」
誘いをやんわり押しとどめ、竹井を先にタクシーに乗せる。バタンとドアが閉まった。
恵理香はニッコリ微笑み、深々とお辞儀をする。発進音が遠ざかるまで、その状態で見送った。新入社員の頃、先輩から教わった礼儀である。
電車を乗り継ぎ、吉祥寺駅で降りた。
恵理香が住む1LDKのマンションは徒歩12分の立地にある。途中、深夜まで営業しているスーパーに寄り、冷蔵庫の中にあるものを思い出しながら食材やミネラルウォーターを買う。
家に着くなり、洗濯機を回してシャワーを浴びる。
平日は疲れているので、家事は週末にまとめてやりたい。しかし週末は優司が泊まっていくので、普段からこまめに掃除や片づけをしておかなければならなかった。
それは恋人がいるからこそ課せられる甘美な義務というものだ。
恋人がいない時期は、義務がない代わりに生活全体に張りがなくなる。平日は仕事に追われ、週末は昼過ぎまで寝ているか、たまった家事をこなすだけで終わってしまう。
その状態が長引くと、今度は習い事などを始め、自ら義務を課すことになる。
恵理香は時間を無為に過ごすのが嫌いなので、そうしたスキマ時間を有効活用してきた。英会話に磨きをかけ、簿記を勉強し、Webデザインを学んだ。テニスやゴルフのスクールにも通った。
習い事で得た知識やスキルは、仕事にもそこそこ役立っている。
仕事関係以外の友達ができたのも収穫だ。レッスン後にお茶をしたり飲みに行ったりするのは楽しい。広告代理店は一般的な企業とはかなり違うので、いろいろな会社の内情を聞くのも新鮮であった。
しかし何か埋められないものがあることを認めざるをえない。
友達になった女たちで、心の空洞を埋めようとしている者はすぐにわかった。体のどこかから過剰なエネルギーが漏れ出ているのだ。
30歳過ぎで独身だったら、だいたいそうである。おそらく欠落感を抱えているのだろう。
たとえ恋人がいても、自分が望む頻度で会えないような男と付き合っている女は、どこか無理をしている。相手に執着しすぎないため、あるいは“輝いている自分”を男にアピールするために習い事に熱中しようとしていた。
恵理香も商社マンや外資系コンサルタントと短い期間付き合ったときは、歪んだエネルギーが出ていた気がする。
そんな空疎な充実感を、優司と付き合ってからの2年間は自覚せずに済んでいた。それだけでも優司は価値ある男かもしれない……。
いつの間にか乾燥機が止まっていた。回っている間に眠ってしまうほど静かなのだ。
ボーナスで買った乾燥機は、ソニップ電機の製品である。優司と一緒に量販店に行って選んでもらった。
「なんだかんだいって家電はうちがいいよ。品質が違うし、センスもいい。韓国製の家電が家にあったら恥ずかしくないか」
もともとテレビ事業部のエンジニアだった優司は、海外勢の製品に対して敵意をむき出しにする。そして、ソニップ製品がいかに優れているか、ブランド力が高いかを語りたがる。
恵理香と知り合ったときもそうだった。
2年前、博通で仲の良いデザイナーがホームパーティを開き、そこに優司が来ていた。
リビングに置いてあるテレビがソニップ製であることに気づくと、
「さすがデザイナーさんですね。ソニップのプラズマテレビは黒の深さが違うんですよ」
と講釈を始めた。
恵理香は画面に目を凝らしてみたが、黒の深さはわからなかった。けれども、優司が仕事に情熱をもっている男だということはわかった。
慶西大学理工学部卒で29歳という。名刺交換をしようとして、
「すいません。名刺を忘れました!」
と、ひどく慌てた様子も飾り気がなくて好感をもった。
その場で携帯電話の番号とメールアドレスを登録し合い、帰り道で早速、優司からメールが届いた。
当時25歳の恵理香は、優司を「結婚向きの男」として分類したのである。
その頃、ソニップ電機の業績はすでに低迷していた。優司は畑違いのマーケティング部に異動を命じられ、しかもテレビではなく、デジタルカメラの担当になった。
エンジニアがマーケティング部へ異動するのは稀なケースらしい。
優司は当初、不本意な異動を愚痴っていたが、マーケティング部はエリートが行く花形の部署であることを上司や同僚に言われて、愚痴が出なくなった。
マーケティングの仕事もやってみると水が合ったようだ。愛社精神はまったく失われていない。
「うちの会社は大きすぎるから意思決定が遅いんだよなあ」
とボヤくとき、どこかうれしそうである。大企業で知名度が高いことは、会社の業績や仕事内容とは関係なく、優司の誇りなのだ。
ソニップ以上の企業はないと信じているのか、自分の実力に自信がないのか、転職や独立の話も全然出ない。
「腐ってもソニップ」
そんな言葉がふいに浮かんだ。それは恵理香にそのまま跳ね返ってくる。優司と付き合い続けている理由を突かれた気がした。
「ソニップ電機の男」と言えば、世間的にはまだまだ聞こえがいい。周囲にもいい男はいるにはいるが、どれも結婚向きではなかった。
広告代理店の男は洗練されていて話が面白く、年収も高い。それゆえ女遊びが派手で、いつまでも自由人でいたがる。
たとえ結婚しても安心はできない。恵理香が知る限り、既婚者で浮気をしていない男は一人もいなかった。
テレビ局や出版社、商社の男もだいたい似たようなものである。
金融系は堅い男が多いが、どんなに稼いでいても、おカネを右から左に動かすだけの仕事を尊敬できなかった。
外資系コンサルは知的だが、その「知」をよその企業に切り売りするだけで、自分自身はプレーヤーではない。何も生み出していないうえに責任を取らないのがズルいと感じる。
もっとも、広告代理店の仕事も他人のふんどしで相撲を取っているのだから、人のことは言えない。
その点、優司は良くも悪くも安心感があった。刺激はないけれども、常識的で優秀だ。組織の中でプレーヤーとして真面目に働いている。
優司のこの奇妙な安定感は、現状のソニップ電機と似ていると恵理香は思う。
「ソニップは終わった」「革新性がなくなった」と何年も言われ続けながら、今なお大学生の就職人気企業ランキングのトップ10に入っているではないか。
あと10年、20年は沈まないのではないかと踏んでいる。
恵理香は最近、スタートアップの社長と立て続けに会ったが、やはり知らない名前の会社は不安が先立った。
どんなに経営者や事業が魅力的に見えても、数年後、この会社は果たして存在しているだろうかと考えてしまうのだ。
27歳の恵理香にとって、長期的な未来を描けない相手と付き合うのは時間の無駄でしかない。
だから、勢いのある起業家と会っても視界からことごとく消えていった。ただ一人を除いては……。
未知数の男
恵理香は洗濯物をたたみ終わり、コーヒーを淹れた。優司はあとしばらく来ないだろう。
ノートパソコンで「毛利健吾」の記事を再び検索する。出てくるのはビジネス系やテクノロジー系ばかりだ。
「~30歳の肖像~アクティベーター社長・毛利健吾」
「電気自動車で世界を変える!」
「みんなのドリーム大賞 毛利健吾|この男が未来をつくる!」
「スタートアップ社長に聞く 僕が大企業を辞めて起業したワケ」
浮ついた見出しが並んでいる。そのほとんどが青色から紫色に変わっていた。すでに読んでしまったからだ。
恵理香は営業の吉岡隼人とともに健吾の会社に行き、イベントへの登壇を依頼した。その日以来、健吾の新しい記事を探すのが日課になっている。
もし1本も見つからなければ、同じ記事を繰り返し読んでしまう。だから健吾の経歴は何度も見た。
国立京阪大学工学部卒、英国の大学院でアートを学ぶ。30歳。大日本自動車でエンジニアとデザイナーをしたのち、海外を放浪。2008年、アクティベーターを仲間と創業した。
この「アート」と「海外を放浪」というあたりが、気ままな芸術家タイプの匂いがする。それは本来、恵理香が好む堅実さとは対局にあるものだ。
しかも「仲間と創業」というのが、まるで少年マンガのノリである。事業を大学のサークル活動のように考えているのではないだろうか。
と、あれこれあげつらいながらも引き込まれてしまう。
やっと青色の見出しが見つかった。恵理香は小躍りした。これが1日のささやかなお楽しみなのだ。
「旅の途中で見つけた、俺だけの道」
旅行ガイド雑誌のWebサイトだった。取材を受ける媒体のジャンルを問わないらしい。
健吾の記事は、たいてい半袖のTシャツにバミューダパンツ姿の写真が載っているが、それは長袖のTシャツにデニム姿だ。初めて会った日と同じ格好である。
健吾の会社は青山にあった。築40年は経っていそうな雑居ビルの3階だ。外観はモダンと言えなくもないが、とにかく古い。
恵理香と吉岡は老朽化したエレベーターに乗った。信じられないほどのろのろ上昇する。
「こんなビルに電気自動車の会社があるんですね」
「しっ」と吉岡が人差し指を立てた。
「クライアント先ではエレベーターの中でも噂話はしちゃいけない。誰に聞かれているかわからないからな」
そう言いながら吉岡は話を続ける。やはり気が緩んでいるのだろう。
「独立して青山にオフィスなんか構えたら固定費だけで相当きつい。ピカピカのビルはまず無理だ。ま、バブルの頃に比べれば全然マシだろうけど」
バブル世代の吉岡は都心のマンションを高値づかみしていた。
「どうして青山じゃなきゃいけないんですか」
「会社のホームページや名刺に載せる住所が大事だから。ブランディングと見栄だよ。もし埼玉だったら客や取材が来ないだろ。いい人材も入ってこない」
「実態が伴わないのにブランド力だけ上げようなんて、ナンセンスですね」
「俺ら、その片棒をかつぐのが仕事じゃないか」
2人は苦笑した。
「吉岡さん、今日は一緒に付いてきてくださってありがとうございます。話題のスタートアップの社長なので、今後のためにと思いまして」
恵理香は礼を言った。吉岡はナショナル・ブランドのクライアントを数多く担当している。
「いいよ、いいよ。どこがどう芽が出て成功するかわからない。いつか大化けして広告をバンバン出してくれるかもしれないからな。今のうちから顔つなぎしておこう」
最後のほうは小声になった。3階に止まったからだ。ゆっくり扉が開いた。
公団住宅のような塗装された鉄扉が通路に並んでいる。
「アクティベーター」の表札を見つけ、吉岡がインターフォンを鳴らした。
中はワンルームだ。恵理香のマンションよりも少し広い程度である。
壁面に机を並べ、20代くらいの男性が3人、パソコンに向かっている。中年の男もいて、紙に何やらデッサンしていた。
スタートアップってあやしい……。恵理香は狭い玄関で思った。
「毛利さん、お客さんです」
大学生風の男が足元の塊に声をかけた。寝袋である。ごそごそ動き、健吾がぬうっと出てきた。
「ああ、すいません。昨日、徹夜したもんで」
目をこすりながら恵理香をまぶしげに見る。無精ひげを生やした精悍な顔がくしゃっと笑顔になった。まるで南の島の男だ。恵理香の鼓動が突如、鳴り出した。
部屋の奥へ通されるとき、健吾と思わぬ近さですれ違う。目線の高さに健吾の胸があった。Tシャツの上からでも逆三角形の引き締まった体が見てとれる。
イベントへの登壇を依頼すると、健吾は快諾した。
「会社の宣伝になるなら喜んで出ますよ」
資金集めに奔走しているのだろう。アクティベーターは、大日本自動車時代の同僚と家電メーカーの友人を誘って起業したという。
振動音がして、吉岡が携帯電話に出た。
「ちょっと失礼します。はい、はい、その件はスケジュール通りで……」
歩きながら話し、部屋を出ていった。
吉岡は大企業のクライアントの前では必ず携帯電話の電源を切っている。それなのに今、電話に出たのは、スタートアップの若造が相手だからだろう。
電話の相手は、付き合っているグラビアアイドルの卵に違いない。
「最近の子は発育が良すぎて18歳以上かどうか確かめないと、危なくてしょうがない」
と酒の席で部下に「忠告」という体裁で自慢していた。吉岡には高校生の娘がいる。
取り残された恵理香は健吾を見た。
マグカップに顔を近づけ、コーヒーをずずっ、ずずっと音を立てて飲んでいる。髪に寝癖が付いている。
恵理香は手持ちぶさたになり、さっきから思っていた疑問を口にした。
「あのう、電気自動車って簡単につくれるものなんですか」
健吾は笑った。
「簡単につくれるよ。電気自動車ってモーターとバッテリーと制御装置で動くんだけど、ガソリン車ほどの技術力はいらなくて、部品の数も少なくて済む。ラジコンカーとかゴーカートみたいなもんだね」
「ゴーカートって、本当ですか」
「イメージね、イメージ。プラモデルを組み立てるような感じ」
「どこで組み立ててるんですか。ここにはパソコンしかないですけど」
「小さい工場が千葉とアメリカにある。部品はすべて外部から調達して、大きい生産設備は抱えないようにしてるんだ。まあ、そんな資金力もないけどね。世界中から一番いい部品を集めて組み立てたほうがいい製品ができるんだよ。あのおやっさんは……」
と中年の男を指した。
「あのおやっさんは千葉の町工場の職人さんで、部品の調達先を探して全国の工場を回っていたときに出会った。おやっさんのつくるホイールがめちゃくちゃカッコよくて、電気自動車をつくりたいから仕入れさせてほしいってお願いしたら、あっさりいいよと言ってくれた。
俺、勝手に弟子入りして工場でしばらく働かせてもらって、業するときに、おやっさんに来てもらったの」
「新人の森沢です。57歳、よろしくどうぞ」
気の良さそうな男は薄い頭をなでた。
「町工場はどうされたんですか」
恵理香は尋ねた。
「息子に任せてます。こっちの部品の加工もやらせてる。うちの職人たちにつくれない部品はないからね」
森沢は胸を張った。健吾はコーヒーを飲んで言う。
「組織が大きいとかえって不利になることがあるんだ。日本の電機メーカーって事業領域をどんどん広げて、生産設備を自前でそろえようとするでしょ。だから環境変化に対応できなくなってるんだよ」
「ソニップ電機とかもそうですか」
「まさにそう」
優司を思った。いつかソニップがなくなる日は来るのだろうか。それでも恵理香は大企業よりスタートアップのほうがいいとは思えない。
「毛利さん、大日本自動車を辞めるとき、こわくなかったですか」
「何が?」
健吾はきょとんとした。
「失敗したらどうしようとか」
「そんなことぜんぜん考えなかったなあ。まず失敗とは何か、だよね。俺は自分のやりたいことができない状況のほうが嫌だから、そういう人生を送るのが失敗だと思ってる」
「やりたいことって何ですか」
「クルマが好きだからずっとクルマをつくり続けたい。それから電気自動車で世界を今よりもっと良くしたいね」
お決まりの「世界」だ。これほど男と女で温度差のある言葉はないと恵理香は思う。
男は「世界」を戦う舞台に設定して熱くなる生き物だ。それを社会人になってから知った。
健吾はパソコンで写真やデータを示す。
「まず二酸化炭素の排出量がガソリン車に比べて減るから、環境に優しい。
自動運転になれば交通事故がなくなって、渋滞もなくなる。目的地を指示すれば自動的に連れていってくれるようになるよ」
恵理香の脳裏を一瞬、幼い頃の記憶がかすめた。
「たとえば、家族でテレビを見ながらディズニーランドに行けたり、カップルが映画を見ながらレストランに行けたりする。
お年寄りが病院やスーパーへ行くのも楽になって、身障者も旅行をもっと楽しめるようになる。どう? こんな未来」
「すばらしいと思います」
「未来」という言葉も男は大好きだ。世界とか未来とか、はるか遠くばかり見ようとする。
女はせいぜい自分の周辺と自分から地続きの将来にしか関心がない。少なくとも恵理香はそうである。
それとも男には女に見えないものが見通せるのだろうか。
「本当に実現するんですか」
「実現させるんだよ」
健吾は当然のように言って、恵理香の名刺を見た。
「平野さん、電気自動車に乗ったことある?」
「ないです」
「広告代理店にいて、俺をイベントに呼んどいて、電気自動車に乗ったことないってマズいでしょ」
たしかにそうだ。
「今度、乗せてあげるよ」
健吾が恵理香の目をまっすぐに見つめる。恵理香の鼓動が早くなった。
「途中で充電が切れたらどうなるんですか」
動揺してつい、ぶっきら棒になる。
「そりゃあ止まってしまうよ。ただ急速充電器が……これ、ガソリンスタンドみたいなものね。急速充電器が街に設置されているから大丈夫」
「見たことないですけど」
「まだ少ないからね」
健吾はなぜかうれしそうだ。
「平野さん、さっきからいい質問するなあ。電気自動車が本格的に普及するための課題は、充電切れの心配をなくすことなんだ。1回のフル充電でどのくらい走れると思う?」
「うーん……。50キロぐらい?」
「もっと走れるよ。東京から伊豆ぐらいまでは行ける」
「それ、片道ですよね。戻ってこられるんですか」
「途中で充電休憩するから。それとももっと長距離、俺とドライブしたい?」
恵理香は笑った。
しかし実際のところ、ずっと走り続けられるかどうかわからないクルマは誰でも不安だろう。止まったらどうすればいいのか。
それは恵理香がスタートアップや起業家に対して抱く不安と同じである。
その日の夕方、健吾からメールが届いた。
「【アクティベーター】電気自動車『アクティZ』試乗会のお知らせ
平野恵理香さん
どうも、毛利健吾です。
2010年12月21日(火)午前10時から『アクティZ』の試乗会をやります!
ココに集合!! →地図」
恵理香は返事を打った。
「毛利健吾さん
本日はお忙しい中、ありがとうございました。
試乗会にぜひ参加させていただきます。ただ私はペーパードライバーですが、助手席に乗るだけでもいいですか。
平野恵理香」
すぐに健吾から返事が来た。
「ぜんぜんオッケー。絶対来てね~」
返信の早さに、健吾と間近で話している気分になった。それが先日のことである。
揺れる女
マンションのチャイムが鳴った。優司だ。午前0時をすぎている。
ドアを開けると、酒臭い息を吐いて恵理香にしなだれかかってきた。
「今日さあ、社長賞の発表があったんだけど、誰が取ったと思う?」
酔っぱらって上機嫌である。
「ひょっとして、優司?」
「正解! すごいだろ」
「すごーい」
と言うしかない。ミネラルウォーターをコップに注いで渡すと、優司は一息で飲み干した。
「なんで受賞したの?」
ソニップ電機はエレクトロニクス事業部全般が赤字体質で、リストラを繰り返していると言っていた。
「それがさあ、ミラーレス一眼のマーケが成功しちゃったんだよねえ。部長はデジカメにもうあんまり力を入れてないから、適当に俺にミラーレスを任せたらしい。
だから絶対に当ててやろうと思って、技術チームと横断プロジェクトを組んで『カメラ女子』ブームを仕掛けたんだ。そしたら販売台数がなんと前年同期比170%!
そうだ、恵理香もうちのカメラ買ったじゃん」
プロっぽく背景をボカせる手軽なデジカメが欲しいと相談したら、優司が薦めてくれたのだ。
「ソニップのミラーレス一眼は、きれいなボケ感が出せるんだよ」
と、テレビのときと同じように講釈した。
優司は技術がわかり、端的に説明する力がある。それがマーケティングの仕事に生きているのかもしれない。技術陣と顧客をつなぐ役割を果たせる。
一方で、あのとき恵理香は不思議な気持ちがしたものだ。
この間までテレビを開発していたのに、今はミラーレス一眼のマーケティングをしていて、その性能を熱く語っている。
組織の命令に従って異動し、すぐに順応して、あてがわれる製品を愛することができる。まるで自分の分身のように。
優秀なサラリーマンの条件とは、洗脳されやすさなのだろうか。「自分」はいったいどこにあるのか……。
「俺、みんなの前で挨拶させられちゃったぁ。中谷社長が『君のリーダーシップと企画力は大したもんだ。これからも期待してるぞ』ってさ」
うれしくてたまらないというように、優司はソファにジャンプして寝転ぶ。
ソニップの業績が低迷しているのは社長の責任も大きいはずだ。それなのに、その社長に評価されて無邪気に喜ぶ気持ちが恵理香は理解できない。
「俺、係長補佐になれないかなあ」
優司がつぶやいた。
「係長補佐? そんな役職あるの?」
「ない。だからつくってほしい」
恵理香は驚いた。
優司が以前から肩書を欲しがっていたことは知っている。ソニップ電機は管理職が増えすぎて若手が昇進しにくくなっていた。31歳で平社員は普通だ。
スタートアップは違う。優司と同年代の男が、執行役員、取締役、社長、CEOといった肩書で活躍し、雑誌に華々しく登場している。
「こんな小さい会社でCEOもクソもねえよ」
その雑誌を放り、吐き捨てたことがあった。
ソニップのマーケティング部は大所帯である。“功績”を評価された今夜、本音の欲が出たのだろう。
それにしても、酔ったうえでの戯言なら「社長になりたい」ぐらい言ってもよさそうである。存在しない役職を夢想するのがいじましい。
「これ、誰?」
優司がノートパソコンに表示されている健吾の記事を見た。
「クライアント。調べものをしてたの」
慌てて閉じた。
「ねえ、係長は誰?」
「前田ってやつ」
「優司は係長になれるんじゃない?」
「そう簡単じゃないよ。前田は6つ上だし、仕事もできる。それに俺、前田のこと、けっこう好きなんだよね」
ビジネス書にはよくこんなフレーズが書かれている。
「大きな夢を持とう」
「あきらめない限り、夢はかなう」
「人が想像できることは、すべて実現可能」
こうした標語が恵理香は好きではない。遠くばかり見ていると、足元の石につまづく気がするからだ。
しかし、優司の目線の低さを目の当たりにすると、別の考えが浮かんでくる。足元ばかり見ていると、空模様の変化にも気づけないのではないか。
優司がジャケットを脱ぐ。恵理香はソファに押し倒された。
「今日は最高の日だったよぉ」
社長賞が「最高」の男。「最高」と設定する地点が、その男の限界かもしれない。だとすれば、優司にしがみついている自分はいったい……。
苦いものが体中に広がっていく。
「電気を消して」
恵理香は頼んだ。
恥ずかしいからではない。押し殺しているさまざまな感情を明るい光の下でさらしたくないからだ。
「よっしゃー!」
優司はすばやく電気を消して、恵理香にキスをしながら部屋着をたくしあげた。胸を強くもみしだき、交互に吸い付いてくる。
恵理香の芯が小さく点火した。苦いものが消えていくことを祈る。だがソファの上だからか、いくつかの工程が省かれた。
突然、優司が恵理香の中に押し入ってきた。感に堪えないといったうめき声をあげる。
体を前後にゆっくり揺らす。しばらく繰り返したあと、恵理香の足首をつかんで二つに折りたたみ、深く挿し込んだ。
スピードが上がった。優司が目を閉じて恍惚とした表情を浮かべているのが、暗闇の中でもぼんやり見える。
自分の快楽に一直線に突き進み、天を仰いで「最高だ」と、もう一度つぶやいた。
それはセックスのことか、それとも社長賞のことか。
後者のほうだと確信し、恵理香は萎える。萎えるというのは相手より優位に立つ感情だ。
前後運動にひたすら没頭する優司を、下から冷めた目で見つめた。
それに気づいた優司は照れたように笑う。
「なんだよぉ」
恵理香は微笑み返し、怒りを込めて男のものをぎゅっと締めつけた。
「ちょっ、ちょっと待った……」
優司は爆発するのをこらえるように動きを止める。恵理香はさらに力を入れる。
「恵理香……」
優司は観念し、再び早く動き出す。恵理香の芯から熱いさざ波が立ち始める。
その瞬間、目をつぶり健吾を思い浮かべた。無精ひげを生やした南の島のような男……。
高まりかけたとき、上に乗っている男が恵理香の名前を叫んで果てた。
ずっしりした重みを受け止める。慣れ親しんだ肌の感触、汗の匂い。荒い息が首にかかる。
恵理香はいつまでも目を開けなかった。やがて、さざ波は静かに遠のいていった。
土曜日の朝、優司は爽快な気分で目覚めた。
コーヒーの香りが部屋に漂っている。いつも優司が起きるタイミングを見計らって、恵理香はコーヒーと厚切りトースト、色鮮やかなスペイン風オムレツをテーブルに並べる。
「簡単よ」と恵理香は言うけれど、スペイン風オムレツは優司の好物だ。
こういうのを幸せというのだろうか。仕事で結果を出し、会社に認められ、彼女を抱き、出てくるメシがうまい。
ものの5分で平らげると、優司は申しわけない顔をして切り出した。
「今日、これから会社に行って仕事しなきゃならないんだけど、いいかな」
本当は早く仕事がしたい。社長に期待をかけられたことで、やる気がみなぎっていた。
「いいよ、気にしないで。私は家でゆっくりしてるから」
休日出勤するというのに、恵理香は快く送り出してくれる。
「仕事、がんばってね」
と励ましてさえくれた。少し寂しそうに見えるが、それでも男を気づかう恵理香が愛おしい。
オフィスに行くと、係長の前田亮介がいた。
「どうした」
「ちょっとプレゼンの準備をしたくて」
来週、ミラーレス一眼の春モデル販売促進キャンペーンのプランを発表する。そのスライドを早く仕上げたかった。セキュリティの都合上、資料やパソコンは社外に持ち出し禁止である。
「俺はたまってる仕事を片づけたくてね」
前田には小学生の子どもが2人いる。家のことをまったくしないので奥さんはしょっちゅうキレると言っていたから、夫婦ゲンカでもしたのかもしれない。
優司は机の上を見た。1つ下の後輩の渡瀬綾に、女性のデジカメの利用実態調査をまとめておくように頼んでおいたのだが、それらしき資料は置かれていなかった。メールも届いていない。
「あーあ、また渡瀬が期日を無視しましたよ。どうにかなりませんかね」
「今日はゴルフに行ってるよ。千葉なのに前泊ゴルフだ」
「前泊ゴルフってなんですか」
「ゴルフの前日からホテルに泊まることだよ。早朝に行けば済むのにな。役員たちも行ってる」
「えっ、もしかして渡瀬、役員の誰かとデキてるんですか」
「さあな」
「ま、どうでもいいですけど、やるべきことをちゃんとやってからヤッてほしいですよね」
2人は声を立てて笑った。
優司は仕方なく自分で調査結果をまとめ始めた。休日のオフィスは静かで底冷えがする。
前田はかつてテレビのマーケティングをしてヒットさせたことがあり、その頃、優司はテレビの開発をしていた。
共通の話題は、「早期退職者募集」という名のリストラで辞めていったテレビ事業部の人間を知っていることだ。
優秀な人間から手を挙げるというのは本当で、トップ級のエンジニアが韓国や台湾のメーカーに引き抜かれたときは動揺したものである。
一方、お荷物社員は明らかに嫌がらせと思われる部署、通称「追い出し部屋」に異動させられ、ジタバタしたあげくに退職していった。
優司と前田は、外部からの引き抜きもなければ会社からの嫌がらせも受けていない。しかし、30代でも「追い出し部屋」に放り込まれた者がいるから油断はできなかった。
ビジネスで有名な「2:6:2の法則」がある。
上位2割と下位2割がいなくなると、中間の6割の中からまた上位2割と下位2割が生まれるという。
自分と前田は中間の6割にいたのだろう。今は上位2割に入っていると信じたい。
そこまで考えて優司は、転職した人間が自分より優秀だと一瞬でも認めたことを悔やんだ。
「前田さん、最新号の『テックNEWS』、見ましたか」
前田は、部署で定期購読しているその雑誌を手に掲げた。
「辞めた水島さん、スタートアップの取締役をしてるんですね。デザイン家電のメーカー」
優司が雑誌の該当ページを開いて見せると、前田は一瞥して視線を戻した。
「企業の5年生存率、知ってるか」
「15%ぐらいですよね」
「10年だと6%だ」
前田もその数字を調べたのだと思った。
ソニップをあっさり辞めた人間に対する屈折した思い。それが優司と前田のもう1つの共通点だ。彼らを仮想敵として結束しているところがある。
新宿の老舗デパートは、不景気とはいえ賑わっていた。
クリスマスカラーを基調にしたキラキラしたディスプレイが、恵理香の気分を浮き立たせてくれる。
シーズンごとにやって来て通勤着をまとめ買いするのだが、今日、訪れたのはカジュアルなデニムの服が欲しいからだ。健吾のラフな格好に合わせるためである。
「試乗会」は来週だ。エスカレーターを上がり、インポートブランドを見て歩いた。
ふとイタリアの靴専門ブランドの前で足を止めた。有名なドライビングシューズを見てみたい。
ピンク、ブルー、イエロー、グリーンなどのカラフルな靴が並んでいる。かかとと靴底に付いているゴムの突起は滑り止めなのだろう。
恵理香は運転免許を大学時代に取ったきり、一度も運転していない。試乗会でひょっとしたら運転することになるかもしれないが、その1回のために買うにしては高価である。普段使いにできるだろうか。
通勤バッグと同じブラウンの靴を試し履きしてみた。上質な革が足にフィットして気持ちがいい。ボーナスが出たばかりだから、思い切ることにした。
最後に下着売り場に行く。フランスのラグジュアリーブランドをのぞいた。本当はこのために来た気がする。
最近、下着はもっぱら国産ブランドか、ファストファッションの店で購入していた。
優司が泊まる週末は最低限、上下の色と柄を合わせるようにしているが、それさえもバラバラになることが多くなっている。
もう下着などまじまじと見なくなっているのだ。ボクサーパンツを履いていても優司は何も言わない。
恵理香は芸術品のように美しく繊細なブラとショーツに吸い寄せられる。淡いピンクのレースにそっと触れた。
健吾はどんな下着が好きなのだろう……。彼の手が伸びてくるのを想像し、頭の中が甘くしびれてきた。
*明日のSeason1(中編)19~36話に続く。
(イラスト:永井結子)
*7月4日(月)からSeason2がスタート。日曜日をのぞく毎日公開(有料)。