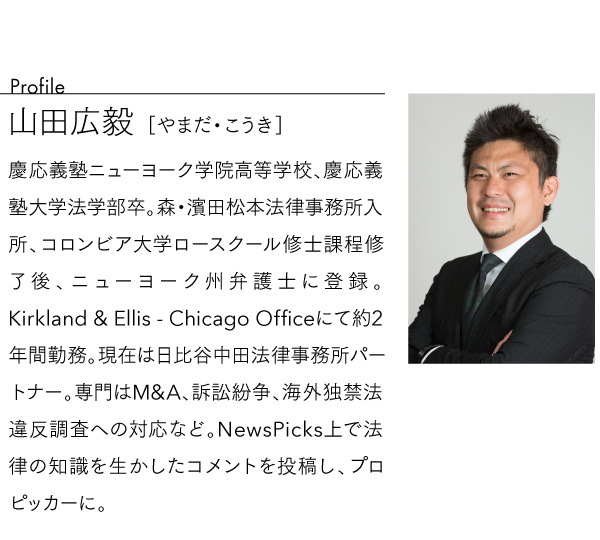ルールの理解が必要不可欠
日本企業の幹部や従業員も服役──米国・カルテル規制の恐ろしさ
2015/11/13
プロピッカーで日比谷中田法律事務所のパートナーを務めている弁護士の山田広毅氏が、日本では詳細がニュースにならない、カルテルに関する米国当局の動きについて解説する。
第2期に引き続き、第3期もプロピッカーとして活動させていただいている弁護士の山田広毅です。今回は、私の専門分野の一つであるカルテルに関する米国当局の調査について書かせていただきたいと思います。
今年に入ってからも、いくつもの日本企業や日本人が、法的責任を問われている分野ですが、詳細がニュースになることはあまりないので、通常のニュースメディアを見ているだけではわからないところについて、掘り下げてみたいと思います。
そもそもカルテルって?
そもそもカルテルって、一体何なのでしょうか。ちゃんとこれを論じようとすると、それだけで、複数の記事が書けるのですが、ここでは、わかりやすいように、実務で出てくる具体例を挙げてみます。
価格カルテル
まず、一番わかりやすいのは、価格カルテルです。価格カルテルとは、同業者同士が、競合商品の販売価格について協定し、競争を回避することです。
たとえば、H社のサプライヤー(部品メーカー)が2社いて、部品Aと部品Bの入札が行われている場合に、両方のサプライヤーが確実に受注できるよう「部品Aについて、うちは110円、オタクは120円で見積りを出す代わりに、部品Bについては、うちが120円、オタクは110円で見積を出そう」と合意することです。
相手の価格情報を知らないでガチンコで競争すれば、お互い105円レベルで見積りを提出できていた場合でも、相手に手の内を明かして合意してしまえば、ベストプライスよりも高い価格で販売することが可能になるわけです。このような行為を許すと、最終消費者は商品を高く買わされることになるので、法律で禁止されているわけです。
一連の自動車部品カルテルのほとんどは、この類型だと思います。
市場分割カルテル
次に、市場分割カルテルがあります。市場分割カルテルは、同業者同士、各企業が商品を売っていい市場を協定し、競争を回避することです。
たとえば、似たような家電商品を販売する競合メーカー同士が、「欧州市場はメーカーA、アジア市場はメーカーB、米国市場はメーカーCのそれぞれ縄張りであり、お互いの縄張りには進出してはいけない」と合意するものです。これも実質的に各市場における競争をなくすものであり、各メーカーは競争がある場合に比べて、自由に価格決定ができることになります。
たとえば、マリンホースカルテル事件では、価格協定に加えて、市場分割カルテルもなされていたことが認定されています。
カルテルは欧米において重大犯罪
そもそも、米国や欧州では、カルテル行為は、自由競争を著しくゆがめるものとして、極めて悪質な重大犯罪(felony)とみなされています。
この辺りの感覚は、官製談合まで存在していた日本とは随分異なっています。実際のカルテル現場でも、日本企業の当事者の方々は、「最近商売の調子はどうですか」「メーカーの締め付けが厳しくて大変です」というような一般的な情報交換の流れの中で、割と軽い気持ちで一線を踏み越えて、違法なカルテル行為に及んでいた状況が見受けられました。
ところが、ここに大きな落とし穴があるのです。前回記事でも軽く触れたのですが、米国や欧州の当局は、国際カルテル事案において、自国の法律・ルールを、極めて積極的に域外適用しています。
日本人の感覚からすれば普通だと感じる商慣習が、米国や欧州の当局からは、重大な悪行の証拠だと糾弾されるわけです。日本企業がグローバルマーケットで勝負し続ける以上、当該マーケットのルールにのっとって勝負するほかありません。ルールの理解が非常に重要なのです。
日本企業の幹部が服役している
米国のカルテル規制の怖いところは、会社に対する多額の罰金もさることながら、関与した個人が刑務所に服役させられることです。
米国司法省の発表(日本人の個人3人の起訴に関するプレスリリース)によれば、2015年10月8日時点で、自動車部品カルテルだけで、37の企業と、58人の個人が起訴されていますが、それらの多くは日本企業とその日本人幹部・従業員です。
そして、起訴されたうち、個別に有罪答弁を行うことを選択した人たちは、実際に米国の刑務所に服役しています。期間は人によりますが、1年〜2年半くらいが現在の相場だと思います。日本人の多くは、USP LOMPOCまたはCI TAFTといった、比較的セキュリティレベルの低い施設に収監されているようです(USP LOMPOCのウェブサイトには外観の写真も載っていますので、興味があればリンク先を開いてみてください)。
多数の日本企業の幹部が実際に服役しているという事実は、かなりショッキングだと思いますが、あまり一般には報じられていないと思います。
時効期間が長い
カルテル規制については、さらに怖い点があります。そもそもカルテル違反の刑事責任の時効は、違反行為から5年間です。ところが、上記米国司法省のプレスリリースを見ても、およそ12年前の2003年ごろの行為まで言及がされています。これはなぜでしょうか。実は時効の起算点(スタート時点)にトリックがあるのです。
カルテルは、「協定」行為なので、その協定の効果が続いていることが外部的に明らかである場合には、当該行為は継続しているとみなされます。
すなわち、犯罪行為が連続して継続しているとみられてしまうのです。たとえば、ある自動車部品について価格カルテルをした場合には、当該カルテルの効果は、その部品が使用された自動車モデルの販売が終了するまで続くことになります。
一般に自動車モデルの部品の調達は、実際にその自動車モデルが量販される2〜3年前に始まることが多く、価格カルテルの合意は、そのときに行われます。
しかし、価格カルテルの影響を受けた自動車が市場に出回るのは、価格カルテルの2~3年後なのです。さらに、自動車の量販モデルは、完全に販売停止になるまでに一般に3〜6年くらい販売されます。
この間、価格カルテルのせいで高値となった自動車がずっと売られていたことになりますので、その間、ずっと価格カルテル行為が続いていたとみなされます。
とすると、当初のカルテル合意から、5~9年間、カルテル行為が継続していたとみなされてしまいます。時効期間は、カルテル行為が終わった時点から、初めてスタートします。
従って、時効期間の5年間がスタートするのは、カルテル合意から5~9年後。つまり、カルテル合意から10~14年たって、ようやく時効が成立するというわけなのです。
カルテルをやっていた企業・従業員からすると、これは脅威です。現在でこそ、カルテルは違法な行為であり、絶対にやってはいけないという意識は強くなっていますが、2000年前半にそのようなコンプライアンス意識があったかというと、必ずしもそうではなかった会社も多いと思います。
すでに起きてしまっていることは変えられないので、非常に難しい問題だと思います。
米国司法省との司法取引とは
米国司法省との折衝を行っていて感じるのは、米国司法省との司法取引は、字のごとく「取引」であって、実際に、交渉次第で結果が変わり得るということです。
(少なくとも現在の)日本の刑事手続とは、パラダイムがまったく異なりますので、対応する日本企業の側も、そのことをちゃんと理解することが肝要です。
そもそも、司法取引とは、(かなり単純化すると)企業側が有罪を認める代わりに、事前交渉で合意された刑を受けるものです。アメリカの刑事裁判は陪審員制であるため、正式な裁判手続ではどのような刑が下されるか最後までわかりませんし、感情論で非常に厳しい刑が下されることがあります。
特に外国企業の場合にはそのリスクが高いです。司法取引の場合には、略式手続が行われ、陪審員による裁判は行われずに、事前に司法省と合意した刑が課されるのが通常です。有罪を認めている企業からすると、陪審員制による厳罰リスクを回避することができるのです。
また、多くの場合、企業側は、コーポレーションクレジット(捜査協力した対価)として、一定の減刑を受けることができます。これにより、相場よりも軽い刑とすることができるのです。
一方で、司法取引は、捜査機関側にも利益があります。まず、司法取引の場合には、上記の通り、罪を認めていることを前提とした略式手続で裁判が行われますので、普通の裁判手続で必要な裁判上の立証活動が一切不要となります。有罪・無罪が争われる刑事裁判だと、一審だけでも何年もかかる場合もあり、そのためにかかるコストは莫大なものになります。
米国司法省は、立件数、罰金の総額などを非常に気にしており、できるだけコストをかけずに、多数の事件を立件し、罰金の支払いを受けることを目指しています。刑事事件の処理にまで経済合理性を持ち込んで考えるのは、非常に米国的と感じています。
加えて、捜査機関が得られる利益として挙げられるのは、当該企業から今後の捜査に関する証拠の提供を受けることができることです。司法取引の契約書の中には、捜査機関への捜査協力義務が必ず盛り込まれています。
かかる協力義務には、共犯などに関する情報提供義務も含まれます。カルテルは必ず共犯がいる犯罪ですので、1社が司法取引をすると、その1社が自らの共犯であるほかの同業者の違法行為の証拠を、積極的に捜査機関に提供することになるわけです(これに加えて、リニエンシーや、アムネスティ・プラスという、「タレコミ」へのインセンティブ施策が取られています。簡単に言うと、一番最初にカルテル行為の「タレコミ」をすると、一番手は、当該カルテル行為についての刑事罰を免れられる制度です)。
このように、場合によっては捜査機関側にも「司法取引で早く案件を終わらせたい」という強いインセンティブが働いていることがポイントです。
たとえば、司法取引の交渉の中で、捜査機関が不当に高額な罰金額を提示してきた場合には、「そんな条件であれば、取引に応じることはできない。正式裁判で戦う!」とテーブルをひっくり返すことは十分にあり得ます。
他方で、捜査機関側が非常に強い証拠を持っていて立件に自信を持っている場合には、ほとんど交渉に応じず、一方的に司法取引条件を通知して、応じなければすぐに正式起訴に移るというような態度で臨んでくることもあり得ます。
実際の現場では、両者の手持ちの証拠を想定しながら、ギリギリの交渉を行っていくことになりますが、これは、捜査機関側との交渉の余地がほとんどない日本の刑事手続とは、随分異なる手続きです。万が一、巻き込まれてしまった場合には、そのことを常に肝に命じておくことが必要です。
日本企業、日本人は、活躍の場をますますグローバルに広げています。しかし、グローバルにビジネス展開をすることは同時に、グローバルのルールにのっとったビジネスをしていかなければならないということでもあります。
そのルールの土俵の上で、いかに上手に戦うかが問われているのです。今回の記事が、そのための一助となればいいなと思います。