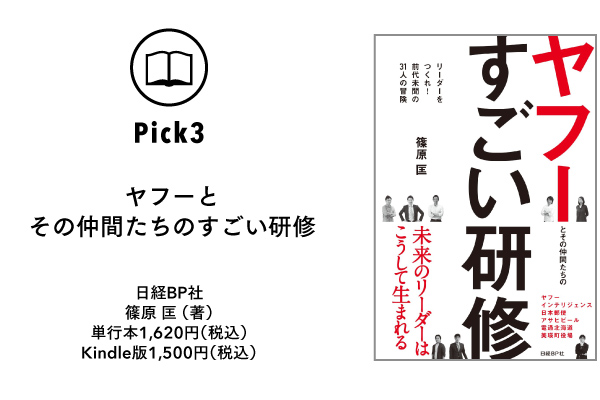編集部がピックアップする新刊本3冊
グーグルが徹底する「データドリブン」な採用・育成体系とは
2015/8/26
時代を切り取る新刊本をさまざまな角度から紹介する「Book Picks」。毎週水曜日は「Editor’s Choice」と題して、NewsPicks編集部のメンバーがピックアップした新刊本を紹介する。
今回はエディターのケイヒル・エミが、「グーグルの採用・育成体系」「全米で人気の古着ネットショップ」「ヤフーの異業種コラボ研修」をテーマに3冊を取り上げる。
本書は、グーグル人事担当上級副社長ラズロ・ボックがグーグルの採用、育成、報酬について赤裸々に語った著書である。
人工芝にハンモック、滑り台のあるオフィスの風景に象徴されるような、自由闊達(かったつ)な社風を説明するのに冒頭3章が費やされている。しかし、本書の真の見どころはグーグルのデータドリブン(データに基づく意思決定をすること)な人事活動に関する記述だろう。
ボックによれば、グーグルでは「社員にかける時間と資金の大部分を、新たな社員を引きつけ、評価し、育てることに投じる」。
これは、小さなスタートアップだったときから、1人で何人分もの成果を出す、突出した「人材」が最大の資本であったことや、グーグルが急スピードで成長したことに関係する。こういった環境では、人材の「はずれくじ」を引くことが、致命的なロスになりかねなかった。
「はずれくじ」を引かないための合理的な採用に必要だったのは、公正中立な「データ」である。本書では、そんな人事活動に関するデータがこれでもか、というほど提示される。
5章から例を挙げてみよう。ボックが「一番力を入れている人事活動だ」と言い切る採用活動に関して、以下のようなデータが提示されている。
応募者の職務能力を測る際、身元照会は応募者の職務能力を7%しか説明できず、職務経験年数はたったの3%しか説明できない。
日本の採用活動でも一般的な非構造化面接(質問項目を特に用意はせず、被面接者の反応に応じて自由に方向づけを行う面接のこと)の職務能力は説明力がたったの14%。逆に、比較的職務能力を測るのに向いているのはIQテストなどの一般認識能力テスト(26%)や、あらかじめ質問項目を決めて行われる構造的面接(26%)なのだそうだ。
グーグルの採用面接では、こうした効果の高い方法を組み合わせている。さらに、採用後の社員のパフォーマンスを追跡することで、面接やテストにおける質問や設問を「能力の高い人材を採用できるもの」に厳選し、採用現場で使うという、すさまじいPDCAを回しているのだ。
冒頭3章でとりわけ強調されるグーグルの社風──グーグルのミッションへの共感や、社員への情報公開をちゅうちょしない透明性、発言権や裁量権を広く認める風通しの良さ──も、実はすべてデータで「人事に有効」と裏付けられていることが読み進めていくうちに明らかになる。
日本の一般企業にとって、「データドリブンな人事活動」はハードルが高いように思うかもしれないが、本書を読んで、「人事の最先端」をも行くグーグルにヒントを得ることも手なのではないだろうか。
CtoCの古着・手づくり雑貨マーケットプレイスである「Etsy(エッツィー)」に、私が好きな古着ネットショップ「Noteworthy Garments(ノートワーシー・ガーメンツ)」がある。そこで初めて買い物をしたときの感動がいまだに忘れられない。
派手な緑色のボンバージャケットと、背中に独特なかたちの穴が空いた花柄のブラウスを購入したのだが、なんと女性店主の直筆の手紙が同封されていた。
「このボンバージャケット、私もお気に入りなの。あなたにも気に入ってもらえるといいな。ジャクリーン」
ネットショップは店主のジャクリーンが1人で運営しており、彼女自身がモデルも務めていたので、ジャクリーンのことは商品写真でたびたび目にしていた。あんなイケててオシャレな女の子がわざわざメッセージをくれたなんて! それだけで私はすっかり舞い上がってしまった。
イーベイや、エッツィーなどのオンライン・マーケットプレイスに、自身のクローゼットひとつでネットショップを立ち上げる、ジャクリーンのような若い女性が増えている。
資本もいらない。学歴もいらない。必要なのは、持ち前のセンスと、ビジネスを軌道に乗せる熱意だけ。こういったネットショップ起業の活性化が、本来ならビジネスと接点のなかったであろう、しかし、商才あふれる若い女性たちをビジネスの世界に引き入れることとなった。
本書の著者、ソフィア・アモルーソはそんな女性の筆頭だ。いまや約2億5000万ドルの資産を持つ天才起業家として『フォーブス』に取り上げられる彼女が、たった8年で100億円企業の「Nasty Gal(ナスティー・ギャル)」をつくりあげるまでを描いたのが本書だ。
彼女は著書の中で自らをADHD(注意欠陥・多動性障害)にたとえるが、彼女の経歴はそれにふさわしい。
高校2年生の頃に学校に行くのを辞め、さまざまなアルバイトを転々とする。「サブウェイ」でサンドイッチをつくってみたり、書店員をやってみたり、アウトレットモールの靴屋でご婦人方に矯正靴を売ってみたり。
当時の彼女の仕事選びの基準は「簡単であること」。だから、すぐにどの仕事も飽きがきてしまい、「退屈しないためには、仕事を替えるしかない」とさらなる転職を続けたという。
プライベートでは、万引きを繰り返し、アナーキズム(無政府主義)にも傾倒。マルクス主義者の勉強会に参加したり、食べ物を探しにゴミ箱をあさったり、部屋の家具を粗大ゴミや盗品でそろえた。
そんな彼女に転機が訪れたのは、22歳でヘルニアになったときのこと。実家に転がり込んで安静にしていた彼女は、イーベイの古着ネットショップを見て「これって、私にだってできるじゃない」と思ったのだ。
起業ストーリーらしからぬ、なんとも間の抜けた始まり方だが、そこからの彼女の奮闘ぶりには目を見張るものがある。
商品が売れれば、すぐに同じような物を仕入れに行く。ネット掲示板で遺品整理をする家を調べて地図をつくり、しらみつぶしに回ってしつこく値切る。広告文にはコーディネートのアドバイスを添え、顧客に付加価値を感じてもらう。
当時流行していたSNS「マイスペース」で、イット・ガール(SNSなどで一躍有名となった女性)やその友人らと次々に「友達」になる。万単位になったマイスペース上の「友達」をネットショップへの呼び込みに利用する。商品の検索用キーワードを、食事中にも練り続ける……。
経営の経験をまったく持たない彼女が直感に従って実践した数々の施策は、実はすべてビジネスの基本を踏襲していた。彼女がそこからネットショップ、ナスティー・ギャルをどう拡大させたかについては、ぜひ本書を手に取って読んでみてほしい。
最後に、ひとつ忠告することがある。この本はかなりの「ゲテモノ」だ。
おそらく原書はユーモアたっぷりの軽い切り口で書かれていたのであろうが、邦訳を通して言い回しの不自然さや、たとえ話のわかりにくさばかり目立つものになってしまった。
そもそも、タイトルにもなっており、本文中でも頻出する「#GIRLBOSS(#ガールボス)」のニュアンスについてさえ、日本語版では補足説明がない。英語では、“Boss(ボス)”は「上司」を意味するほかにも、「活躍していること」「格好いいこと」を指すスラングでもあるのだ。
ソフィア・アモルーソの物語は、まさに前出の若い女性起業らのトレンドを象徴するもの。「彼女らは一体何者か?」が気になる人は、一度手に取ってみてはいかがだろうか。
昨年、人事関係者の間で話題になった「地域課題解決プロジェクト」をご存じだろうか。
「地域課題解決プロジェクト」とは、ヤフー、インテリジェンス、日本郵便、アサヒビール、電通北海道、美瑛町役場と、業種もカルチャーも異なる企業や団体の幹部候補が混成チームを組み、北海道上川郡美瑛町における社会課題の解決策をプレゼンする異色の研修のこと。昨年10月から半年間かけて行われた。
本書はそんな異業種コラボレーション研修「地域課題解決プロジェクト」をリポートした著作である。
冒頭の「主な登場人物」ページには、研修に参加した31人や、研修を企画・運営した面々の写真や名前、役職、そして性格や特徴までもが軽妙な語り口で記されており、まるでゲームのキャラクター紹介のよう。
この「主な登場人物」ページに象徴されるような絶妙なエンタメテイストを織り交ぜ、まるで現場で一緒に研修を受けているかのような臨場感が本書の特徴だ。
同研修の仕掛人である本間浩輔ヤフー・ピープル・デベロップメント統括本部長が、こうした研修では「人間の習性がさまざまなかたちで現れる」と話すように、同研修に集められた多様なメンバーの間でさまざまな化学反応が起こる。
当然ながら、チームビルディングに失敗するチームもあり、その失敗が、町民らをして「軽い、浅い、ひどい!」と言わしめるほどのプレゼンの質の低下に直結するさまも赤裸々に描かれる。
一読者としては、チームビルディングに成功したチームの経験から多くを学ぶことができた。
都内の大企業幹部候補らと、地元の美瑛町役場のメンバーから成るEチームは、同じ言葉でも、メンバーそれぞれ異なる定義を持っているため会話がすれ違うことに早期に気づいた。解決策として、一部メンバーには縁遠い「横文字」をディスカッション中に禁じる、などのルールを決めた。
また、チーム内で「マイノリティ」になりがちなメンバーにも発言しやすい雰囲気をつくるため、お互いの気心が知れるまでは議論を止めて、発言の少ないメンバーに話を振る。
別のチームでは、最年少メンバーが早期にチームの強みや特徴を分析、自身が一番貢献できると考えた役割に手を挙げたことを機に、チーム内の役割分担がビシッと決まった。
こういった異なる背景を持つメンバー同士が時にぶつかり合い、切磋琢磨し合う様子が見られるほかにも、昨今話題に上ることの多い「地方創生」の現場を垣間見ることができるのも本書の魅力のひとつだ。机上の空論にとどまらず、地元住民が実際に「必要だ」と感じるようなソリューションを編み出すことがいかに難しいかがひしひしと伝わる。
さらに、人事やコミュニティマネジメントのプロが手塩をかけて研修を完成させた様子にも文量をかなり割いているので、本書は人事関係者などにも参考になるだろう。
(文:ケイヒル・エミ)