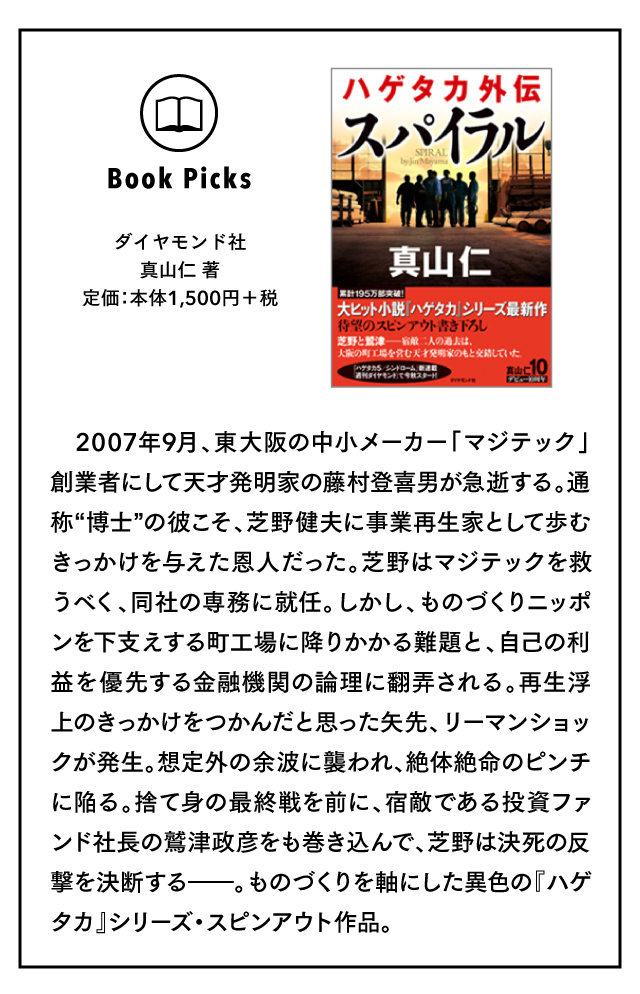『ハゲタカ外伝 スパイラル』著者 連続インタビュー(上)
真山仁が問う。「なぜ弱い中小企業が潰れないのか」
2015/8/21
新連載「Book Picks」では、時代を切り取る新刊本をさまざまな角度から紹介。隔週金曜日は、話題の新刊著者インタビューを、3回にわたって掲載する。
第1回に登場するのは、先月、『ハゲタカ外伝 スパイラル』を刊行した真山仁氏。これまでグローバル金融の最前線を描いてきた『ハゲタカ』シリーズだが、今回の舞台は大阪の町工場。その舞台設定の理由から、本作のテーマとなる中小企業問題、TPP、エネルギーといった社会問題に至るまで、縦横無尽に聞いた。
「巨大自動車メーカーの命運を町工場が握る」テーマを描こうとしたが……
──真山さんが7月に出版された『ハゲタカ外伝 スパイラル』は、『ハゲタカ』シリーズの外伝という位置付けの作品です。物語の舞台もグローバルな金融の最前線から大阪の町工場というドメスティックな場所へ一気に移りましたが、その舞台設定の理由について伺えますでしょうか。
真山:これまで『ハゲタカ』シリーズでは、大掛かりな買収案件を描いてきました。不良債権処理や買収案件について描いた『ハゲタカ』を皮切りに、『ハゲタカII』(『バイアウト』を改題)では日米のファンドが電機企業をめぐって争う姿を、『レッドゾーン』では日本の巨大自動車メーカーと中国の国家ファンドの攻防を、そして『グリード』ではリーマンショック前後のアメリカの巨大メーカーをめぐる争いを描いたように、シリーズのスケールがどんどん大きくなっていきました。
読み物としては、規模が大きくなればなるほど、国際化すればするほど面白い。しかし、一方では読者にとって遠い話になりすぎてしまうとまずい、という意識もありました。そこで、バランスを取るために、足元の日本の中小企業で起きていることについても書く必要があると思い続けていたことが実現しました。
『レッドゾーン』連載当時、ある信州の小さな機械メーカーに興味がありました。トヨタ自動車がハイブリッドカーを生産することができたのは、このメーカーが電気とガソリンを上手に交換できるようにする、角度センサーという部品をつくったからなんです。同社が存在しなければ、トヨタはハイブリッドカーをつくれなかった、といっても過言ではないんですね。
この角度センサーの事例から、「巨大自動車メーカーの命運を町工場が握る」という設定を思いつきました。エジソン的な発想で優れた発明をすれば巨大メーカーとでも競える、というストーリーを、国内の小さな工場を舞台に描くつもりだったんです。
そこで、「角度センサーのような事例をもっと掘り起こそう」と思い、取材を始めました。
──具体的には、どういった企業に取材したのでしょう?
はじめに、コモンレールというディーゼルエンジン用の部品をつくっているドイツのメーカー、ボッシュの日本工場に取材に行ったのですが、最初の30分で不可能だと判明しました。
──不可能だと諦めた理由は?
コモンレールは、ディーゼルエンジンにおける軽油の噴出を細かい霧状にし、黒煙の排出を止める部品です。軽油で動くディーゼルエンジン車は、CO2の排出量が少ないので、黒煙の問題さえ解決すれば既存の自動車より環境に優しい。そういった事情から、ドイツではコモンレールの開発が進んでいました。
ボッシュの研究員たちにその話をすると、「1の37乗分の1秒の間隔で霧状の軽油を噴かせるような、そんな技術が町工場にできると思いますか」と言われました。似た仕組みのものでは、町工場がインクジェットプリンターの先端部をつくっていたんですけれども、「インクジェットとコモンレールでは必要な技術のレベルがまったく違う」と。
さらに、ボッシュの研究員いわく、そもそも外資系企業はいわゆる「職人芸」を持つ人材をすでに囲っているそうです。社内に町工場をいくつも抱えているような状態なので、日本企業のようにわざわざ外の町工場に発注しない。
町工場が集まる東京都大田区や、トヨタの城下町である愛知県豊田市にも行きましたが、町工場がものすごくハイテクな技術をもって巨大企業を支えるというのは「おとぎ話になってしまう」というのが取材を通して得た結論でした。

真山 仁(まやま・じん)
小説家
1962年、大阪府生まれ。同志社大学法学部政治学科卒。新聞記者、フリーライターを経て、2004年『ハゲタカ』で作家デビュー。2007年に『ハゲタカ』『ハゲタカII』を原作とするNHK土曜ドラマ『ハゲタカ』が放映され、大きな反響を呼ぶ。近刊に、『そして、星の輝く夜がくる』(講談社)、『売国』(文藝春秋)、『雨に泣いてる』(幻冬舎)など
立場が変わることによって、ものの考え方が変わる
──当初の物語の構想は崩れてしまったのですね。
そうです。ただ、「中小企業が大企業に挑むものの、断念する」というのも、物語の答えになり得ると思いました。そこで、中小企業の再生というテーマは継続して使い、『ハゲタカ』シリーズの主人公の一人である芝野に試練を与えることで、多くの人に響く普遍的な内容に落とし込もうと考えました。
ターンアラウンド・マネージャーである芝野はモノをつくれず、カネ勘定と、ヒトを切ることしかできない人間です。そんな彼が、油まみれになって働くような町工場に乗り込んで、企業再生に挑む。芝野の『スパイラル』での体験は、「立場が変わることによって、ものの考え方が変わる」という点において、実は多くの人にとって普遍的な体験ではないでしょうか。
たとえば、今の銀行では50歳を過ぎて役員が決まると、同期はみんな出向させられてしまいます。中堅企業の社長クラスならまだしも、どうかするともっと小さい会社に出向させられる人もいますよね。そうなったときに、外で通用する人と、通用しない人の違いは、環境の変化に順応できるかどうかなんです。
今までは「これコピーして」って言ったら誰かがやってくれる、「ここは組織変更すればいい話だろ」と気軽に言ってしまえる。そんな環境だったのに、出向先では「いえ、それは全部、部長一人でやってくださいね」と言われてしまう。これは、実は多くのビジネスマンにとって結構現実感のある話なのです。
そう考えて芝野を主人公に据えたのですが、この小説を書くうえで常に意識したのは、この話を芝野のための物語にしてはいけない、ということです。
芝野は自身に託された町工場“マジテック”を再生しようと、懸命に努力します。意地になってしまうこともある。しかし、会社にとってそれが必ずしもベストな選択につながるとは限りません。自分たちの資産を持っているうちに会社を解散させたほうが、傷が少なくて済むこともある。借金を重ねて商売を続けるのは、いったい誰のためなのかという視点を忘れてはならない。
資本主義の国なら、“自然の摂理”を重視すべき
──無理に投資をし、企業活動を創造することで関係者が幸せになるのかという問題提起は、『スパイラル』で何度も出てきますね。
日本の中小企業庁がやっていることは、あてずっぽうに選んだ企業に補助金をあげて、銀行の借金をとりあえずトントンにしているだけでしかない。補助金を受け取った中小企業経営者の多くは、資金を融資してもらっても、また潰してしまう。これを国やマスコミは「ものづくりの支援」と呼んでいます。
こうした中で問うべきなのは、「なぜ倒れようとするものを助けるのか」という、本作での鷲津(ハゲタカシリーズ本編の主人公)の問いかけです。
企業を生き物にたとえるならば、私たちは一人で生きることができない生き物を無理やり助けてしまっています。特に企業再生の場合は、企業の自立能力を厳しく見極める必要があります。弱肉強食の発想は資本主義の根幹となるものだと思うのですが、日本では、まるで社会福祉のように企業を助けてしまう。
でも、資本主義の国を標榜しているのであれば、“自然の摂理”の法則をもっと重視すべきです。
だから中小企業のマジテックがもがきあがく物語を延々と書くことで、「いい加減、いつ潰すんだ」ということを読者に感じてもらい、「それでも潰れないのは芝野の意地なのか? あるいは(社長の)浅子の意地なのか?」という疑問も読者に喚起したいと考えました。
(聞き手:野村高文、構成:ケイヒル・エミ、撮影:遠藤素子)
*続きは、明日掲載します。