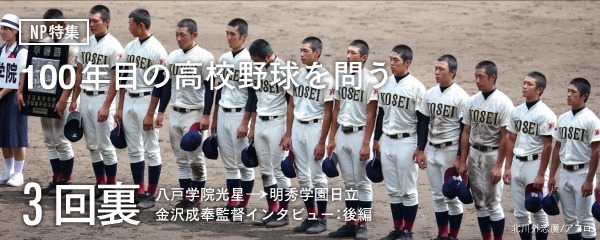【野球留学校の実態・後編】「文武両道なんてあり得ない」
2015/7/29
野球留学生を引き受ける覚悟
──現在、全国に高校野球部員は約17万人いて、そのうち毎年1万5000〜2万人が途中退部していると言われます(NPO法人ルーキーズ調べ)。金沢監督のチームでやめていく生徒はどれくらいいますか。
金沢 ほぼ、いないですね。
──どうすれば、やめさせないで済むのでしょうか。
やっぱり一番は、いかに深く関わるかですね。普段の顔色、顔つき、体調面も含めて、いかに把握するか。うちは寮なので、グラウンドの中と外で積極的に声をかけていきます。
それと、どんな補欠の子にもチャンスをあげていますね。特にうちの場合は県外から来ているので、ただただボール拾いだけで終わるっていうことはしませんでした。
うちでは「補欠」や「メンバー外」という言葉を使わず「育成メンバー」と呼んでいるのですが、彼らを3班くらいに分けて、3班はバッティング、2班はノック、1班はレギュラー組と一緒に練習、などとやっています。
野球をやりに来た子どもたちに対して、しっかりと野球をやらせてあげる環境はつくっていましたね。レギュラーの子たちと同じくらい、育成の子たちにも試合を組んでいます。
それと光星学院の頃は、野球の通知表をつくっていました。出場試合数や打席数、打率、防御率を出して、さらに1年間の生活状況を通知表のように書いて、年末年始に実家に帰るときに子どもたちに持たせていました。よその学校と比べて密なことをやっていたし、練習できるだけの環境もあったというわけです。
──密に付き合うには、監督にも覚悟が求められますね。
遠くまで来て、ほぼ逃げ道をなくして来ている子たちに関して、その子の人生をわれわれが背負ったようなかたちになりますからね。僕に限らず、野球で県外から来る子の指導をされている監督は、同じような強い覚悟がなければできない気がします。

金沢成奉(かなざわ・せいほう)
1966年生まれ。大阪で高校時代を過ごし、東北福祉大学に進学。1995年光星学院の監督に就任。春夏通算8度の甲子園出場に導き、2011年夏から3季連続の準優勝を果たした(2010年3月以降は総監督として指導)。2012年、明秀学園日立の監督に就任。今年の夏は茨城大会で準決勝進出に導いている。打撃理論に定評があり、教え子に坂本勇人(巨人)、田村龍弘(ロッテ)、北條史也(阪神)など。(撮影:中島大輔)
バッシングを受け止め、ベストミックスで甲子園へ
──金沢監督は光星学院で結果を出したので、さまざまなオファーがあったと想像します。そんな中、光星の監督に就任した頃と同じような環境の明秀学園日立での仕事を引き受けたのは、なぜですか。
僕が八戸に行くまで、光星は1回も甲子園に出ていませんでした。当時は甲子園の抽選会で青森の学校を引いたら、ガッツポーズされていたような時代です。「日本一」なんて口にしたら笑い飛ばされるような状況の中、本気で目指して県外からも人を獲ってきました。
最初は本当にすごかったです、バッシングが。「あんなの全部、野球留学生じゃないか」って。僕は積極的に野球留学生を獲りましたけれど、でも、そこだけでは終わろうとしなかった。野球留学生を起爆剤にして、学校が強くなって、地元の子たちも来てくれるようになって地域が発展すればいいと思って、ずっとやり続けてきました。
最初は笑い飛ばされていたところから徐々に認められるようになって、初めて甲子園に出たときにはベストミックス状態で、県内の子たちも半分くらい出場していましたね。その中で青森勢として32年ぶりにベスト4に入ったとき、あの青森県の感動が身に染みて感じていますので。
──それを明秀日立でも味わいたいわけですね。
そうです。茨城の県北からは25年以上、甲子園に出ていないんですね。「3.11」の震災で、少なからず日立も影響があったわけです。そういう話を理事長に聞いて、青森とリンクしました。
日立は八戸とほとんど似ているんですよね。関東ですけれども、果てしなく東北人に近い。「そこを何とかしたい」っていう思いはあります。よその血を入れることに賛否両論があるにせよ、みんなが地域のことを思っていくようにしていけば、必ず成功につながる。青森でそういうモデルとなる学校を経験しているので、日立でもそれをやりたいという強い思いはありますよね。
「364日苦しくて、たった1日の喜びのためにやっている」
──大学や社会人ではなく、高校野球で監督をすることにこだわっていますか。
やっぱり、高校だからですね。高校野球の魅力にはまっていますので。
──高校野球の魅力はどこにありますか。
なんて言うのか、成熟していない子どもたちが、目に見えて成長する過程がわかるっていうんですかね。結局エゴイストなのかもわからないんですけれど、自分の指導するかたちが姿となって、かたちとなって表れるのが高校生だと思うんですよ。その後の子どもたちの人生にかなりの影響を与えやすいですしね。
その大変さはすごくありますけれど、大変な分だけ成長度がわかる楽しさっていうのかな。それはやってみないとわからない気がします。僕らは364日苦しくて、たった1日の喜びのためにやっている。その1日の喜びがすべての苦しさを吹き飛ばすくらいの魅力が、やっぱり高校野球、甲子園にはあるんじゃないかなと思うんですよね。

2012年夏、光星学院は決勝で大阪桐蔭に敗れ、優勝旗を手にすることはできなかった。(写真:北川外志廣/アフロ)
野球留学生と365日、24時間同じ生活
──試合を行う場所は、甲子園でなければダメですか。
甲子園を目指すことに意義があると思います。甲子園じゃなきゃダメなんだと思う気持ちで日々過ごして、日々訓練することによって何かが生まれるので。その何かが生まれた部分が大事だと思うんですね。
それが「いや、いいんだ、お前ら。別に甲子園行けなくったって、第二の人生があるから」っていうような、ふわっとした部分で子どもらと接していても、そこに「何か」というのは生まれてこないと思うんですよね。
──高校野球の監督の大変さは、どんなところにありますか。
遠くから来た子たちと、大げさに言うと365日、24時間ほぼ同じような生活をしているわけです。僕はいつも「寮生活は戦争です」って言うんですけれど、気の休まるところがありません。
イジメなどの問題を出させず、「この学校、この仲間、この寮で育って良かった」って感じてもらうためには、生半可な気持ちでは子どもたちと一緒にやれないじゃないですか。
先ほど1万人の退部者がいるという話をしていましたけれど、それは寮生活をしていないチームのことだという気がするんですよね、たぶん。光星では通いの子もいましたけれど、明秀日立ではほとんど寮に入っています。そういう意味では、ほとんど逃げ道のない中でやっているわけです。
「野球があれば、人生を歩いていける」
──金沢監督は休日を取れていますか。
僕らは結局、どこまでが仕事なのか、切れ目がないんですよ。切ろうと思えば切れるし。休みは取りますけれど、完全休養日っていうのはほぼないわけなので。寮に子どもがいる限り、完全に体もすべても休められるというのはないですよね。
──自分で選んだ以上、やり抜くという覚悟なわけですね。
うん、覚悟だし、この言い方がベストなのかわからないですけれど、これが僕の職業だと思うので。
子どもたちにはいつも、「天は二物を与えないけれども、天は一物は与える」と言います。「俺もそうだけれど、お前らにとってもたぶん、一物は野球のことだろう。俺の場合、野球を教えるのが、人より多少うまいかもしれん。これが一番自分の中で得意な分野であって、野球があれば人生を歩んでいけると思うから、今これをやっている。お前らにとっても、野球が天から与えられた一物であると思う」って言うんです。
僕が集めている子たちは、勉強が多少できなくても、学校で先生に多少嫌われていても、野球というものさえやっていたら、必ずこういう道を歩いていけるんだっていう集団的な部分もあるんですよね。それも含めて僕の人生というか、天から与えられた職業だと思っています。
だから野球はできるけれど、勉強はできない子も獲ります。地域だけにこだわっちゃうと、なかなかそういうわけにはいかないですよね。
野球エリートの誇り
──金沢監督は生徒たちに勉強もさせるのですか。
させますよ。だから頭が良くなかったとしても、ちょっとずつ良くなっていきます。勉強の苦手な子たちをベースにいろいろ指導しているから、頭のいい子にはちょっとかわいそうな部分もあるんですけれどね。
でも僕、「文武両道なんてねえんだからな」ってよく言うんですよ。たとえば東大が六大学リーグで優勝したら、文武両道です。ハンカチ王子(斎藤佑樹)はひょっとしたら文武両道をしたかもわからない。でも、それ以外は文武両道ではないだろうって思います。
日立で言えば、日立一高っていう超進学校があります。子どもたちに言うのが、「日立一高がうちの野球部に勝ったら、これは文武両道だね。でも、俺は絶対負けないねん。なぜかというと、あの子らが得意な勉強をしている間、お前らは得意な野球をしているんだから、負けるはずがない。それを負かすような、文武両道でやっているような学校が出たら、それを俺らは見習うべきだ」と言っています。
簡単に文武両道って言いますけれど、昔の武士はちゃんと勉学したり、馬に乗ったり、弓を持ったりしていました。本当の文武両道で、鍛えたんだと思います。そういうレベルで本当に文武両道をやっている高校が今、どのくらいあるのかなとは思いますね。

明秀学園日立の校章。ちなみに日立一高は徒歩約5分の距離にある。(撮影:中島大輔)
常総学院にあって、明秀日立にないもの
──最後に聞かせてください。高校生だけでなく、最近の日本人は自分で考える力が弱いと言われています。高校野球の場合、どうやって考える力を養いますか。
まあ、難しい問題ですよね。うちが今、(茨城県で)準優勝で甘んじているのはそこの部分ですよね。自ら考えて、自ら行動して、自ら責任をとるのに欠けている子どもたちの集団なので。それを今、改めてやり直しているのは、結局行動力が欠如しているからだと思うんです。行動力を養うため、トーク式のミーティングをやらせてみたりしていますね。
──どんなことをするのですか。
みんなで話し合ったり、1分間スピーチで、自分の言葉で物を伝えるという作業を多く取り入れなければと思っていますね。言葉では「自ら考え、自ら行動して、自ら責任をとる」と言うけれど、それでも現状、なかなかできないので。だから、必ず自分を出せる場所というのをこの1カ月、与えるようにしてきました。
結局、それが常総学院にあって、うちにないものだと思います。子どもたちへの思いも経験も何も、僕のほうが子どもたちより勝っちゃっているんですよね。常総は木内(幸男)さんからの伝統があって、自分の考えで動ける子たちがいます。それはゲームをやると、すごくわかるので。
※編集部注:常総学院は茨城きっての名門私学。2011年まで率いていた名将・木内幸男に強化され、春夏通算23度甲子園に出場し、2度の全国制覇を達成。
それって、社会に出てもすごく大事なことですよね。野球で勝つためにも、それが今、うちのチームには必要だと思っています。自分で考える力を教えることが、最終的には試合で負けたとしても、社会に出て役立つことだと思っているので。
高校野球を通じ、苦難の乗り越え方を指導
われわれには寮があって、立派なグラウンドもつくってもらっています。ある意味、野球で採用されたような人間たちは、覚悟を持ってやっています。そこまで深く考えないと、甲子園まで勝てないと思うんですよ。そうすることで、さっき言った「何か」が生まれるんだと思います。
今、「なぜ勝てないのか?」と言ったら、逆にそういうところに原因があります。それを養っていくには、やっぱり深さだと思いますね。子どもたちとの関わり合いの深さが大事なんだと思うんです。
人生はきれいごとだけではありません。最終的には強いか弱いか、勝つか負けるか。うまいとか、下手とかは関係ありません。とにかく大事なのは、ボーダレスの21世紀の時代で生き抜くだけの力を養うために、自分自身を鍛えているのか、鍛えていないのか。その1点に尽きると僕はいつも言うんです。そのためには寮が必要だということです。
うちでやっていければ、どこに行っても生きていけるくらいのものを教えたい。人と人との調和であったり、あるいは苦難や苦境を乗り越えるという部分を含めてですね。そういう目的が高校野球には特にあると思います。
取材後記「野球留学で議論すべきこと」
2015年6月23日、日立から水戸まで明秀日立の練習に向かう中、金沢監督の運転する車中で1時間強、話をじっくり聞いた。「高校野球の功罪を考え直したい」と取材の意図を伝えると、包み隠さず胸の内を明かしてくれた。
前後編のインタビューを読んで、なお、野球留学に否定的な読者もいるだろう。だが、少なくとも選手たちや監督がどれほどの覚悟を抱いているのか、少しでも伝わっていれば幸いだ。
勉強だけ1日8時間行う高校生がバッシングされることはないだろうが、野球の練習に同じ時間没頭している者は批判の対象になることもある。高校生の本分は勉強であり、野球ばかりしていては勉強に支障が出るからだ。少なくとも、世間にはそう見る者もいる。
野球に限らず学校の指導者にとって、大きな仕事は学生たちの可能性を広げてあげることだ。勉強は当然得るものがあるし、受験対策に多い記憶式ではなく、思考力を養うようなものが望ましい。
「野球をやめたら、野球なんて何の役にも立たない」。学生野球を取材していて、時折指導者から耳にするセリフだ。もっともな意見だと思う。
だからこそ、野球を通じて何を学ぶかが重要だ。指導者は一方的に野球を詰め込むのではなく、野球を通じて「何か」を教えることが重要な職務になる。
一般社会において、大学に進んでなお、人生で何を極めようとするか、その答えを見い出せていない者は決して少なくない。一方で高校3年間、野球に打ち込み「何か」を学んだ者は、たとえプロ野球選手になれなくとも、その後の人生を生き抜く強さを身につけているはずである。
対して、指導者の言われるままに野球漬けの生活を送った者が、卒業後、路頭に迷うケースも見られる。自分で考える能力を養わないまま社会に出て、どうやって現状を打開すればいいのか、探し出すことができないからだ。
バッシングの対象になることもある「野球留学」だが、議論すべきはその是非ではなく、指導者や学校が野球を通じて「何か」を伝えようとしているか、その姿勢を持っているかだと思う。
(取材・文:中島大輔)