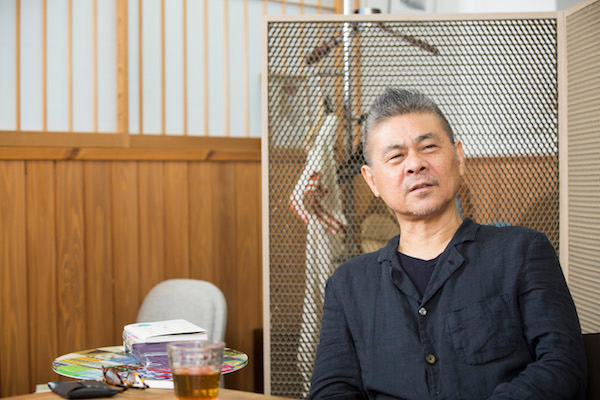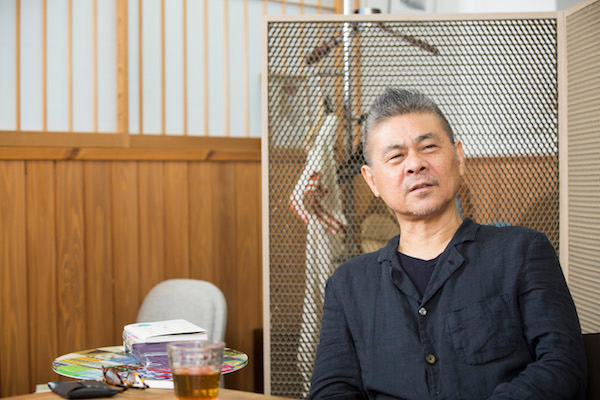大切なのは「ストーリー」か「絵」か
2015/10/6
作家の頭の中をパブリッシュする
糸井 ぼくが「ほぼ日」をやるときに、気づけてよかったのは「インターネットがこれからはやる」ってこと。
でもそれを言うと、「もう遅い」って言う人と「まだ早い」って言う人の2種類がいたんです。そのタイミングがもっと早くても遅くても同じだったわけで、ぼくが「インターネットの流れが弱まることはない」と思ったことは合ってた。
佐渡島 ええ。
糸井 佐渡島さんが今思ってらっしゃる「作品の質を担保して喜びを高めていこうという考え方は、貴重な価値だぞ」っていうのは、絶対合ってると思うんです。
姿勢とか意志とか憧れの在り方とかが合ってて、これを一生懸命本気でやってる人がいれば、ぼくはそれは「買い」だと思いますね。だから、疑う暇があったら何か考えてたほうがいいんじゃないですか?(笑)
佐渡島 そうですね。
そういうわけで作家エージェントを始めたんですが、最初は本当にITのことを知らなかったので、とりあえずは電子書籍などで作品をつくり続ければいいや、くらいに思ってたんですよ。
だけど、実は作品をつくり続けるだけじゃダメで、ITの変化っていうのがもっと全然大きいことだってことに気づいた。本や出版の在り方自体、発表のやり方自体も、完全に変わっていっちゃう可能性もある。
糸井 はい。
佐渡島 それに、物語自体も一直線で進むんじゃなくて、複数の方向性で進んでいくゲームブックみたいなものを書く小説家のほうが、それを小説家と呼ぶのかもわからないけども、そういうストーリーをつくる人間のほうがいいとされる時代が来るかもしれない。そんなふうにだんだん思うようになってきたんですね。
さらには、ストーリーを「ストーリーとして」売っていくっていうことすらも難しいんじゃないか、と。
「ほぼ日」って、「ほぼ日的なもの」を商品に落とし込んでますよね? 手帳とかジャムとか……。
糸井 ハラマキとか(笑)。
佐渡島 ハラマキとかに落とし込んでいってるじゃないですか。じゃあ、ほぼ日は手帳の会社なのかっていうと違いますよね? あくまで「ほぼ日的なもの」をいろんなものに落とし込んでいってるじゃないですか。
糸井 はい。
佐渡島 ぼくらも、ある作家がつくったストーリーの中にある世界観を、現実にあるいろいろなものに落とし込んでいこうと思ってるんです。服や靴の可能性もあれば、食べ物の可能性もある。すると、ストーリーが全産業に入っていけるんですよ。
あらゆる産業に入っていって商品を届けて、その商品のところのロイヤルティーで作家が食っていくみたいなことができるんじゃないかなあっていうふうに考えてるんです。
糸井 はいはい。
佐渡島 それで、最近は「作家の頭の中をパブリッシュする」というのを目指してるんです。パブリッシュというのは「出版」ということ以前に「公にする」って意味がありますよね。だから、作家の頭の中をどんどん公に広げていったら楽しいんじゃないか。
糸井 面白いですね。
佐渡島 作家の頭の中にある世界をビビッドに感じるために、ストーリーで読むだけじゃなくて、物もたくさんあれば、よりその世界に入っていける。
たとえば、物語を読んだ日に、その物語の中でおいしそうに食べてたケーキを食べることができる、とか。すると、自分でつくった料理とは違うおいしさを感じるはずで、そういうふうな「日常の経験の在り方」をストーリーによって変えることができると思うんです。そこまでまるごとセットで提供できる会社にしたい。
糸井 はい。
佐渡島 「ほぼ日的」っていうのは中心に糸井さんがいるんですけど、ぼくはそれを同時に「小山宙哉的」「安野モヨコ的」「三田紀房的」というまったく違う世界をいくつも作ろうとしている。そういう世界をつくり出していくっていうことが、ぼくが挑戦しようとしてることなのかなあ、っていうふうに思ったんですよ。
糸井 とても面白いと思います。
いわば「ハリウッドの創造」をしようとしてるんですよね。さまざまな映画監督をアンダーグラウンドから呼んでくる場合もあるし、外国人だったり亡命者だったりする場合もある。
ハリウッドって、いつでも「ハリウッド的なもの」を否定しながら伸びてきてるってところも面白い。A監督の世界観とB監督の世界観が、まったく異なってたり、ひょっとしたら相反するものだったり。
それを「るつぼ」のように持ってるのがハリウッドだと思うんですけど、そういうことを佐渡島さんが今、漠然と捉えられてるんだろうなって思って。そこはとても、まずは「ああ、面白いだろうな」と思います。
インスタグラムを楽しめない
糸井 ぼくと佐渡島さんの考えが、もしかしたら違うかもしれないなっていうのは、ぼくはストーリーの部分もすごく好きなんですけど、ストーリーっていうのは実は「二義的」なものじゃないかと思ってるんです。ですから、佐渡島さんの方法論ってかなりストーリー寄りなんですよ。『ドラゴン桜』とか。
佐渡島 ストーリー寄り。
糸井 はい。「詳細なシナリオに絵で肉付けをすると、面白い物語の中に一緒になって入っていけるよ」っていう非常に脚本家的な視点で考えてらっしゃる方だな、と。そこを「あ、それ特徴だな」と思ったことがあります。
佐渡島 はい。
糸井 ぼくももう少しストーリー寄りの人間かなと思ってたんですけど、大人になるにしたがって、そこ以上に重要なのが「説明しきれない絵の部分」だなと。絵の魅力。
谷川俊太郎さんも同じこと言ったんですけど、「絵本は絵だから」って(笑)。自分たちは書き手として絵のバックに回りますって。「好きだ!」とか「嫌いだ!」とか「おいしそう!」って言わせるのって、最後には「絵」だったりするわけですね。
今みんなが写真を撮って楽しんでるのも、ストーリーじゃないんですね。だから、ぼくと佐渡島さんがもし同じ会社だったら、「佐渡島派」と「糸井派」みたいに2方向展開していけたんじゃないかな。
佐渡島 ぼく、今、糸井さんがおっしゃったこと、すごく悩んでるんです。ぼくがストーリーを大切に思いすぎてるんです。
糸井 それは気づいてるわけですね(笑)。
佐渡島 そうなんです。
糸井 面白い(笑)。
佐渡島 だから、ぼく、インスタグラムってできないんですよ。インスタを楽しめない。でも、世界の多くはインスタだから(笑)。ぼくのほうがマイナーなんじゃないかなって。
ぼく、夢を言葉で見ちゃうときがあるんです。
糸井 はぁー……!
佐渡島 普通、夢って絵じゃないですか。でも、ぼくの夢は本を読んでる感じなんです。ずっと文章が朗読されてって、そのあとに絵になるっていう夢のほうが多かったりするんです。言葉がまずありきで。
糸井 その個性なんですね(笑)。
佐渡島 そう(笑)。それで、その言葉で理解していくときはストーリーが絶対必要で。
糸井 面白いね(笑)。
佐渡島 だから、写真に言葉がついてると、すごく好きになるときがあるんだけど、写真だけだと、とてつもなく好きになったこととかがあんまりなかったりするんです。
糸井 それは、これまでの作品に全部表れてますよね。
インスタにハマれる人がいるのは確かなんですけど、でもそれは「あるジャンル」にすぎないんですよ。ハリウッドっていうのはそうじゃないですよね。いろんなジャンルがある。
もう一人違う個性の人が自分の中にいればいいんじゃないかなって思うんです。「俺はお前のことわからん!」って言いながら同じ会社にいるっていうのが、会社の面白さですから。
佐渡島 そうですね。
糸井 ストーリーというのは、アメリカで神話研究がはやった時代に「だいたい、まあ、こうなるだろう」というのは大筋は理解されちゃった。そのあとは、ディテール、感覚みたいなところに至ってる。
ゲームが生まれてからは、「どこに連れていかれるんだろう」って手を引かれて楽しむ遊びはどんどん発達したんだと思うんです。
ぼくは、もうちょっと自分の中にある野性を目覚めさせるような、暗闇だけど一人で行ってみたいというようなものをやれないか。「平安時代の人でも喜ぶようなことしようよ」って、ぼくはよく言うんです。
佐渡島 確かに、パッと見て「面白い!」っていう感じがないと、なかなかヒットしないですよね。
糸井 『宇宙兄弟』とかも、最初はダメだったんですか?
佐渡島 全然ダメだったんです。
糸井 大ファンがいますよ、うちの会社(笑)。
佐渡島 あれももう5、6巻に行くまではもう全然ダメで。
糸井 面白いですねえ。
佐渡島 でも、今はみんな「1巻から面白い」っていうんです。だから、アマゾンのレビューも、初期の段階は3点の前半で伸び悩んでたんですけど、巻が進むにしたがって、5点つける人がいっぱいになってきて、いま平均は4点いくつになってるんですけど。
糸井 なるほど。取り返してるわけですね(笑)。
佐渡島 そうなんですよ。でも、それってぼくがストーリーを重視しすぎてることと重なっちゃってて。だから、ぼくがもっと「瞬間的なもの」にすごく興味があると、作家の人に対して、「はじめのほう、もっとこういうふうにしましょう」みたいなことができるかもしれなくて。
糸井 そうですね。
佐渡島 そこが弱さで、それでまあ、人数的には実はぼくのほうが少ないなとも思ってるから(笑)。
糸井 いやいや、「コンテンツを買う」っていうことからしたら、人数は拮抗してるんじゃないでしょうかね。
佐渡島 確かにそうですね。「買う」っていう部分で考えれば、そうなんです。だから、ストーリーのほうが説得力というか、買わせるところの納得させるところまでは行きやすかったりするんで。
糸井 そうそう。あと、価値が高いと思われやすい。
「通用しなかった5割ってなんだろう」と考え続ける
佐渡島 同時にぼくが考えてるのは、本などの閉じたパッケージの中でつくられたストーリーだと、全部「いいものの集まり」で感情の波を起こすんですね。
でも、インターネットの中だと、大したことないコンテンツであっても、ネットの中の波に乗せることによって、とても面白くさせることができるなあと思ってて。そういう「波の演出」みたいなのをどうやってやるんだろうってことを考えてるんです。
「今日のダーリン」って、やっぱり毎日消えていく、そのはかなさゆえに絶対毎日来ちゃうという強さも持ってるんだけれども、なかなか連続性の波というか、「今日の『今日のダーリン』を前の5回と合わせて読むとヤバいよ」みたいなつくりにはなってないじゃないですか。
ぼくの場合はもう常に波ばっかり考えちゃうんですよ。どういうふうにすればこの平凡な言葉が平凡に聞こえないか。
糸井 ちゃんとした人なんですよ(笑)。だから、ぼくみたいなことを考えてる人の右腕側に佐渡島さんがいたら、ものすごく楽ですよね。佐渡島さんがリーダーの会社でぼくみたいな人が右腕にいると、邪魔ですよね、きっと。
佐渡島 邪魔なんですかね。ありがたい気がしますけど。
糸井 そうですかね。だったら、「双頭の鷲」みたいになっちゃったほうがいいのかもしれないですね。けんかするだろうけどね(笑)。
佐渡島 (笑)。
糸井 ぼくのところに佐渡島さんがいたら、ぼくが「お前はわからず屋だ」と言って(笑)、「最後は俺が決める」と言って、ものすごく展開できると思いますね。
ぼくはそのビジュアル的なコミュニケーションや驚きや感性の部分って、もともと持ってたことなんだけど、「学び直した」ような気がするんです。
この学び直すというプロセスに結構時間がかかって、絶えず自己否定を入れながら学び直すってことをしていって、今に至るんですね。「現実がこうだから、それをどう分析するか」からいつもスタートするようにしたんです。
だから、佐渡島さんが考えてる「これは万全だな」と思ってることが、たとえば5割しか通用しなかったときに、「通じなかった5割って何なんだろう」というのを切実に考える。これを繰り返すと、「あ、わかった」となって6割通じるようになる、みたいなことがあるのかもしれないですね。
佐渡島 そうですね。
糸井 「ほぼ日」も17年やってきて、最初と今では、同じ面もいっぱいあるんですけど、だいぶ違ってますよ。
「5年前と今ではどれくらい変わったか」ってことを調べてきた社員がいたんです。売り上げや社員の人数、当時のコンテンツ。「この時代はこうでした」「今はこうです」っていうのを並べると、「え! 同じ会社には思えない!」ってくらい違うんです。
ということは、ぼくらが5年先を計画するときって、こうなんですよって話です。じわじわと変わったつもりでいたのに「別の会社?」ってくらい違う(笑)。でも、顔つきは同じなんです。
(取材・構成:竹村俊介〈ダイヤモンド社〉、撮影:福田俊介)